初心者にもわかるホールパート法とは?基本構造・目的・特徴から活用ポイントまで徹底解説
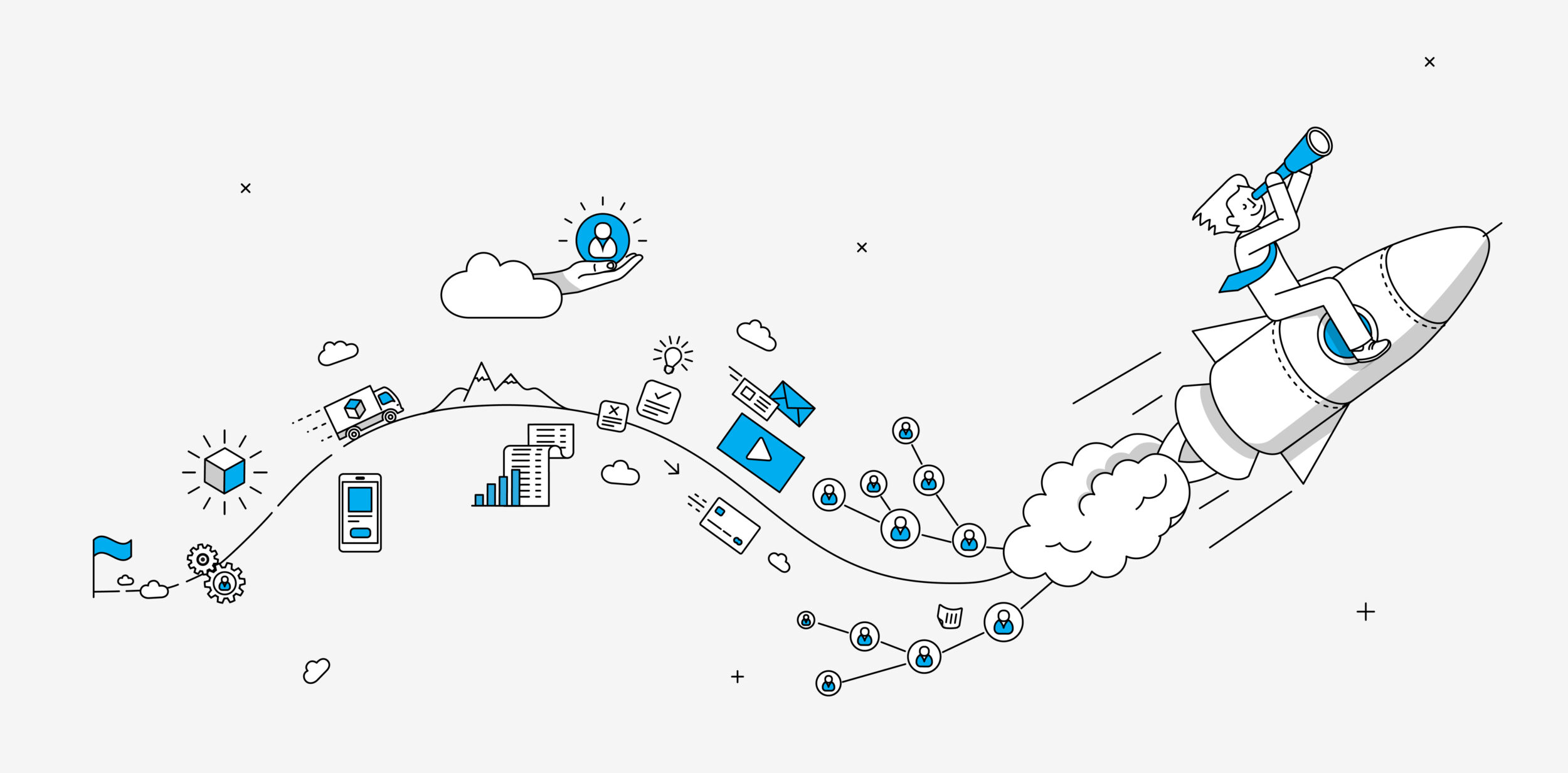
目次
- 1 初心者にもわかるホールパート法とは?基本構造・目的・特徴から活用ポイントまで徹底解説
- 2 ホールパート法の特徴:全体像を伝える説明法の仕組みとポイントを初心者にもわかりやすく徹底解説!実践のコツも紹介
- 3 ホールパート法のメリット:相手の理解度を大きく向上させ、説得力や効率をアップさせる効果が期待できるといえる
- 4 ホールパート法の構成と使い方:3ステップで分かる実践方法とポイントを初心者にもわかりやすく徹底解説
- 5 ホールパート法の例文:5つのビジネスシーン別具体例【営業・報告・説明】と解説、初心者にもわかりやすく
- 6 ホールパート法の応用場面:プレゼン・会議・スピーチなどビジネスシーン別活用例を詳しく紹介【完全解説】
- 7 ホールパート法とPREP法・SDS法の違い:それぞれの特徴と使い分け方を徹底解説、ポイントも紹介
初心者にもわかるホールパート法とは?基本構造・目的・特徴から活用ポイントまで徹底解説
ホールパート法は、最初に話の全体像や結論を示し、その後で各詳細部分を説明し、最後に再び全体像を伝える構造のコミュニケーション手法です。最初に大枠を提示することで聞き手の理解を促し、途中で詳細な説明をはさみ、最後にまとめ直すことで要点を強調します。ビジネスのプレゼンや報告など、複数の情報を効率よく伝える必要がある場面で活用され、聞き手の理解度向上や説得力の強化に効果的です。本章では、ホールパート法の基本構造や目的、特徴について初心者にもわかりやすく解説します。
ホールパート法の基本構造:Whole(全体)→Part(詳細)→Wholeの3ステップとは?分かりやすい構成を事例で解説
ホールパート法の基本構造は、〈ホール(Whole)〉→〈パート(Part)〉→〈ホール(Whole)〉の3ステップで成り立っています。まず冒頭で「本日のポイントは~です」と話全体の要点(ホール)を示し、次にその要点を支える各詳細を順番に説明(パート)します。最後にもう一度「つまり○○です」と結論を繰り返して全体像(ホール)に戻ります。例えば、会議の冒頭で「本日の議題は3つあります」と提示し、その3つを順に説明し、最後に「以上が3つの議題でした」とまとめる流れが典型例です。このように、ホール→パート→ホールの構成によって聞き手は話の全体像をつかみやすくなり、情報の理解が深まります。
ホールパート法の名称の由来と意味:WholeとPartを組み合わせて作られた言葉や背景を初心者にもわかりやすく解説
ホールパート法という名称は、英語の「Whole(ホール:全体)」と「Part(パート:部分)」を組み合わせた造語です。つまり「全体を提示して部分で説明し、再び全体に戻る」構成を表しています。ビジネスコミュニケーションの分野で、話の流れを明確にするために用いられるようになりました。全体像を先に示す手法は、もともと教育やプレゼンテーション技法として古くから存在しますが、近年になって会議や報告の場面で意識的に使われるようになったことから、この名が広まりました。本項では、ホールパート法という名前の由来や開発背景を初心者にもわかりやすく解説します。
ホールパート法が注目される理由:複数の情報を整理し効率よく伝えるビジネスコミュニケーションの重要性を解説
ホールパート法がビジネスで注目される理由は、限られた時間内に複数の情報を整理して伝える際に非常に有効だからです。現代のビジネスシーンでは、複数の案件や要点を短時間で共有する必要が多く、聞き手も多くの情報に触れることが求められます。ホールパート法ではまず全体像を明確化するため、聞き手は「何がポイントか」をすぐに理解できます。その後、各詳細を説明し、最後にまとめることで、話全体の流れが明確になります。このように「情報を最初に整理して提示することで情報量が多くても伝わりやすくなる」という仕組みこそが、ビジネスコミュニケーションでホールパート法が取り入れられる背景です。
ホールパート法が適している場面:複数の項目を簡潔にまとめて伝えたい時の使いどころについて具体的に解説
ホールパート法が特に適しているのは、複数の事柄や項目を簡潔に伝えたい場合です。例えば、会議で複数の議題を報告したり、営業提案で複数の製品特長を説明するシーンなどです。ポイントを並べる前に全体像を伝えることで、聞き手は事前に「何項目あるか」「何を伝えられるか」を把握できます。その結果、説明中に迷うことがなくなり、最後まで集中して聞いてもらえます。限られた時間で要点を効率的に説明したいとき、ホールパート法を使うと相手の理解を得やすくなるのです。本項では、具体的な事例を交えてホールパート法がどのような場面で効果を発揮するか解説します。
ホールパート法の準備:伝えたい要点の整理や構成を考えるポイントを初心者にもわかりやすく伝授します
ホールパート法を実践する前には、伝えたい要点の整理が欠かせません。まずは話す内容を洗い出し、重要な項目をリストアップしましょう。次に、その中から特に伝えたいポイントを3~5つ程度に絞ります。これらが「ホール」で伝える要旨となります。その後、各要点を支える具体的な内容(パート)を考え、順序立てて並べます。要点は相手が理解しやすい順序で構成し、漏れがないか再確認しましょう。最後に「ホール」として冒頭で提示する言葉を準備し、結論部分を締めくくる文章も用意しておきます。準備段階で内容を明確に整理しておけば、実際に話すときに話題が迷子にならず、聞き手にスムーズに伝わります。
ホールパート法の特徴:全体像を伝える説明法の仕組みとポイントを初心者にもわかりやすく徹底解説!実践のコツも紹介
ホールパート法の大きな特徴は、話の全体像を最初に提示する点です。全体像(ホール)を冒頭で示すことで、聞き手は「何を中心に聞けばいいか」が分かり、説明の全体構造を把握できます。逆に、全体を示さないと詳細を聞き始めたときに「結局何が言いたいのか?」と混乱しがちです。また、説明の最後に再び結論を伝えることで、最も伝えたいポイントを強調し、相手の記憶に残りやすくします。ホールパート法ではこの最初と最後に結論を置く形になるため、要点を二度提示して強く印象づけられるのです。さらに、必要な情報だけにフォーカスする構造になっており、余計な情報が省かれる点も大きな特徴です。以下では、ホールパート法の主なポイントを詳しく解説します。
全体像を先に示すメリット:伝えたい要点を冒頭で明確に提示する意図、その仕組みと効果について初心者にもわかりやすく解説
全体像の明示は、ホールパート法のもっとも重要なポイントです。プレゼンや報告の冒頭で「今日は○つの話があります」「結論から言うと△△です」と述べることで、相手にあらかじめ要点を共有します。これにより聞き手は、あとで説明される各項目がどの結論に紐づくのか認識しやすくなります。全体像を示す意図は、「話のゴール地点を最初に教えておく」ことです。導入時点で要点が明示されるため、細かい説明を聞く準備ができ、理解度が高まります。結果として、聞き手は「前提条件」が頭に入った上で詳細を聞くため、情報の受け止め方がスムーズになります。
重複の効果:繰り返し構造で理解を強化し、結論を記憶に残す仕組みを初心者にもわかりやすく解説
ホールパート法では結論を冒頭と最後の2回に分けて伝えます。この結論の重複効果により、聞き手は重要なポイントを反復的に理解できます。具体的には、最初に「○○です」と聞き、その後の説明で細かい情報を得たあと、最後に再度「つまり○○です」と繰り返されると、情報が記憶に定着しやすくなります。この仕組みは学習理論でも知られ、復習効果とも呼ばれます。たとえば研修で新しい知識を学ぶときも、重要な部分を2度聴くことで理解が深まるのと同じ原理です。ホールパート法では、この重複を意図的に使うことで、説得力を増し、聞き手の頭に「結論」を強く印象づけます。
情報の取捨選択:余計な話を省き、必要なポイントに集中させる方法を解説
ホールパート法では、話す前に要点を絞り込み、余計な情報は省く点が特徴です。重要なポイントだけを伝えることで、説明全体が簡潔になり、聞き手の混乱を防ぎます。具体的には、最初に「話すべき項目」を挙げ、それぞれに対応する詳細説明だけを行い、脇道にそれる話題はカットします。こうすることで、話が散漫にならずに集中力を保たせることができます。例えば3つのメリットを述べるなら、その3点以外は触れずに、結論や要点に絞って説明すると良いでしょう。この情報整理の方法により、時間の節約にもつながり、聞き手は必要な情報だけを効率的に理解できます。
ホールパート法ならではの構成:イントロ・詳細・まとめがシームレスにつながる理由を詳しく紹介
ホールパート法独特の流れは、イントロ(冒頭)・詳細・まとめの3段階が自然につながる点にあります。冒頭で話全体の概要を提示した後、各ポイントを順に説明し、最後に再度概要を示す構造は、とてもロジカルです。イントロで「5つの要点があります」と宣言すれば、次に紹介する詳細が5つだとすぐ分かります。そのまま1つ目~5つ目まで説明を進め、最後に「この5つがポイントでした」とまとめると、聞き手は「始めと終わりで同じ内容(5つ)を確認した」として認識できます。このように一貫した流れで話が進むため、説明全体にブレがなくなり、情報がシームレスに繋がるのです。
相手を飽きさせない工夫:全体像提示で先読みを促し、興味を引くテクニックを解説
ホールパート法では冒頭に結論を示すことで、聞き手の興味を引き付ける工夫ができます。先に要点を明かすと「この後○○が出てくるのか」と聞き手は内容を先読みしながら聞くようになります。これにより注意力が高まり、話を最後まで聞いてもらいやすくなります。例えば「今日は3つの新製品についてご紹介します」と始めれば、相手は「何が1つ目なのか」と集中します。興味を持たせた上で具体的な内容に入ると、話の脱線が防げます。また、まとめの部分で「繰り返しますが○○です」という形で冒頭の内容に戻すと、相手には一貫性が伝わり、納得感が生まれます。これらのポイントを意識することで、ホールパート法を使った説明はより効果的になります。
ホールパート法のメリット:相手の理解度を大きく向上させ、説得力や効率をアップさせる効果が期待できるといえる
ホールパート法を用いると、話の構造が整理され、相手の理解度や印象に良い影響を与えます。ここでは主なメリットを紹介します。まず、理解度が向上する点です。冒頭で要点を提示し、最後に再度結論を述べることで、聞き手は常に話の骨子を把握できます。そのため情報の吸収が効率化し、復習効果も生まれます。次に、説得力が高まる効果もあります。重要なポイントを最初と最後の2回で強調できるため、説得要素が相手に深く残ります。特に売り込みやプレゼンでメリットを伝える際は、この強調効果で記憶に残りやすくなります。さらに、伝達の効率化という利点もあります。余計な説明が減ることで短時間で必要な情報が伝えられ、会議時間の節約にも繋がります。最後に、話が整理されているので聞き手に信頼感やプロフェッショナルな印象を与えられる点も見逃せません。以上のように、ホールパート法には聞き手の理解を深め、説得力や効率を高める多くのメリットがあります。
理解度向上:冒頭とまとめで全体像を示し、聞き手に分かりやすく伝える効果を解説
理解度向上はホールパート法最大のメリットです。最初に結論を示すことで、聞き手は「何を学ぶか」の骨子を即座に理解します。その後の詳細説明はその前提をもとに進むため、話の全体像がぶれません。最後に再び結論を伝えると、「ああ、こういうことだったのか」という納得感が生まれます。例えば3つのポイントを挙げる場合、冒頭で「ポイントは3つあります」と伝え、各ポイント説明後に「この3点が大事です」とまとめると、聞き手の理解度が格段に上がります。このように要点が明確に示されることで、相手はスムーズに内容を受け入れられます。
説得力の強化:結論を繰り返し、伝えたい要素を強調して印象付ける効果、効果的な活用ポイントを紹介
説得力の強化もホールパート法の重要なメリットです。結論を冒頭と最後の2回で繰り返すため、聞き手は伝えたいメッセージを強く印象づけられます。特にプレゼンや提案では「要点を相手に納得させたい」ときに有効です。例えば製品のメリットを伝える場合は、冒頭で「この製品は①高速性、②耐久性、③省電力性の3つがメリットです」と示し、説明を重ねた後に再度「このように3つのメリットがあります」と復唱します。こうすることでメリットがより強調され、相手に深い印象を与えられます。また、話の最後に結論を言うクロージング効果も期待できるため、提案の説得力がさらに増します。要点の強調と組み合わせると、伝えたいメッセージが相手に残りやすくなります。
時間効率化:余計な内容を省いて必要情報に集中し、短時間で伝えられる利点を紹介
時間効率化も見逃せないメリットです。ホールパート法では先に要点を示すため、話の方向性が明確になり、詳細説明も脱線せずに進みます。結果として不要な情報を省くことができ、限られた時間内で必要なポイントだけを効率よく伝えられます。例えば報告事項が多い会議で「3件の重要報告があります」と示せば、参加者は各報告の重要性を理解した上で聞くので、議論はスムーズになります。余計な説明が減ることで会議時間が短縮され、ビジネス全体の時間活用も向上します。
記憶定着:結論を再提示することで学習・記憶が促進される仕組みと復習効果を紹介
記憶定着の効果も大きな利点です。ホールパート法では結論を2回聞くため、自然と情報の「復習」が行われる状態になります。人間の記憶は、同じ情報を複数回聞くことで定着しやすくなります。例えばセミナーで新知識を学ぶときも、要点が繰り返されると理解が深まるのと同じです。ホールパート法では説明後に結論を繰り返すことで、聞き手は内容を整理しやすくなり、長期的にも記憶に残りやすくなります。この仕組みによって、聞き手は自然と要点の再確認をすることができ、内容の習得が効率的に進みます。
プロの印象を与える:構造化された説明は聞き手に安心感と信頼感を与えることを解説
プロの印象を与えられる点もメリットです。ホールパート法で話すと、説明が論理的で整理されているように聞き手には映ります。聞き手は自分が段階的に案内されていると感じるため、話し手に安心感を抱きやすくなります。例えば情報が無秩序に飛び交う人よりも、最初から最後まで道筋が明確な話し手の方が信頼感が増します。構造化された説明は「この人の説明はわかりやすい」「論理的だ」と評価されるため、結果的に話し手への信用も高まります。
ホールパート法の構成と使い方:3ステップで分かる実践方法とポイントを初心者にもわかりやすく徹底解説
ホールパート法を実際に使うには、前述の3ステップ(全体像提示→詳細説明→まとめ)を意識して構成を組み立てることが大切です。ここではそれぞれのステップのポイントと、実践に役立つコツを初心者向けに解説します。
ホールパート法の3ステップ:全体像提示→詳細説明→まとめで構成される流れを初心者にもわかりやすく解説
ホールパート法の構成は大きく3ステップに分かれます。ステップ1(導入)では、話の冒頭で全体像や結論を伝えます。このとき、伝えるべき複数の要点を箇条書きで示してもよいでしょう。次に、ステップ2(本文)で各要点について順番に詳しく説明します。ここでは例やデータを交えて具体的に話すことがポイントです。最後に、ステップ3(まとめ)で再び最初の結論や重要ポイントを提示し、話を締めくくります。このように「全体→詳細→全体」の構成を守ることで、聞き手が迷わず内容を理解できます。
ステップ1(導入):全体像や要点を冒頭で伝える効果的な方法と具体例を解説
ステップ1:導入部分では、聞き手に最初に全体像を伝えます。例えば「本日の提案は3点あります」と結論を先に述べたり、「○○についてお話します」と主題を明確にします。このときのコツは、端的でわかりやすい表現を使うことです。具体例として、「我が社の新製品の強みは3つあります。まず1つ目は~、2つ目は~、3つ目は~です」というように話します。冒頭で全体像を提示することで、聞き手は「これから何を聞くのか」が明確になります。その結果、本文の詳細を聞いてもらいやすくなり、話全体がスムーズに始まります。
ステップ2(本文):各パートを順序立てて詳しく説明するための工夫:箇条書きや図解を活用するポイントを解説
ステップ2:本文部分では、導入で示した各要点(パート)を順番に詳しく説明します。ポイントは論理的かつ具体的に伝えることです。各パートごとに小見出しや番号を使って話すと聞き手がついていきやすくなります。また、箇条書きや図解を取り入れると視覚的に理解しやすくなります。例えば「ひとつ目のポイントは○○です」と言葉で説明した後、図やグラフで数値を示すと効果的です。各パートは「要点→理由→具体例」の順で話すと論理が通りやすくなり、相手に説得力を持って伝えられます。
ステップ3(まとめ):冒頭で提示した結論を再度伝え、話を効果的に締めくくるコツを初心者にもわかりやすく解説
ステップ3:まとめ部分では、冒頭に伝えた結論を再び示して話を締めくくります。例えば「改めてまとめますと、今回の提案のポイントは○○でした」という形で表現します。コツは、詳細説明で話した内容を簡潔に言い換えながら、元の結論につなげることです。最後に「質問はありますか?」や「以上で終了です」と受け答えを促すフレーズを加えると、聞き手は話が終わったことを明確に認識できます。まとめをしっかり行うことで、相手にはきちんと理解した安心感と、話し手の自信が伝わります。
導入前の準備:伝えたい内容を洗い出し、各パートの要点を作成する効率的な方法を解説
ホールパート法を効果的に使うには、事前準備も重要です。まず、伝えたい内容の全体像を把握するため、話すテーマに関するポイントをブレインストーミングで洗い出します。次に、それらの中から特に重要な要点を選別し、全体像(ホール)に当たる結論を決めます。続いて、各要点ごとに補足情報や具体例をリストアップし、説明の順序を考えます。最後に、「はじめに言った通り、○○です」と言えるような結論の再提示文も準備しておくとよいでしょう。これらを整理しておくことで、本番では話の構成を意識せずとも自然とホールパート法が実践できるようになります。
ホールパート法の例文:5つのビジネスシーン別具体例【営業・報告・説明】と解説、初心者にもわかりやすく
ここではホールパート法を用いたビジネスシーン別の例文を紹介します。例文を読むことで、実際にどのような流れで説明すればよいかイメージしやすくなります。
例文1:商談・提案の場面
全体像(ホール):本日の提案ポイントは2つあります。
部分1(パート):1つ目はコスト削減です。新システム導入により、年間500万円のコスト削減が見込まれます。
部分2(パート):2つ目は生産性向上です。最新の機器を使用することで、作業効率が20%向上します。
全体像(ホール):以上のとおり、新システムは「コスト削減」と「生産性向上」の2つのメリットがあります。
例文2:会議・報告の場面
全体像(ホール):報告事項は3点あります。
部分1(パート):1点目は売上報告です。今期は目標を10%超過して達成しました。
部分2(パート):2点目は経費報告です。無駄な経費を削減し、予算内に収まりました。
部分3(パート):3点目は来季の計画です。新商品の投入により市場拡大を目指します。
全体像(ホール):以上3点の報告でした。
例文3:プレゼンテーションの場面
全体像(ホール):当社新製品の魅力は3つあります。
部分1(パート):1つ目は高性能です。最新CPU搭載で処理速度が従来比2倍になります。
部分2(パート):2つ目は使いやすさです。初心者でも直感的に操作できるUIを備えています。
部分3(パート):3つ目は安全性です。業界最高水準のセキュリティ機能が組み込まれています。
全体像(ホール):つまり、新製品は「高性能・使いやすさ・安全性」という3つのポイントが特長です。
例文4:社内ミーティングの場面
全体像(ホール):本日の議題は4点です。
部分1(パート):1点目はプロジェクト進捗です。予定通り50%完了しています。
部分2(パート):2点目は品質問題です。先週発生した不具合への対応が完了しました。
部分3(パート):3点目は人員計画です。増員体制でリソースを確保します。
部分4(パート):4点目は予算管理です。現状では収支が均衡しています。
全体像(ホール):以上4点を議論しました。
例文5:教育研修・説明の場面
全体像(ホール):新人研修で学ぶべきポイントは2つあります。
部分1(パート):1つ目は報告・連絡・相談です。業務上の重要なコミュニケーション原則を理解します。
部分2(パート):2つ目はビジネスマナーです。敬語の使い方や身だしなみの基本を学びます。
全体像(ホール):つまり、新人が身につけるべきは「連絡・相談」と「マナー」の2点です。
ホールパート法の応用場面:プレゼン・会議・スピーチなどビジネスシーン別活用例を詳しく紹介【完全解説】
ホールパート法は様々なビジネスシーンで活用できます。以下では代表的な場面ごとに使い方のポイントと効果を解説します。
プレゼンテーションでの活用:複数提案の整理に役立つホールパート法の実例と成功事例を紹介
プレゼンテーションでは、聞き手を引き込むために冒頭で要点を伝えることが重要です。例えば「本日は3つの新戦略を提案します」と最初に伝えると、相手は話の展開を予想でき安心して聞けます。各戦略の詳細を順に説明し、最後に3つのポイントを再度まとめることで、提案内容を相手に強く印象付けられます。この構成を用いた結果、聴衆の理解度が上がり、プレゼン成功につながった事例も多く報告されています。
会議・打ち合わせでの活用:議題を効率的に伝えてスムーズな進行を促すホールパート法の仕組みとポイント
会議や打ち合わせでは、限られた時間で複数の議題を扱うことが多いです。ホールパート法を使って「本日の議題は3点あります」と冒頭で示すと、参加者は計画を立てやすくなります。その後、1つずつ議題を説明し、最後に「以上3点です」と締めくくると、議題が漏れなくカバーされます。これにより「いつまで続くのか」といった不安が解消され、会議の流れがスムーズになります。
営業・商談の応用:複数商品のメリットを分かりやすく伝えるホールパート法の活用例とポイント
営業・商談の場面では、複数の商品やサービスのメリットを伝える機会があります。ホールパート法では冒頭に「本日は2つの提案があります」と伝え、商品の強み1つ目、2つ目を順に説明し、最後に「このように2つのメリットがあります」とまとめます。こうすることで相手はそれぞれの利点を整理して聞けます。メリットを繰り返すことで説得力が増し、契約成立につながるケースも多いです。
教育・研修シーンでの応用:研修内容や作業手順を整理して教えるホールパート法の活用例とメリット
研修や教育の場では、学習項目が複数ある場合にホールパート法が有効です。例えば新人研修で2つの重要事項を教えるとき、「ポイントは2つです」と全体像を示し、各項目を説明して最後に繰り返すと受講者は内容を整理しやすくなります。これにより研修の効率が高まり、学習効果も向上します。
日常コミュニケーションでの使用:報告・説明などでホールパート法を活かすテクニックを紹介
普段の報告や説明でもホールパート法を使うと、相手に分かりやすい伝え方ができます。例えば「本日の連絡事項は3点あります」と切り出し、各項目を説明し、最後に「以上3点です」とまとめると、相手は重要事項を見逃しません。特に上司への報告などでは短時間で要点を押さえられるため、ホールパート法を活用すると効率的にコミュニケーションできます。
ホールパート法とPREP法・SDS法の違い:それぞれの特徴と使い分け方を徹底解説、ポイントも紹介
ホールパート法の他にも、論理的な説明手法には「PREP法」や「SDS法」などがあります。それぞれ構成や目的が異なるため、状況に応じて使い分けることで、より効果的な説明ができます。以下に各手法の概要と違いを解説します。
PREP法とは:結論・理由・具体例・再結論の順で伝えるプレゼンテーションの構成と説明
PREP法は、まずPoint(結論)を伝え、次にReason(理由)を示し、続いてExample(具体例)を述べ、最後に再びPoint(結論)を提示する構成です。ビジネスでは説得力を高める話し方として用いられます。例えば「私たちはリモートワークを推奨すべきです(結論)。なぜなら労働生産性が向上しコスト削減になるからです(理由)。実際、導入した企業では生産性が20%増加しました(具体例)。以上の理由からリモートワークを推進しましょう(結論)」。PREP法は一つの主張に焦点を当て、理由と例を丁寧に示して納得感を高めます。
SDS法とは:Summary(要点)・Detail(詳細)・Summary(要点)の構成で伝える手法を解説
SDS法は、「Summary(要点)→Detail(詳細)→Summary(要点)」の順で情報を伝える手法です。冒頭で概要(要点)を示し、続けて詳細を説明し、最後に再度要点を述べます。ホールパート法と非常に似ていますが、SDS法では特に一つの要点に絞って深掘りする点が特徴です。たとえば「健康の秘訣は○○です(要点)。その理由は~。これらにより健康が実現します(まとめ)」といった形で使います。SDS法はニュース番組のリード文などでも使われ、要点を明確にしながら詳細を簡潔に伝えるのに適しています。
ホールパート法 vs PREP法:複数項目を簡潔に説明 vs 単一項目で説得力を高める違い
ホールパート法とPREP法の主な違いは、対象とする情報の数と目的です。ホールパート法は複数の項目や要点を整理してわかりやすく説明することを目的とします。対してPREP法は一つの主張や項目について理由や例を用いて相手を納得させる手法です。つまり、複数のポイントを簡潔に示したいときにはホールパート法、ひとつのポイントを説得力高く伝えたいときにはPREP法が向いています。ビジネスの場面では「複数の改善策を一覧で示すならホールパート法、単一の提案の利点を深く説明するならPREP法」というように使い分けると効果的です。
ホールパート法 vs SDS法:要点を多項目で示す vs 一点集中で深掘りする違い
ホールパート法とSDS法はどちらも冒頭と結論で要点を伝える点は共通しています。しかし、ホールパート法は複数の要点を扱うのに対し、SDS法はひとつの要点をより詳細に掘り下げることに向いています。例えば「メリットを複数伝えたい」場合はホールパート法、「その中の最重要メリットを深く説明したい」場合はSDS法を選ぶとよいでしょう。また、ホールパート法では結論部分に複数のポイントを含められますが、SDS法では最初と最後の要点が同じになるのが特徴です。用途に応じて「多点列挙型(ホールパート) vs 深堀り型(SDS)」として使い分けます。
使い分けのコツ:相手・目的に応じて最適な説明手法を選ぶポイントを解説
最適な説明手法を選ぶポイントは、相手の立場や目的に合わせることです。もし複数の情報を手短に伝えたいならホールパート法が適しています。一方で説得が重要な場面ではPREP法、教育や詳細説明ではSDS法を活用しましょう。例えば上司に短い報告をする際はホールパート法で要点を箇条立てて示すと評価が上がり、取引先への提案ではPREP法で論理的に訴えると信頼度が増します。状況に応じた使い分けで、それぞれの手法を効果的に活かすことが重要です。















