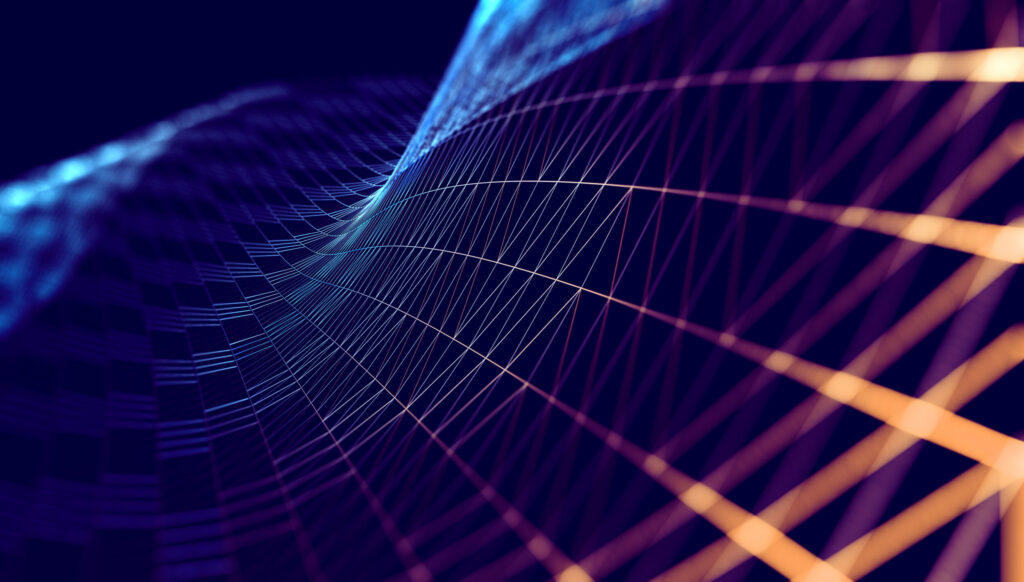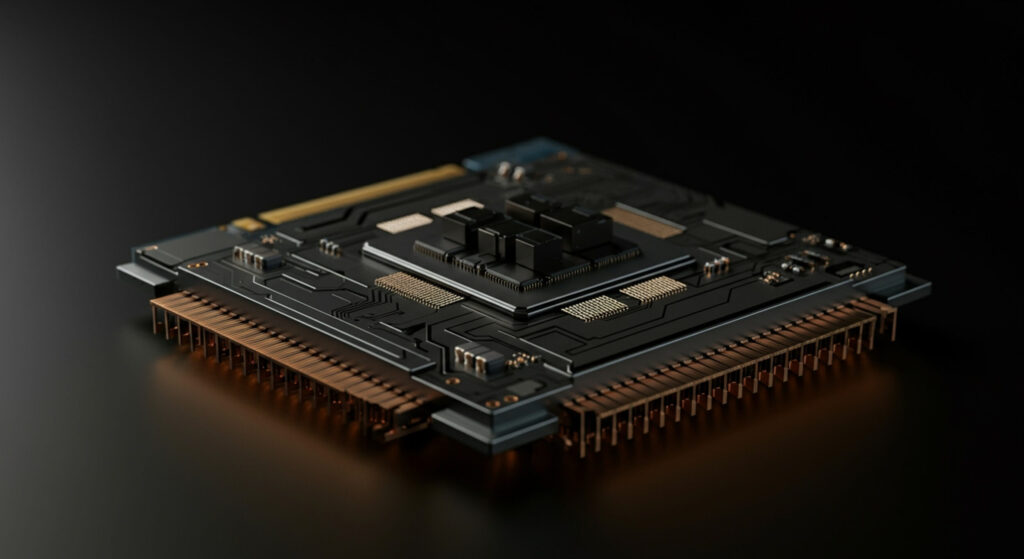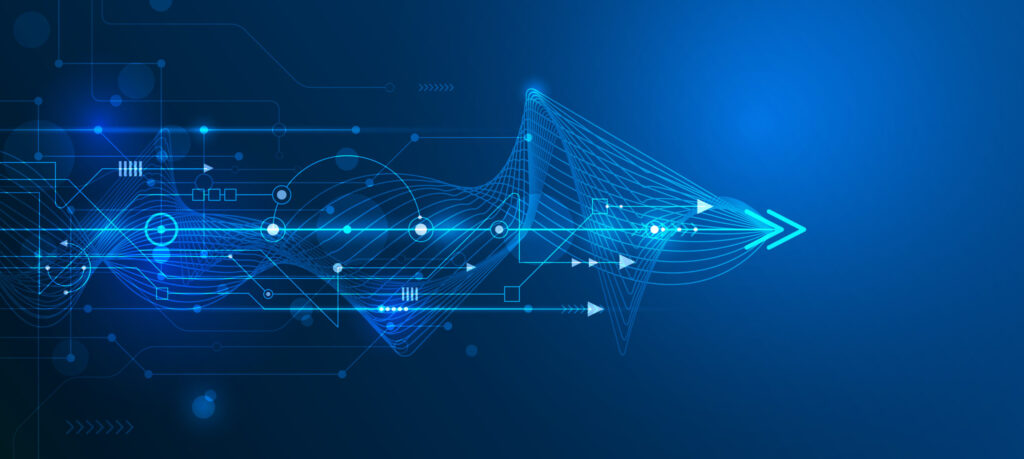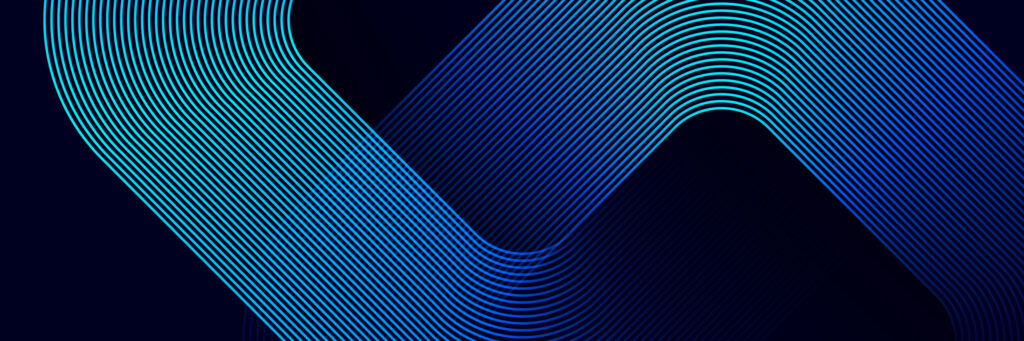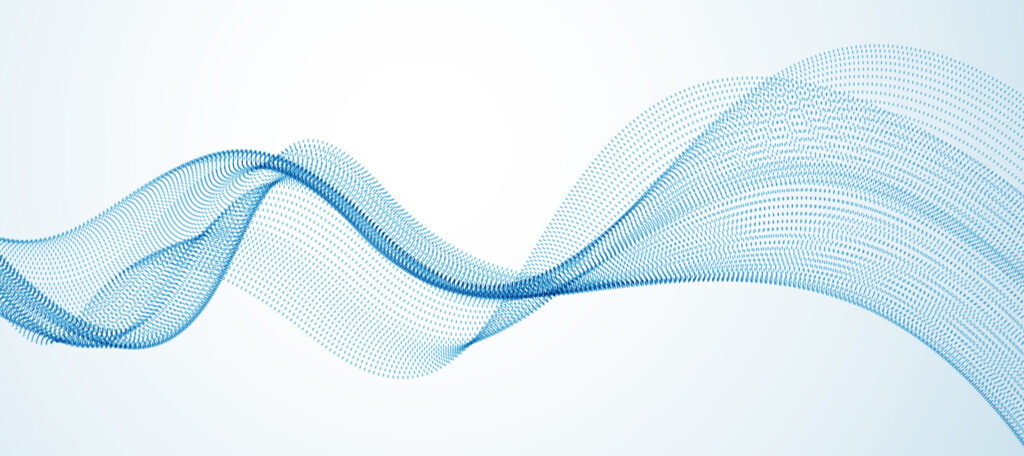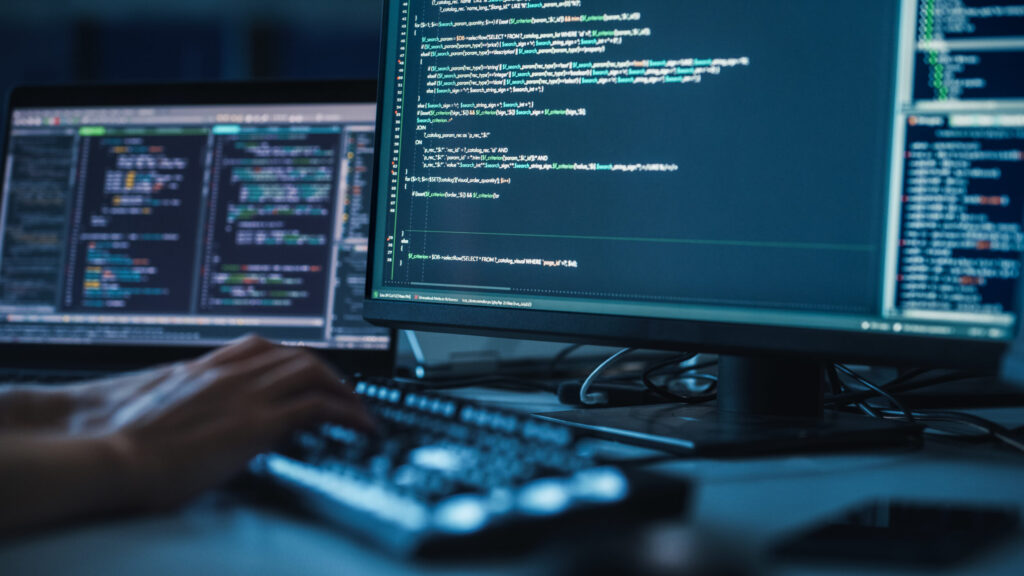Oracle Database 23aiの新機能とAI強化機能を徹底解説:パフォーマンス最適化とセキュリティ向上
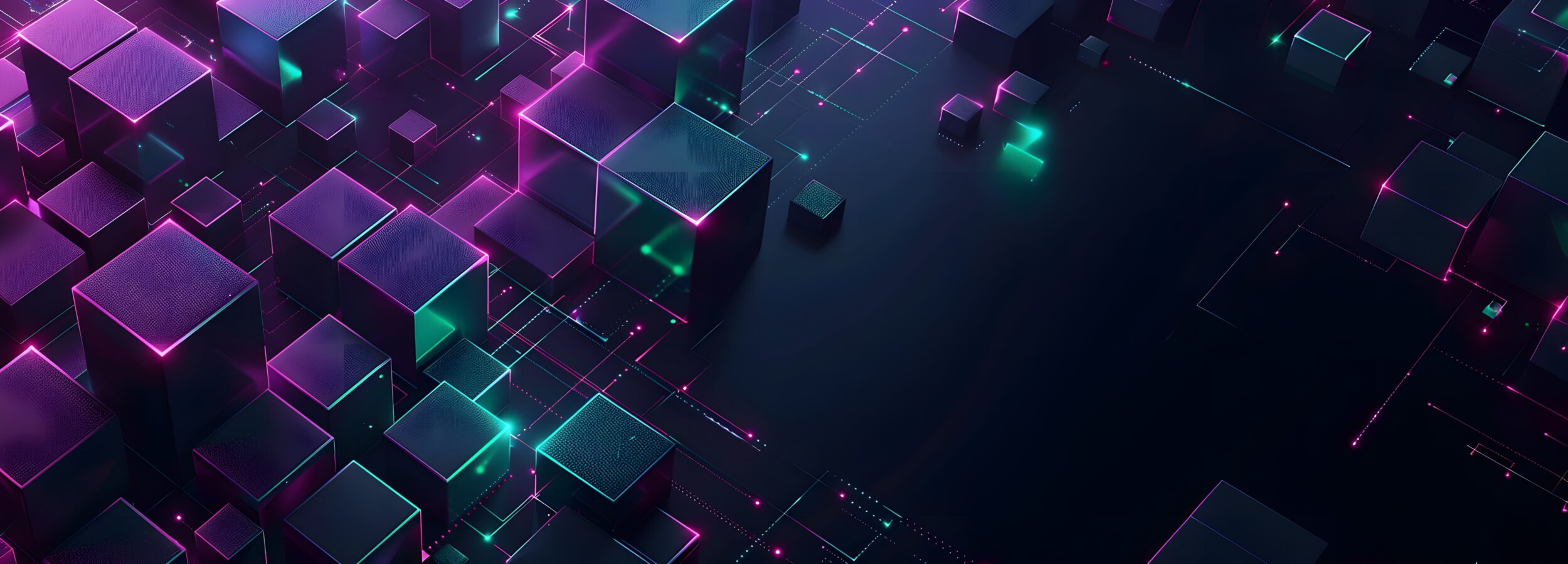
目次
- 1 Oracle Database 23aiの新機能とAI強化機能を徹底解説:パフォーマンス最適化とセキュリティ向上
- 2 Oracle AI Vector Searchの機能と活用事例:23aiで実現する概念検索と応用シナリオ
- 3 ベクトルデータベース入門:Oracle 23aiで始めるセマンティック検索の基礎から応用まで徹底ガイド
- 4 Oracle True Cacheの概要と導入手順:完全導入ガイドでデータベース高速化・可用性・性能向上
- 5 生成AIとOracle Database 23aiの連携:RAG構成や自然言語クエリ実装例での活用事例
- 6 開発者のためのOracle Database 23ai活用術:AI時代のアプリ開発戦略と実践事例集で解説
- 7 Oracle Database 23aiのクラウド限定リリースとFree版活用ガイド:導入メリット解説
- 8 Oracle Database 23cから23aiへの名称変更の背景と狙い:AI強化新時代を示すリリース名の意義
Oracle Database 23aiの新機能とAI強化機能を徹底解説:パフォーマンス最適化とセキュリティ向上
Oracle Database 23ai は最新の長期サポート版で、23c から名称が変更され、AI 活用を前面に出したリリースとなっています。このリリースでは AI 関連機能を含む300以上の新機能が追加されました。中でも、非構造化データやリレーショナルデータを概念レベルで検索できる AI Vector Search 機能や、プライマリ DB の読み取り専用レプリカとして動作するメモリ内キャッシュ True Cache が特徴的です。これらによりデータ移動を伴わずに AI 処理をデータベース内部で実行し、クエリ応答性や処理効率が大幅に向上します。さらに、23ai ではアクセス制御強化やデータ保護機能も追加され、セキュリティ面での強化も図られています。23ai は長期サポート版として 2029年までプレミアサポートが提供されるなど、エンタープライズでの信頼性も確保されています。
Oracle AI Vector Search機能の詳細:23aiで追加された概念検索の仕組みとユースケース
AI Vector Search は、ドキュメントや画像を LLM などで埋め込みベクトルに変換し、概念レベルでの検索を可能にする機能です。実際の導入例では、言語モデルにプロンプトを投げて得られた埋め込みベクトルをVECTOR型の列に格納します。その上で、VECTOR_DISTANCE関数や特別な演算子 <=> を使ってベクトル間の類似度を計算し、SQLクエリで似た内容を探索できます。Oracle のドキュメントでも、SQL上でプロンプトを実行してベクトル表現を得ることで、RAG(Retrieval-Augmented Generation)を実現できると説明されています。これにより、データ移動不要でDB内完結の AI 検索が可能となり、例えば社内ドキュメント検索や画像検索のユースケースで効率的な検索体験が得られます。
Oracle True Cache機能の概要:23aiで導入された新しい高速読み取りキャッシュの特徴
True Cache は Oracle 23ai で導入された新機能で、プライマリデータベースの読み取り専用レプリカとして機能するインメモリ・キャッシュです。最も参照頻度の高いデータを自動的にキャッシュしてデータベース負荷を軽減し、結果としてアプリケーションの応答性を向上させます。キャッシュ内容はリアルタイムにプライマリDBと同期されるため、常に一貫性のあるデータが提供されます。この仕組みにより、True Cache は高い可用性とスケーラビリティを実現し、特に高トラフィック時の読み取り性能を劇的に向上させます。さらに、生成AIの RAG ワークロードにおいては、大規模言語モデルへのアクセス結果をキャッシュすることで、LLM使用コストを削減する効果も期待できます。
セキュリティ強化点:23aiで追加されたデータ保護機能とアクセス制御の改善
Oracle 23ai ではセキュリティ機能も強化されています。たとえば、従来からの暗号化技術やユーザー管理機能に加えて、細かなアクセス制御ポリシーが導入されました。個々のテーブルや行レベルでのアクセス権限設定が可能となり、重要データへのアクセス権限をより厳密に管理できるようになりました。また、データベース間通信の暗号化や、監査ログ機能の拡充により、不正アクセス検知能力も向上しています。これらの機能追加により、ミッションクリティカルなシステムにおいてもセキュリティとコンプライアンス要件を満たしやすくなっています。
パフォーマンス最適化:23aiで強化されたクエリ処理とインメモリ最適化機能
23ai ではクエリ処理とインメモリ機能がさらに最適化され、高速なデータ分析を実現できます。インメモリ列ストアの自動サイズ調整機能により、ワークロードに応じてメモリが効率的に利用されます。また、複数段階のハッシュ結合やグループ集約を SIMD 命令で高速化する「In-Memory Deep Vectorization」(IMDV)の拡張により、複雑な分析クエリでも処理性能が向上しています。これらの最適化により、従来よりも大規模データを高速処理でき、リアルタイム分析のパフォーマンスが大幅に改善します。
その他新機能紹介:Global Data Services拡張やGraph Analytics強化など追加機能まとめ
このほか、Oracle Database 23ai では多数の機能拡張が行われています。Global Data Services(GDS)は高可用性構成のサポートが拡充され、大規模分散環境でのデータ管理が容易になりました。グラフデータベース機能でも機能強化が実施され、Property Graph の性能向上や Cypher クエリサポートの改善などで複雑なグラフ解析が効率化されています。加えて、OCI GoldenGate 23ai においてはベクトルデータのリアルタイム複製が可能になるなど、データ連携機能も強化されました。これら新機能により、従来のデータベース運用から AI・機械学習連携まで、幅広い用途への対応力が大幅に向上しています。
Oracle AI Vector Searchの機能と活用事例:23aiで実現する概念検索と応用シナリオ
Oracle Database 23ai の AI Vector Search 機能は、自然言語インターフェースと機械学習技術を組み合わせて、データベース内の非構造化データの検索を革新します。LLMから取得した埋め込みベクトルをデータベースに格納して処理することで、従来のキーワード検索では難しかった概念レベルの検索を可能にします。例えば、問い合わせ文書や製品画像と同様の意味を持つレコードを素早く抽出でき、ナレッジ検索や問い合わせ支援のユースケースに活用されています。これにより、データベースの情報を活用した次世代アプリケーション開発が加速し、AIパワードな検索体験が実現します。
AI Vector Searchの仕組み:埋め込みモデルとコサイン類似度による検索方法
セマンティック検索により、単語単位ではなく文書や画像の「意味」を理解して検索できます。これにより、たとえば商品のマニュアルやレポートの中から、ユーザーが思い描く概念にマッチする情報を抽出できます。実際に同義語や関連用語が含まれなくても、全体のコンテキストが同じものを検索結果に上げることが可能です。ビジネスデータ活用では、FAQ やナレッジベースから顧客の質問にマッチする回答を見つけたり、画像データベースから類似商品をリコメンドしたりといった応用が期待されています。これらの機能により、従来の全文検索では得られなかった精度と関連性が実現できます。
セマンティック検索の利点:概念検索でビジネスデータ活用を強化
具体的な活用例としては、社内文書管理や電子カタログでの検索があります。たとえば営業資料や設計図のテキスト説明を埋め込みベクトル化し、「セキュリティアップデート」というようなコンセプトでクエリすると、関連文書を簡単に抽出できます。また、製品画像をベクトル化し、類似した見た目の別製品を推薦する画像検索も可能です。これらの検索はすべて Oracle データベース上で完結するため、外部サービスへの依存なく安全に実行できます。実際に Oracle の導入事例では、エンタープライズDBに蓄積されたデータに対しシームレスに自然言語検索機能を組み込むことで、ユーザーの生産性向上につながったと報告されています。
活用事例:文章や画像の類似検索を実現するAI Vector Searchの具体例
AI Vector Search の基本的な導入手順は以下の通りです。まず、データベースにベクトル埋め込みを生成するための言語モデルを登録します。次に、ベクトルを格納する対象テーブルに VECTOR 型の列を追加し、テキストや画像データから埋め込みベクトルを生成してインサートします。データ登録後はベクトルインデックス(近似検索インデックス)を作成し、クエリ実行時の検索を高速化します。最後に、SELECT 文で WHERE embedding <=> :query_vector や VECTOR_DISTANCE 関数を使用して類似レコードを取得します。これらの手順により、自然言語から得たベクトルとデータベース内のベクトルを照合する仕組みが完成します。
導入ステップ:モデル登録からクエリ発行までの設定と実行手順
大量のベクトルデータ検索においては、近似検索インデックス(Approximate Index)の活用がポイントです。Oracle 23ai では高次元ベクトル向けのインデックスがサポートされており、膨大なデータから類似ベクトルを効率的に見つけられます。さらに、AI Vector Search は Exadata Smart Scan に対応し、ストレージレベルでも高速処理を実現します。データ量や次元数に応じて適切な索引方式を選択することで、大規模データセット上でも高速に回答結果を得られるよう設計されています。
パフォーマンス最適化:大規模データで高速なベクトル検索を実現する技術
Oracle 23ai 環境を用意するには、OCI上で23aiコンテナを立ち上げるか、ローカルで23ai Free版のDockerイメージを利用できます。Qiita によれば、以下のコマンドで23ai Free イメージを取得・起動できます:docker run -p 1521:1521 container-registry.oracle.com/database/free:23.4.0.0。起動後はデフォルトの管理ユーザーでログインし、パスワード設定や必要なユーザー作成を行い、前述のテーブルを作成します。これによりベクトルDBを試せる環境が整います。あとはサンプルデータを挿入し、クエリで結果を確認すれば、23ai上でのベクトル検索が体験できます。
ベクトルデータベース入門:Oracle 23aiで始めるセマンティック検索の基礎から応用まで徹底ガイド
ベクトルデータベースとは、テキストや画像などを数値ベクトルで表現し、その類似度をもとにデータ検索を行うシステムです。Oracle Database 23ai では、新たに提供される VECTOR 型列を用いてベクトルデータを格納できます。例えば、複数の文章を自然言語処理モデルで埋め込みベクトルに変換し、それらをテーブルに登録します。ベクトル間の類似度は VECTOR_DISTANCE 関数や <=> 演算子を使って算出でき、SQLクエリで距離の小さいデータを抽出します。ベクトルDBの特徴は、数値的に高次元なデータを扱うことで多様なデータ型を統一的に検索できる点にあります。実際の運用では、先述のようにベクトルを文字列として INSERT 文で格納することも可能で、アプリケーションから簡単にベクトル検索を利用できます。
ベクトルデータの基本:埋め込みベクトルとは何か、活用例を解説
埋め込みベクトルは、テキストや画像の内容を固定長の数値ベクトルで表現する技術です。深層学習モデル(LLMや画像モデルなど)を用いて生成され、言語意味や画像特徴を数値化します。ベクトル化されたデータは数値空間に配置されるため、ベクトル間距離が小さいほど元データも類似しているとみなされます。この性質を利用し、ベクトルDBでは類似度検索や近傍検索を行います。ビジネス例としては、ユーザーレビューや質問文の埋め込みから類似する過去問い合わせを見つけたり、画像のベクトルから似た見た目の製品画像を検索したりといった応用があります。
ベクトル格納方法:Oracle 23aiでのVECTORデータ型とテーブル定義方法
Oracle 23ai から追加された VECTOR 型を使うと、テーブルにベクトルデータを直接格納できます。たとえば以下のようにテーブルを定義します:CREATE TABLE galaxies (id NUMBER, name VARCHAR2(50), doc VARCHAR2(500), embedding VECTOR); その後、文章や画像の埋め込み結果を文字列表現で INSERT 文に渡すことでベクトルを保存できます。このようにデータベース上にベクトルを保持することで、SQLだけで類似検索が可能になります。保存したベクトルには通常の数値型と同じくインデックスを作成でき、検索効率を高めることができます。
ベクトルインデックス構築:正確検索と近似検索インデックスの違い
ベクトル検索ではインデックスが重要です。Oracle 23ai では高精度な正確検索インデックスと、高速に近似検索を実行する近似検索インデックスが提供されます。正確検索インデックスは完全な検索結果を返しますが、構築と検索に時間がかかります。一方、近似検索インデックスは検索結果に若干の誤差を許容する代わりに高速に処理できます。多くの場合、データセットのサイズに応じて近似検索インデックスを使用することで、実用的な速度で結果を返しつつ、精度をある程度担保できます。Oracle 23ai ではこれらを使い分けることで、ベクトルDB検索のスケーラビリティを向上させています。
環境構築とサンプル:Oracle 23aiでのベクトルDBセットアップ手順
Oracle 23ai 環境を用意するには、OCI上で23aiコンテナを立ち上げるか、ローカルで23ai Free版のDockerイメージを利用できます。Qiita によれば、以下のコマンドで23ai Free イメージを取得・起動できます:docker run -p 1521:1521 container-registry.oracle.com/database/free:23.4.0.0。起動後はデフォルトの管理ユーザーでログインし、パスワード設定や必要なユーザー作成を行い、前述のテーブルを作成します。これによりベクトルDBを試せる環境が整います。あとはサンプルデータを挿入し、クエリで結果を確認すれば、23ai上でのベクトル検索が体験できます。
Oracle True Cacheの概要と導入手順:完全導入ガイドでデータベース高速化・可用性・性能向上
Oracle True Cache は Oracle Database 23ai で新たに導入されたインメモリ読み取り専用キャッシュ機能です。プライマリデータベースの頻繁にアクセスされるデータを自動的にキャッシュし、アプリケーションに対して高速かつ一貫性のあるデータ提供を実現します。True Cache はプライマリ DB の完全な読み取り専用レプリカとして動作し、高い可用性を維持しながらデータベース負荷を軽減します。特に読み取り中心のワークロードが増加する大規模システムや、生成AIの RAG 実装で複数回同じデータを参照する場面で、大幅なパフォーマンス改善効果が期待できます。
True Cacheとは:インメモリ読み取り専用レプリカとしての機能概要
True Cache はプライマリデータベースの読み取り専用の完全なレプリカで、メモリ上にキャッシュを保持します。従来のキャッシュと異なり、キャッシュ内容の一貫性を自動的に管理し、プライマリ DB へのコミット時に即座に反映されます。これにより、True Cache はバックエンドの DB 処理を邪魔せず、大量の並列読み取り要求に対応可能です。また、JDBC などからはプライマリとキャッシュを透過的に切り替えて利用できるため、アプリケーションからは通常のデータベース接続と同様に True Cache を利用できます。
True Cacheのメリット:読み取り性能向上とデータ整合性の確保
True Cache を利用すると、読み取り処理をキャッシュでオフロードできるため、プライマリ DB の負荷が大幅に低減し、全体のレスポンスが向上します。データ変更がプライマリで行われても、キャッシュではリアルタイムに同期されるので、常に整合性のある最新データを提供します。また、True Cache はマルチスレッド対応で複数 CPU を活用するため、非常に高い並列処理性能を発揮します。結果として、ピーク時のトラフィックや DDoS 攻撃時にも安定した性能を保てるようになり、システム全体の可用性が向上します。
導入要件:アーカイブログモードなどTrue Cache前提条件と注意点
True Cache を導入するには、プライマリデータベースがアーカイブログモードで稼働し、レプリケーションのための適切な準備が必要です。また、パスワードファイルや TDE ウォレットをキャッシュノードにも複製する必要があります。Oracle データベース構成アシスタント(DBCA)を使用する場合は、-prepareTrueCacheConfigFile オプションでパスワードファイルを含む構成ファイル(BLOB)を作成し、キャッシュノードにコピーします。これにより、True Cache のインスタンス作成時に認証情報が自動適用されます。加えて、ネットワーク接続設定やリスナ設定などにも注意が必要で、適切に設定しないとキャッシュノードがプライマリに接続できない場合があります。
セットアップ手順:DBCAを使用したTrue Cacheインスタンス作成方法
True Cache インスタンスは Oracle Database Configuration Assistant (DBCA) を使って作成します。具体的には、True Cache ノード上で dbca -createTrueCache コマンドを実行し、Global Database Name やプライマリDBへの接続情報、事前に作成したBLOBファイルを指定します。この一連の作業により、True Cache サービスが構成され、キャッシュインスタンスが起動します。設定が完了した後、アプリケーション側では読み取り処理を True Cache へルーティングできるよう接続設定を行う必要があります。
利用シナリオ:Generative AIやRAGでのTrue Cacheを活用した例
True Cache は生成AIやRAG (Retrieval-Augmented Generation) のワークロードでも効果を発揮します。例えば、RAG の手法では大量のクエリでデータベースから情報を取得し、大規模言語モデルに組み込むため、同じデータへの読み取りが何度も発生しがちです。True Cache を使えばこれらの読み取りをキャッシュで処理できるため、LLM への問い合わせコストやレイテンシを大幅に削減できます。また、オンラインゲームやECサイトなど読み取り重視のアプリケーションでは、True Cache によりアクセス数の多いデータを高速に提供できるため、ユーザー体験の改善に直結します。
生成AIとOracle Database 23aiの連携:RAG構成や自然言語クエリ実装例での活用事例
Oracle Database 23ai は生成AIとの連携機能をネイティブにサポートしています。データベース内の企業データに対し、自然言語で質問を投げかけて回答を得る仕組みが実現されています。AI Vector Search の追加により、これまでクエリしにくかった非構造化データの内容を自然言語で検索できるようになりました。また、Oracle では SQL レベルで RAG を構築可能とされており、LLM への問い合わせ結果をベクトルストアからの情報で補強し、回答の精度を高める設計が可能です。このように、23ai を使った RAG 構成により、データベース内の情報と生成AIの力を組み合わせた高度な問答システムを構築できます。
23aiの生成AI機能:自然言語問い合わせとAIクエリ処理の概要
Oracle 23ai では生成AIを活用した新機能が多数追加されています。特に「AI Vector Search」によって、データベース内のビジネスデータに自然言語で問いかけ、関連情報を抽出できるようになりました。これにより、テキストや画像といった非構造化データへのアクセスが容易になります。また、SQL に新たに導入された SELECT … AI 構文を使うことで、アプリケーションから直接大規模言語モデルを呼び出し、自然言語クエリを実行することも可能です。これらの機能により、開発者はデータベースから直接生成AIを利用した問い合わせを行い、回答や次のアクションを得るアプリケーションを構築できます。
RAG概要:Retrieval-Augmented Generationの仕組みと必要性
RAG (Retrieval-Augmented Generation) とは、生成AIに対して外部情報を検索して補強する手法です。通常の生成AIはトレーニングデータに依存するため、最新情報や独自データへのアクセスが制限されます。RAGではまず検索エンジン(ここではAI Vector Search)で関連情報を取得し、その内容をプロンプトに追加して LLM に送信します。これにより、AIは回答に必要な具体的データを得た上で回答を生成するため、正確性や有用性が向上します。23ai ではこの RAG のワークフローをデータベース内で完結できる仕組みが整っており、セマンティック検索と LLM の組み合わせによって、効率的かつ安全に知識ベースから情報を抽出できます。
DB内RAG構築例:Vector SearchとLLM連携による実装手順
データベース上で RAG を構成するには、まずテーブルにセマンティック検索用の情報(文章やドキュメント)をベクトルとして格納します。次に、ユーザーからの自然言語質問を SQL 文(または新しい AI キーワードを用いたクエリ)で LLM に渡します。この際、データベース内で最も関連性の高いベクトル情報を取得し、その結果を LLM へのプロンプトに組み込むことで、LLM に最新かつ文脈に合った情報を提供します。最後に、LLM から返ってきた生成文をアプリケーションに返す流れです。この一連の処理を Oracle DB 内で実行することで、高度な検索機能と生成AI回答をシームレスに統合できます。
実装手順:Oracle 23ai上でRAGパイプラインを構築する方法
具体的には、まず RAG 用の「ベクトルテーブル」を作成し、対象ドキュメントをベクトル化して格納します。次に、AIモデルを呼び出すための AI プロファイルを設定し、SQL から LLM に接続できるようにします。そして、SQL 内で SELECT AI_TEXT(...) や AI_IMAGE(...) のような関数を使用し、ベクトル検索で取得した情報をプロンプトとして渡しながら LLM を呼び出します。Oracle の DBMS_CLOUD_AI パッケージを使うことで、これらの手順をシームレスに連携できます。最後に、LLM の返答をアプリケーションに返し、ユーザーに提示します。
活用事例:ドキュメント検索における生成AI回答システムの実例
実際のユースケースとしては、社内ナレッジベース検索システムがあります。例えば、技術文書や設計書を対象に RAG を構築し、ユーザーが自然言語で質問すると、それに関連する文書や抜粋を取得した上で LLM が回答を生成します。Oracle 23ai の AI Vector Search が文書の埋め込みから関連文書を絞り込み、LLM が回答を作成することで、人手では難しい質問への正確な回答が得られます。また、Azure 上の ChatGPT との連携例では、Oracle DB 上の顧客データやFAQを利用してチャットボットを構築し、リアルタイムで個別顧客に合った回答を提供する事例も報告されています。
開発者のためのOracle Database 23ai活用術:AI時代のアプリ開発戦略と実践事例集で解説
Oracle 23ai は開発者向けにも多くの新機能を備えています。開発者は JSON データとリレーショナルデータを透過的に組み合わせる「JSON Relational Duality」や、SQL から LLM を直接呼び出せる「Select AI」などにより、迅速に高度なアプリケーションを構築できます。特に Select AI 機能により、データベース内のメタデータを活用して自然言語から SQL クエリを自動生成したり、RAG を利用して最新データに基づいたチャットインターフェースを実現したりできます。これらの技術を利用すれば、従来以上に効率的な開発プロセスが可能となり、アプリケーションの生産性が大幅に向上します。
JSON Relational Duality:JSONとリレーショナルデータの双方向操作
JSON Relational Duality により、JSON ドキュメントとリレーショナルデータを同一視して操作できます。具体的には、JSON カラムを持つテーブルに対して SQL クエリと JSONPath 両方でアクセス可能になり、開発者は柔軟にデータモデルを構築できます。これにより、NoSQL 的な柔軟性とリレーショナルの強力なクエリ機能を両立でき、モデル変更やスキーマ変更のコストを削減しつつアプリケーション開発を高速化できます。
Select AIの使い方:SQLからLLMを呼び出し自然言語クエリする方法
Select AI 機能を使うと、SQL 文に新設された AI キーワードを使い、LLM との対話が可能になります。たとえば、SELECT AI('Generate sales report') FROM DUAL; のように記述することで、大規模言語モデルにクエリを投げて結果を取得できます。また、自然言語での問い合わせに基づいて SQL クエリを自動生成することもできるため、データベースに詳しくないユーザーでも直感的にデータ抽出を実行できます。開発者は DBMS_CLOUD_AI パッケージを使って AI プロファイルを管理し、セキュアかつ制御された環境でこれらの機能を利用できます。
グラフ機能強化:Property Graphと関連SQLの新機能活用法
Oracle 23ai ではプロパティグラフの機能が強化され、ANSI SQL/PGQ 準拠のクエリによってグラフデータを扱うことができます。これにより開発者はノードやエッジの属性を通常の SQL クエリで簡単に検索・集計できるようになりました。さらに、グラフと関係データを結合して分析できるため、組織内のデータ依存関係の可視化やレコメンデーション機能の実装が容易になります。これらのグラフ解析機能強化は、ソーシャルネットワーク分析や詐欺検知といった複雑なユースケースの開発をサポートします。
低コード開発:APEXやGenDevを利用したノーコード/ローコード開発支援
Oracle APEX などのローコード開発プラットフォームも、23ai の機能と連携可能です。GenDev(Generative Development)アプローチを活用すれば、開発者はデータモデルやアプリ設計を定義するだけで、AI を活用した UI やデータバインディングが自動生成されます。これにより、プログラミングの詳細に依存せずにセキュアでスケーラブルなエンタープライズアプリケーションを高速に作成できます。低コード環境でも高度な機能が使えることで、非エンジニアでも AI の価値を享受しやすくなります。
自動化開発戦略:GenDevに基づくマイクロサービスとAI統合の手法
GenDev では、宣言型言語や API 契約を重視した開発モデルが推奨されます。Oracle 23ai の機能を組み込むことで、マイクロサービス単位に必要なデータアクセスと AI 機能を定義可能です。たとえば、サービス間連携には GoldenGate でベクトルデータをレプリケートし、各サービスで独立したキャッシュ(True Cache)や検索機能を配置するといった構成が考えられます。これにより、開発者は AI とデータを密結合させながらも、モジュラーで可観測性の高いシステムを構築できます。
Oracle Database 23aiのクラウド限定リリースとFree版活用ガイド:導入メリット解説
Oracle Database 23ai は初期リリース時点でクラウド限定で提供されています。具体的には Oracle Cloud 上の Exadata Database Service や Base Database Service など一部サービスでのみ利用可能であり、オンプレミス版の正式提供は当面予定されていません。一方、開発や評価用途向けに23aiの Free版も公開されています。23ai Free では、2 CPU スレッド、2GB のメモリ、12GB のユーザーデータ領域など利用制限が設定されています。この Free版を使うことで、検証環境や学習用途で実際の23ai機能を手軽に試せます。ただし、Free版には機能制限があるため、本番利用には有償版へのアップグレードが必要です。
クラウド限定リリース:23aiの提供がOCIのBase Database Serviceに限定される理由
2024年5月時点で、23aiの正式版は Oracle Cloud Infrastructure 上のみリリースされています。これは新しい長期サポート版をクラウドで迅速に展開し、検証フィードバックを得るための方針とみられます。Base Database Service(旧 Database Cloud Service)や Exadata サービス上でのみ利用可能であり、OCI のほかのサービスやオンプレミスにはまだ対応していません。Oracle は今後オンプレミス向け提供も計画していますが、しばらくはクラウド環境での利用が中心になります。
23ai Free版概要:2スレッドCPU/2GBメモリなどリソース制限と主な機能
23ai Free版は、無償で提供される23aiのエディションです。利用可能なリソースは、CPU 2スレッド、メモリ 2GB、ユーザーデータ容量12GB といった制限があります。Free版でも多くの 23ai 機能(AI Vector Search、True Cache など)は利用できますが、RAC や Data Guard など一部のエンタープライズ機能は含まれていません。リリース当初は Linux コンテナ上でのみサポートされていましたが、最新では Windows 環境でも利用可能になっています。Free版は検証や学習環境、プロトタイピングに最適で、実際の製品版導入前に機能を体験できます。
オンプレミス版予定:23aiオンプレ版リリース見通しと提供計画
Oracle は 23ai のオンプレミス版も計画しており、当初のスケジュールでは 2024 年後半に提供開始が予定されていました。ただし、リリース時点ではクラウド限定となっているため、オンプレミス環境への展開を検討している組織は正式提供開始を待つ必要があります。オンプレミス版リリース後は、自社データセンターへの導入により、既存環境で23aiを活用できるようになります。オンプレミス版の提供が開始されたら、既存の Oracle Database から 23ai へのアップグレードや、仮想マシン/クラウドとのハイブリッド利用が可能になります。
Free版導入手順:Oracle Database Freeの入手方法と基本インストール
23ai Free版はコンテナイメージとして提供されており、OCI Container Registry からダウンロードできます。Oracle の公式サイトから Free 版のイメージを取得し、Docker または Podman 環境で起動します。Qiita によれば、以下のコマンドで23ai Free イメージを取得・起動できます:docker run -p 1521:1521 container-registry.oracle.com/database/free:23.4.0.0。起動後、デフォルトの管理ユーザーでログインし、パスワード設定や必要なユーザー作成を行えば、すぐにベクトル検索などの新機能を試せる環境が構築できます。
Free版 vs Enterprise:機能制限やライセンス上の違いを比較
Free版は開発・検証用途向けのエディションであり、ライセンスコストが不要な反面、機能やリソースに制限があります。前述したリソース制限のほか、Data Guard や RAC、Oracle Database Vault などのエンタープライズオプションが使えません。一方、Enterprise 版ではこれらすべての機能が利用可能で、サポートや更新サービスも含まれます。Free版は商用環境での使用はライセンス違反となるため、実運用では有償版への移行が必要です。Enterprise 版には標準的なライセンス体系(コアライセンス、クラウドライセンスなど)が適用されます。
Oracle Database 23cから23aiへの名称変更の背景と狙い:AI強化新時代を示すリリース名の意義
Oracle は今回のリリースでデータベース名称を「23c」から「23ai」に変更し、AI 技術の採用を前面に打ち出しました。ミッションクリティカルなデータベースに生成AIの力を取り込むことが今回の焦点であるため、Oracle EVP であるJuan Loaiza氏は「AI を強調するためにリリース名を変更した」と述べています。この名称変更には、AIを駆使した次世代アプリケーションやデータ分析を推進するというメッセージが込められており、開発者や顧客にAI時代への移行を強く印象付ける狙いがあります。
AIに注力する戦略:Oracleが23cから23aiへ名称変更した背景
Oracle がリリース名に「AI」を冠したのは、人工知能技術をデータベースに組み込む姿勢を明確に示す戦略です。これにより、開発者やビジネスユーザーに対して、このリリースではAI関連機能が強化されていることを直感的に伝えています。Loaiza 氏は「AI関連の画期的技術を含むため、リリース名を『Oracle Database 23ai』に変更した」と説明しており、AI統合へのコミットメントをアピールしています。
公式声明:Juan Loaiza氏による名称変更の説明と狙い
Oracle ミッションクリティカルDB担当 EVP の Juan Loaiza 氏は声明で「AI技術を強調するために23aiへ名称を変更した」と述べています。彼のコメントによれば、今回のリリースはAI中心のアプリ開発パラダイムとミッションクリティカル機能を組み合わせる重要な節目であり、名前を変えることでその革新性を際立たせています。この公式声明は、Oracle が今後も AI とデータベースの深い連携を推進していくビジョンを示しています。
リリース名の意義:AI強化を強調する名前変更の効果
「23ai」という名称変更はマーケティング面でも大きな効果があります。リリース名に直接「AI」を含めることで、顧客企業にはAI時代へのアプローチを意識させ、注目度を高めます。これにより、AIベクトル検索やTrue Cacheといった新機能の訴求力が増し、顧客がこれらの機能に関心を持ちやすくなります。また、一般認知度の高いAIというキーワードを用いることで、教育や導入促進の観点からもメリットがあります。実際に Oracle Japan のプレスでは「生成AIを活用した自然言語での質問が可能に」といった表現で、AI機能の革新性を強調しています。
歴史的経緯:過去リリース名との関連と今回の命名変更
Oracle Database のリリースはこれまで、数字と「c」で表現されてきました(例:18c, 19c, 21c)。23ai の発表は、この命名体系を初めて大きく変更したケースです。これまでのナンバリングはリリース年を示していましたが、「23ai」は単に年ではなく機能重視の命名となりました。これにより、Oracle は「23年のリリース」から「AI強化リリース」というメッセージを発信しました。同様に、以前から「Oracle Autonomous Database on Exadata」では「24c」「24ai」といった名称も検討されており、今後も AI を軸にした命名が続く可能性が考えられます。
今後への展望:名称変更が示すOracleのAI時代戦略
名称変更で「AI」を打ち出した Oracle は、今後の DB 技術進化にも AI を軸に据えることを示唆しています。例えば、次期リリースではさらに強力なLLM統合や、AI支援開発ツールの追加などが期待されます。また、今回の取り組みで得た知見はクラウドプラットフォーム全体にも波及し、データベース以外のサービスでも生成AI活用が進むでしょう。このように、23ai のリリースは Oracle が AI テクノロジーの採用を加速させる大きな転換点となり、今後のロードマップを示す重要な指標となります。