BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)とは? 定義から事例まで徹底解説
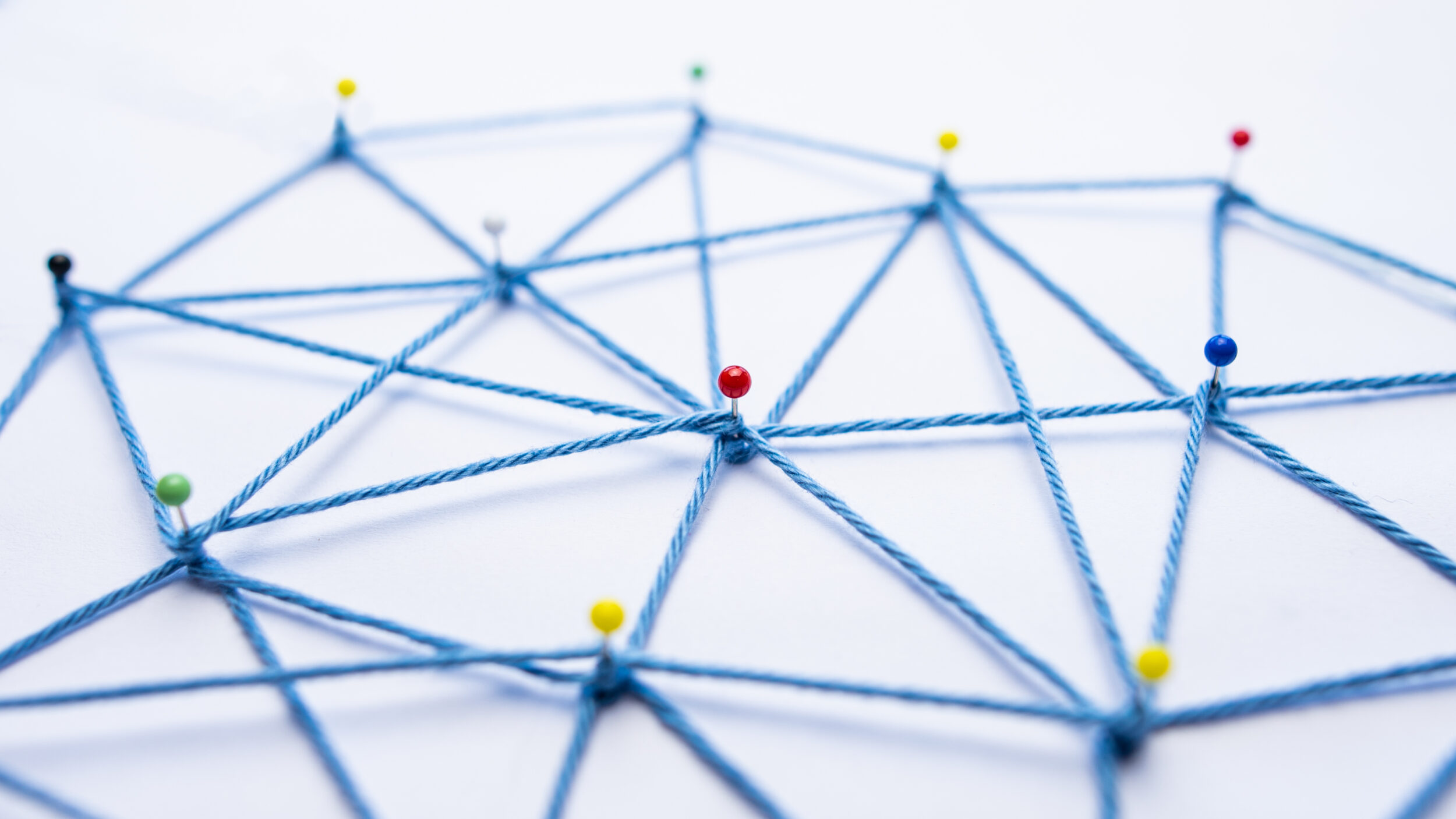
目次
- 1 BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)とは? 定義から事例まで徹底解説
- 2 BPRとは何か?ビジネスプロセス・リエンジニアリングの定義と基本特徴
- 3 BPRと業務改善の違いとは?抜本的改革と継続的改善の違いを解説
- 4 BPRのメリット・デメリットとは?ビジネスプロセス再構築の利点と潜在的な課題
- 5 BPRの進め方・ステップとは?業務プロセス再構築を成功させる具体的手順
- 6 BPRの成功事例・導入事例:成果を上げた企業の具体例から学ぶ
- 7 BPRとDX(デジタルトランスフォーメーション)の違いとは?業務プロセス再構築とデジタル変革の関係
- 8 BPRに役立つフレームワーク:業務プロセスの可視化・分析・改善に使える手法やツール
- 9 BPRの注意点・失敗しない進め方:プロジェクト成功のためのポイント
- 10 BPRとERP・BPOとの関係や違い:業務改革と基幹システム導入・アウトソーシングの位置づけ
BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)とは? 定義から事例まで徹底解説
現代のビジネス環境では市場変化や競争激化に伴い、企業は業務効率化や生産性向上への取り組みを強化する必要に迫られています。こうした中で注目される手法がBPR(Business Process Reengineering、ビジネスプロセス・リエンジニアリング)です。BPRとは既存の業務や組織構造を根本から見直し、業務プロセスを抜本的に再設計することで劇的な業績向上を目指すアプローチです。本記事では、BPRの定義と基本特徴、業務改善やDXとの違い、メリット・デメリット、進め方のステップ、成功事例、BPRに役立つフレームワーク、プロジェクトを成功させるポイント、さらにERP・BPOとの関係まで、一般ビジネスパーソン向けにわかりやすく解説します。
BPRとは何か?ビジネスプロセス・リエンジニアリングの定義と基本特徴
BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)とは、「業務プロセス再構築」や「業務改革」とも呼ばれ、企業内の既存の業務フローや組織・制度を抜本的に見直し、ゼロベースで再設計する手法を指します。米国で1990年にマイケル・ハマー氏(元MIT教授)によって提唱され、1993年に出版された『リエンジニアリング革命(Reengineering the Corporation)』によって世界的に知られるようになりました。同書ではBPRを次のように定義しています。
「コスト、品質、サービス、スピードといった重大で現代的なパフォーマンス指標を劇的に改善するために、ビジネスプロセスを根本的に考え直し、抜本的にそれをデザインし直すこと」
この定義から見ても、BPRのキーワードは「根本的な見直し」「抜本的な再設計」「劇的な改善」「プロセス志向」の4つに集約されます。つまり、BPRでは現在の組織や業務の前提にとらわれず、企業活動そのものをプロセス(一連の業務の流れ)として捉え直し、そのプロセスをゼロから再デザインします。目的は従来比で桁違いのパフォーマンス向上を実現することであり、部分的な微調整ではなく全社的・抜本的な改革である点が特徴です。
例えば、従来10人月かかっていた業務をBPRによって根本から見直すことで半分以下の期間で完了できるようにしたり、100ステップの手続きをシステム導入を含め再構築して数ステップに削減する、といった劇的改善がBPRの目指すところです。BPRの推進には全社横断のプロジェクトチームが組成されることもあり、既存の部門の枠を超えて業務フローやシステムを見直すことで大きな成果を得ようとします。
BPRと業務改善の違いとは?抜本的改革と継続的改善の違いを解説
BPRと日常的な業務改善(継続的改善)は、いずれも業務効率化や品質向上を目的とする取り組みですが、そのアプローチやスケールは本質的に異なります。主な違いをポイントごとに整理すると以下の通りです。
改革のスコープ(範囲)の違い
BPRは既存業務プロセス全体を白紙に戻してゼロベースで再構築する大規模改革です。組織横断的に業務フロー全体を見直し、必要なら組織構造自体も変える抜本的な変革になります。一方、業務改善は現在の業務フローの一部や特定業務に焦点を当て、その部分を部分的に効率化・最適化する小規模・中規模の改善活動です。つまりBPRは全社的・包括的、業務改善は局所的・部分最適という違いがあります。
目指す改善幅・インパクトの違い
BPRが狙うのは劇的な改善であり、「従来比○倍」という飛躍的向上を目指します。例えば業績を数割向上させる程度ではBPRの出番ではなく、現状の延長線上でも達成可能な場合は通常の業務改善で十分だとされています。BPRは「現状では到底なし得ない飛躍」を狙うアプローチであり、10%の改善で足りる状況ではむしろBPRは不要ともいえます。一方、業務改善は既存の延長線上での効率化(5~10%の改善など)を積み重ねるイメージで、目標水準も漸進的です。
進め方・リーダーシップの違い
業務改善は現場レベルでの自主的な工夫やボトムアップで進むケースも多く、現場社員自らが小さな改善を積み重ねることができます。しかし、BPRは基本的にトップダウン主導で進められます。全社規模の抜本改革となるため、社長や事業責任者クラスが旗振り役となり、明確なビジョンと方針を示して組織を牽引する必要があります。現場から自然発生的に生まれるものではなく、トップのリーダーシップの下、プロジェクトとして推進されるのがBPRです。
プロジェクトの期間・継続性の違い
BPRは目標が達成されるか、あるいは達成が困難と判明した時点で一旦終了する取り組みです。目的達成のために集中的にリソースを投下し、結果が出たらプロジェクトは完了します。永続的にダラダラ続けるものではありません。一方、業務改善は終わりのない継続的な活動として位置づけられます。日常業務の一部として常に少しずつ改善を積み重ねていく活動であり、期限を区切らずに続けられる点でBPRとは異なります。
以上のように、BPRと日常的な業務改善は「抜本的改革」と「継続的改善」ほどに考え方が異なります。例えば、「ミスを10%減らす」「作業を10分短縮する」程度であれば現場の改善努力で十分可能ですが、「処理時間を1/10に短縮する」「コストを半減させる」といった桁違いの目標を掲げる場合、既存の延長では難しくBPRのような思い切ったアプローチが必要になるという違いです。
例として, 1980年代のフォード社では当初、経理部門の人員を20%削減する改善を目標に掲げました。しかし通常の業務改善では目標達成が難しいと判断し、BPR手法で購買から支払いに至るプロセス全体を再設計しました。その結果、請求書を用いない新プロセスを導入し、経理担当者数を75%削減するという劇的な成果を上げています。このように、BPRは常識を覆すレベルの大改革を可能にしますが、逆に言えばそこまでの大改革が不要な場合にまで多用すべき手法ではないと言えるでしょう。
BPRのメリット・デメリットとは?ビジネスプロセス再構築の利点と潜在的な課題
大規模な業務改革であるBPRには、多大な労力がかかる一方で成功すれば非常に大きなメリットを企業にもたらします。ここではBPRの主なメリットとデメリットを解説します。
BPRのメリット(利点)
業務全体の「見える化」と最適化
BPRを推進する過程ではまず全社の業務フローを洗い出して可視化する必要があります。これにより、これまで埋もれていた無駄な作業や非効率な手順を発見しやすくなります。その上でプロセスを再構築し直すことで、組織全体の業務を最適化し、生産性向上やムダの排除(コスト削減)につなげることができます。言い換えれば、BPRを通じて業務プロセスの全貌を把握しボトルネックを除去することで、業務効率や生産性を飛躍的に向上させられるのです。
意思決定スピードの向上
業務フロー全体を見直し効率化が進むと、必要な情報が統合されプロセスの処理時間も短縮されます。その結果、経営層への報告・承認の時間が減り、経営判断のスピードアップが期待できます。組織内の情報伝達やワークフローがスムーズになることで、ビジネス環境の変化に対する迅速な意思決定が可能になります。
社内コミュニケーション活性化
BPRでは部署横断のプロジェクトが組まれ、改革に向けて部門間の壁を越えた議論・協働が行われます。その過程で従業員同士のコミュニケーションが活発化し、組織全体の一体感が醸成される効果もあります。部署を超えて同じ目標達成に取り組むことで、セクショナリズムの打破や情報共有の促進といった副次的メリットも得られるでしょう。
顧客満足度・従業員満足度の向上
BPRによって業務プロセスを抜本的に改善すると、サービス提供の迅速化や品質向上が図れます。その結果、顧客への提供価値が高まり顧客満足度の向上につながります。同時に、従業員にとっても無駄な業務や非効率なルールが廃止されることで負担軽減や働きやすさの向上が期待でき、従業員満足度の向上にも寄与します。BPRは顧客と従業員の双方にプラスの効果をもたらし、ひいては企業競争力の強化につながります。
コスト削減
プロセス改革により重複業務の排除や処理時間短縮が実現すれば、人件費や在庫費用、システム維持費など様々なコストの削減につながります。例えば前述のフォード社のように、不要な業務を廃止することで人員を別業務に振り向けたり削減したりできれば大幅なコストカットが可能です。BPRは一時的に投資が必要でも、長期的にはコスト効率の高い組織への変革をもたらします。
BPRのデメリット(潜在的な課題)
多大な労力・コストがかかる
BPRを実行するには全社横断の大規模プロジェクトが必要となり、現状業務の調査分析から新プロセス設計、システム改修、従業員教育に至るまで非常に多くの手間と時間がかかります。また、プロジェクトチームの人件費やコンサルタント費用、新システム導入費など初期コストも莫大です。したがって、BPRは成功すればリターンが大きい反面、取り組みには相応の投資と労力を要する点を覚悟しなければなりません。
従業員の抵抗・不満が生じる可能性
業務フローや組織体制を抜本的に変えるBPRでは、現場の従業員に大きな変化が及びます。慣れ親しんだやり方を否定されることで心理的抵抗が起きたり、自分の業務が不要になる不安から反発が生じることもあります。実際、1990年代にBPRが流行した際には、大規模リストラ(人員削減)とセットで語られることも多く、一部では「従業員に冷酷な改革」という悪いイメージも持たれました。こうした抵抗を放置するとプロジェクトが停滞・失敗する恐れがあるため、BPR推進にあたっては目的や必要性を全社で共有し、従業員の理解と協力を得ることが重要です。
効果が出るまで時間がかかる
BPRは抜本改革ゆえに中長期的視野で取り組む必要があります。新プロセスを定着させ成果が現れるまでには時間を要し、短期で劇的な数字改善が見えにくい場合があります。そのため経営陣の忍耐強いコミットメントと継続的なモニタリングが不可欠です。短期で成果が出ないからと途中で投げ出してしまうと、投資が無駄になるリスクもあります。
専門知識や経験が要求される
全社的な業務改革を成功させるには、高度なプロジェクトマネジメント能力や業務分析のスキル、新しいIT技術の知見などが必要です。社内にBPRの経験者やプロセス改革のノウハウを持つ人材がいない場合、外部コンサルタントの支援を仰ぐなどしないとプロジェクトを軌道に乗せるのは難しいでしょう。十分な知見なく見よう見まねで進めると、的外れな改革になったり途中で頓挫するリスクもあります。
このように、BPRには大きなメリットがある一方で相応のコスト・リスクも伴います。成功のためには周到な計画と組織の理解・協力、そして経営トップの強力なコミットメントが不可欠と言えるでしょう。
BPRの進め方・ステップとは?業務プロセス再構築を成功させる具体的手順
BPRを効果的に進めるには、全体のロードマップを描き計画的に実施することが重要です。ここでは、一般的なBPRプロジェクトの基本ステップを順を追って説明します。
1. 目的・目標の設定と範囲の明確化
まずはなぜBPRを行うのか、その目的や達成すべき目標を明確に定めます。また、改革の対象とする業務範囲(どの部門・プロセスを対象にするか)を決め、プロジェクトのスコープを定義します。経営戦略上の課題やKPIを踏まえて、トップマネジメントが方向性を示しつつ、各階層の意見もヒアリングして目標を設定すると良いでしょう。
2. 現状把握と課題の分析(As-Is分析)
次に、現在の業務プロセスの実態を詳細に把握し、問題点を洗い出します。業務フローを図解(プロセスマッピング)したり、関係者へのヒアリングや現場観察を行って、どこに非効率やムダ、ボトルネックがあるかを調査します。必要に応じてABC分析(重要度分析)やベンチマーキング、BSC(バランススコアカード)などの手法を用いて定量・定性的に課題を可視化します。現在抱える課題を正確に把握することが、後工程の改革方針策定の土台となります。
3. 改革方針の策定と新業務プロセスの設計(To-Be設計)
現状分析で浮き彫りになった課題に基づき、業務改革の戦略・方針を立案します。どの課題を優先的に解決すべきか、どういった手段で解決するかを検討し、新たなビジネスプロセス(あるべき業務フロー)を設計します。例えば、「○○の業務を廃止する」「△△の工程を自動化する」「権限委譲して承認ステップを減らす」など具体策を盛り込みます。効果が高いものから優先実施できるようにし、新プロセスの姿が描けたら関係者間で共有して認識合わせを行います。
4. 施策の実行(改革の実施)
設計した新プロセスに沿って、実際に業務の再構築やシステム導入・組織変更などの施策を実行に移します。このフェーズでは、現場への周知徹底と教育を行いながら、計画通りに業務変更を進めます。BPRは効果が出るまで時間がかかる場合も多いため、中長期の視点で段階的に進めることがポイントです。途中経過でチェックポイントを設定し、進捗や中間成果を確認しつつ必要なら軌道修正しながら進めます。
5. モニタリングと評価・定着化
改革後の業務が計画通り機能しているかをモニタリング(監視)し、効果測定と評価を行います。BPR実施前に設定した目標が達成できたかKPIを計測し、改善点が残っていないか確認します。問題が見つかれば原因を分析して追加改善を行い、新しい業務プロセスが現場に定着するようフォローします。この評価フェーズを経て、BPRプロジェクトは完了となります。必要に応じて、新たな課題に対しては継続的な業務改善活動(PDCAサイクル)に引き継いでいくと良いでしょう。
以上がBPRの基本的な進め方です。各企業やプロジェクトの性質によって詳細手順は異なりますが、「目的設定 → 現状分析 → 新プロセス設計 → 実行 → 評価」という大枠は共通しています。このステップを踏むことで、闇雲な改革ではなく計画的で効果的なBPRを遂行できるでしょう。
BPRの成功事例・導入事例:成果を上げた企業の具体例から学ぶ
実際にBPRを取り入れて成果を上げた企業の事例を紹介します。それぞれのケースで、BPRによって得られた効果やポイントを見てみましょう。
日鉄ケミカル&マテリアルの事例
大手素材メーカーの日鉄ケミカル&マテリアル株式会社では、グループ各社でバラバラだった基幹業務システムを統合・再構築する大規模BPRプロジェクトに取り組みました。共通システムを導入して業務プロセスの標準化を図り、分散管理されていたデータを一元化した結果、受注・在庫・生産状況をリアルタイムで把握できるようになりました。これにより、生産計画の迅速化や在庫の適正化(在庫削減)、リードタイム短縮など大きな効果が現れています。グループ全体でデータやプロセスを統一したことで内部統制も強化され、品質管理のレベルも向上しました。この事例は、システム再構築を通じた業務標準化によりBPRを成功させたケースと言えます。
日刊スポーツ新聞社の事例
国内初のスポーツ新聞「日刊スポーツ」を発行する株式会社日刊スポーツ新聞社では、老朽化した自社のCMS(コンテンツ管理システム)を全面刷新する形でBPRに取り組みました。特徴的なのは、短いサイクルで開発とリリースを繰り返すアジャイル開発手法を採用した点です。これにより、自社の細かな要望にも柔軟に対応できるシステムを構築し、コンテンツ配信スピードの大幅アップに成功しています。さらに、記事更新作業にワークフローシステムを導入し業務プロセスにおける役割分担を明確化したことで、担当者それぞれが自分の役割を理解しやすくなり、メディア運営におけるコア業務の流れ全体への理解も深まりました。この結果、組織横断での協力体制が強化されただけでなく、属人化してブラックボックス化していた作業の解消にもつながっています。日刊スポーツの事例は、ITシステムの刷新と業務フローの再設計によってサービス提供速度と内部統制の両面で成果を上げた好例です。
これらの事例から学べるポイントは、BPR成功の鍵はそれぞれの企業の課題に合わせた適切な手法選択と確実な実行にあるということです。日鉄ケミカル&マテリアルのように業務標準化とデータ統合による効率化を図ったり、日刊スポーツのように最新技術(CMSやアジャイル)を活用してスピードと柔軟性を高めるなど、自社の状況に応じた改革を行うことで大きな成果が得られるのです。
BPRとDX(デジタルトランスフォーメーション)の違いとは?業務プロセス再構築とデジタル変革の関係
近年よく聞くDX(デジタルトランスフォーメーション)とBPRは、一見似たように企業改革を指す用語ですが、その内容には明確な違いがあります。簡単に言えば、BPRは手段を問わない業務プロセス改革であり、DXはデジタル技術を手段とするビジネス変革です。
BPRは前述の通り、組織の業務プロセスを抜本的に再設計し直す取り組みで、アナログであろうとデジタルであろうと考えうる全ての方法が選択肢になります。極端に言えば、人員増強や組織再編、アウトソーシングなど非ITの手段も含めて、目的達成のためならあらゆる改革策を講じるのがBPRです。
一方、DXはデジタル技術の活用によって企業の業務プロセスやビジネスモデル、組織文化そのものを変革し、競争優位の確立を目指す取り組みです。AI・IoT・クラウドなど先端ITを駆使して新たな価値創出やビジネスモデル転換を図る点に特徴があります。DXは「デジタルの力で主に組織やビジネスモデルそのものを変革する」ものであり、BPRが「プロセスに着目した業務再設計」であるのとはアプローチの焦点が異なります。
両者の違いをまとめると、以下のようになります。
手段の違い
BPRは特定の手段に限定せず非デジタルを含むあらゆる方法で業務改革を行います。一方DXはデジタル技術の活用にフォーカスし、ITを駆使して変革を起こします。つまりDXは手段が「デジタル」に限られる点でBPRの一部領域といえます。
概念・目的の違い
BPRはあくまで既存業務プロセスの再構築ですが、DXは新たなビジネスモデルや組織文化の創造を含むより広義の概念です。DXではデジタル技術によって新サービスを生み出したりビジネスの在り方自体を変えることも含まれるため、従来業務の延長に留まらない変革が含意されています。
このように異なるBPRとDXですが、実際の企業変革においては重なり合う部分もあります。例えば、デジタル技術を活用して既存業務プロセスを抜本的に見直すようなケースでは、DXの文脈で行われた施策がBPRの一環ともみなせます。したがって「BPRとDXは完全に別物」と断言するより、DXがBPRに内包され得る関係として捉えるのが適切でしょう。重要なのは、自社の課題に応じてデジタルも含めた最適な手段を選択し、業務改革(BPR)と新たな価値創造(DX)の双方をバランス良く推進することです。
BPRに役立つフレームワーク:業務プロセスの可視化・分析・改善に使える手法やツール
BPRを進める際には、業務の現状を分析したり新プロセスを設計する上で様々なフレームワーク(手法や分析ツール)が活用できます。以下に代表的なものを紹介します。
業務フローの可視化(プロセスマッピング)
現状業務を正確に把握する基本手法として、フローチャートやBPMNなどで業務プロセスを図式化する手法があります。プロセスマッピングにより、処理の流れや関係部署、所要時間などが一目で分かるようになり、ムダや滞り箇所を発見しやすくなります。BPRの第一歩として有効です。
ABC分析(パレート分析)
業務や業務項目を重要度や頻度に応じてランク付けする分析手法です。わずかな重要項目(全体の20%)が成果の80%を生むとされる「パレートの法則」に基づき、業務上クリティカルな要素に経営資源を集中させる判断に役立ちます。BPRの課題抽出フェーズで、どの問題に優先的にメスを入れるべきか決める際に用いることができます。
ベンチマーキング
自社のプロセスを業界のベストプラクティスや競合他社と比較分析する手法です。他社と比べて非効率な部分を定量化して把握できるため、BPRで達成すべき水準(目標設定)の裏付けに使えます。また他社の優れた仕組みを参考に改革アイデアを得ることもできます。
SWOT分析
自社のStrength(強み)・Weakness(弱み)・Opportunity(機会)・Threat(脅威)を整理するフレームワークです。経営環境と社内資源の両面から現状を俯瞰できるため、BPRの背景や重点課題を洗い出すのに有効です。実際、千葉県松戸市が行政BPRに取り組んだ際にはプロジェクトチームでSWOT分析を行い、業務の俯瞰把握や方向性明確化に成果を上げています。BPRに限らず戦略策定でも広く使われるオーソドックスな手法です。
シックス・シグマ
アメリカで生まれた品質管理のための代表的手法で、統計学を駆使して業務プロセスの不良・ばらつきを極限まで減らすプロジェクト手法です。シックス・シグマではDMAIC(定義・測定・分析・改善・管理)のステップでプロセス改善を行い、工程能力をシグマ値で評価します。製造業での品質改善で知られますが、サービス業務の効率化などにも応用可能です。BPRの一環としてプロセスの精度向上に用いることで、顧客満足度の向上に寄与します。
バランススコアカード(BSC)
企業のビジョン・戦略を「財務」「顧客」「業務プロセス」「学習と成長」の4つの視点で具体的な指標に落とし込み管理する手法です。BPRでは主に業務プロセスの視点にフォーカスしますが、BSCを使えば他の視点(財務効果や従業員能力など)も含め改革の成果を評価・管理できます。改革目標の設定や成果測定に体系性を与えるフレームワークとして有用です。
この他にもリエンジニアリングのための各種手法がありますが、重要なのは適材適所で活用することです。例えば現状分析にはプロセスマッピングやSWOT、改善策立案にはベンチマーキングやQC手法、効果測定にはBSC、といった具合にBPRの各段階でツールを使い分けると効果的です。必要に応じて専門家の協力も仰ぎながら、これらフレームワークを活用してBPRを体系立てて進めましょう。
BPRの注意点・失敗しない進め方:プロジェクト成功のためのポイント
BPRは高度なプロジェクトであるだけに、進め方を間違えると失敗するリスクもあります。最後に、BPRを成功させるために押さえておきたいポイントや注意点を解説します。
現状や常識にとらわれずゼロベースで発想する
BPRを成功させるには、これまでのやり方や前提を一度リセットし「そもそも何のためにその業務が必要か」から考え直す姿勢が重要です。小手先の効率化に留まらず不要な業務の廃止や統合も含め大胆に検討しましょう。現場からは「そんなの無理」「前例がない」といった声も出がちですが、従来の延長線上にない改革であることを周知し、固定観念を打破することが肝心です。
現状を徹底的に分析して真の問題点を見極める
誤った課題設定で改革をしても成果は出ません。BPRの着手前に現状業務を見える化してデータに基づき分析し、ボトルネックや根本原因を突き止めることが成功への近道です。思い込みで「ここが悪いだろう」と決めつけず、なぜそれが問題なのか「なぜなぜ分析」をするなどして本質的課題を特定しましょう。原因にアプローチできれば効果的な対策が打てます。
経験・ノウハウのある人材をプロジェクトに参画させる
BPRには業務改革やIT導入の豊富な経験を持つ人材が不可欠です。社内にプロセス改革の専門知識を持つ人がいなければ、外部のコンサルタントや専門家の力を借りることも検討しましょう。特にDXやIT活用が絡む場合は最新技術に精通した人材が必要です。経験者の知見を活用することで、改革の質と成功率を高めることができます。
対象業務の選定は慎重に(優先順位付け)
リソースは無限ではないため、BPRでどの業務を優先的に改革するか見極めることが重要です。一般に効果が大きく実行に移しやすいのは、総務・人事・経理などのバックオフィス業務やコールセンター、定型的なIT運用業務などと言われます。自社の状況を見て、改革のインパクトが大きい領域から着手すると良いでしょう。的確な対象選定はBPR成功の近道です。
経営トップのコミットメントと明確なビジョン
先述の通りBPRはトップダウンで推進されるべきものです。経営層が強力に旗を振り、明確な改革ビジョンと目標を示すことで全社を巻き込むことができます。トップの後押しが弱いと現場も本気になれず改革が中途半端に終わる恐れがあります。経営トップ自らが「この改革は会社の命運を握る重要プロジェクトだ」というメッセージを発信し続けることが成功の前提条件です。
従業員の理解・協力を得る(チェンジマネジメント)
BPRでは従業員の業務内容や働き方も変化します。抵抗感や不安を和らげ、前向きに取り組んでもらうためには丁寧な説明と対話が欠かせません。改革の目的や必要性、従業員にもたらすメリット(負担軽減やスキル向上など)を繰り返し説明し、現場の声にも耳を傾けましょう。巻き込まれ意識ではなく「自分たちのプロジェクト」という当事者意識を持ってもらうことで、BPRの現場定着率が格段に上がります。
以上のポイントに留意しながら進めれば、BPRプロジェクトの失敗リスクは大きく低減できます。要は「トップ主導で現場を巻き込み、的確な課題設定とプロの知見で進める」ことが肝要です。変革には困難も伴いますが、組織全体で理解と協力を得て推進することで、大きな成果へとつなげることができるでしょう。
BPRとERP・BPOとの関係や違い:業務改革と基幹システム導入・アウトソーシングの位置づけ
最後に、BPRとよく関連して語られるERPやBPOとの関係・違いについて整理します。BPRプロジェクトではしばしばこれらの手段を組み合わせるケースがあるため、その位置づけを理解しておきましょう。
ERP(Enterprise Resource Planning)との関係
ERPとは企業の人・モノ・カネといった経営資源を一元管理し有効活用するための考え方、またはそれを実現する統合基幹業務システムのことを指します。ERPシステムを導入すると、従来バラバラだった各部門のデータやシステムを統合でき、情報の一元管理による迅速な意思決定や業務効率化が実現します。例えばERP導入によって重複入力がなくなり業務のムダが解消されるなど、プロセス改革に直結する効果が得られます。
BPRとERPの違いは、BPRが業務プロセスそのものの再設計であるのに対し、ERPは業務を支えるITシステムの導入だという点です。ただし実際には、ERP導入はBPRを促進する手段の一つになり得ます。業務プロセスを統一・標準化するためにERPを導入するケースや、ERP導入に合わせて業務フローをBPR的に見直すケースも多く見られます。要するに、ERPはBPRを実現するための強力な武器であり、両者は補完関係にあると言えます。BPRで定義した新しい業務プロセスを定着させるためにERPを活用したり、逆にERPプロジェクトの一環でBPRを行う、といった形でERPとBPRはセットで語られることが多いのです。
BPO(Business Process Outsourcing)との関係
BPOとは企業内の業務プロセスを外部の専門企業に委託すること、いわゆる業務のアウトソーシングを指します。例えば経理・人事・物流・ITサポートなどの非中核業務を丸ごと外部に任せてしまう形態です。BPOでは委託先に業務の企画や手順まで含めて一任するため、発注企業は自社資源をコア業務に集中できるメリットがあります。また、委託先企業の持つノウハウや最新テクノロジーを活用できるため、自社内で無理に抱えるより高品質・高効率になる利点もあります。
BPRとBPOの関係性について言えば、BPOはBPRを進める上での一つの手段になり得ます。BPRの検討過程で「この業務は自社でやらず専門業者に任せた方がよい」と判断すれば、その業務プロセスを丸ごと外部委託(BPO化)することも改革策の一つです。実際、BPRの一環でバックオフィス業務をアウトソーシングして固定費を削減したりサービスレベルを向上させた例も多く報告されています。一方で、BPOそれ自体は業務プロセスの「所有主体を外に移す」ことであって、「業務そのものの再構築」ではありません。したがって、BPR(自社内での業務改革)とは目的もアプローチも異なります。ただし繰り返しになりますが、BPRを進める中でアウトソーシングの活用(BPO)が改革の手段になることは十分にあり得るため、両者は代替案あるいは補完関係にあると言えます。













