Orange Pi 5 Plusとは何か?8コアCPU搭載の高性能SBCの概要とその魅力を徹底解説!
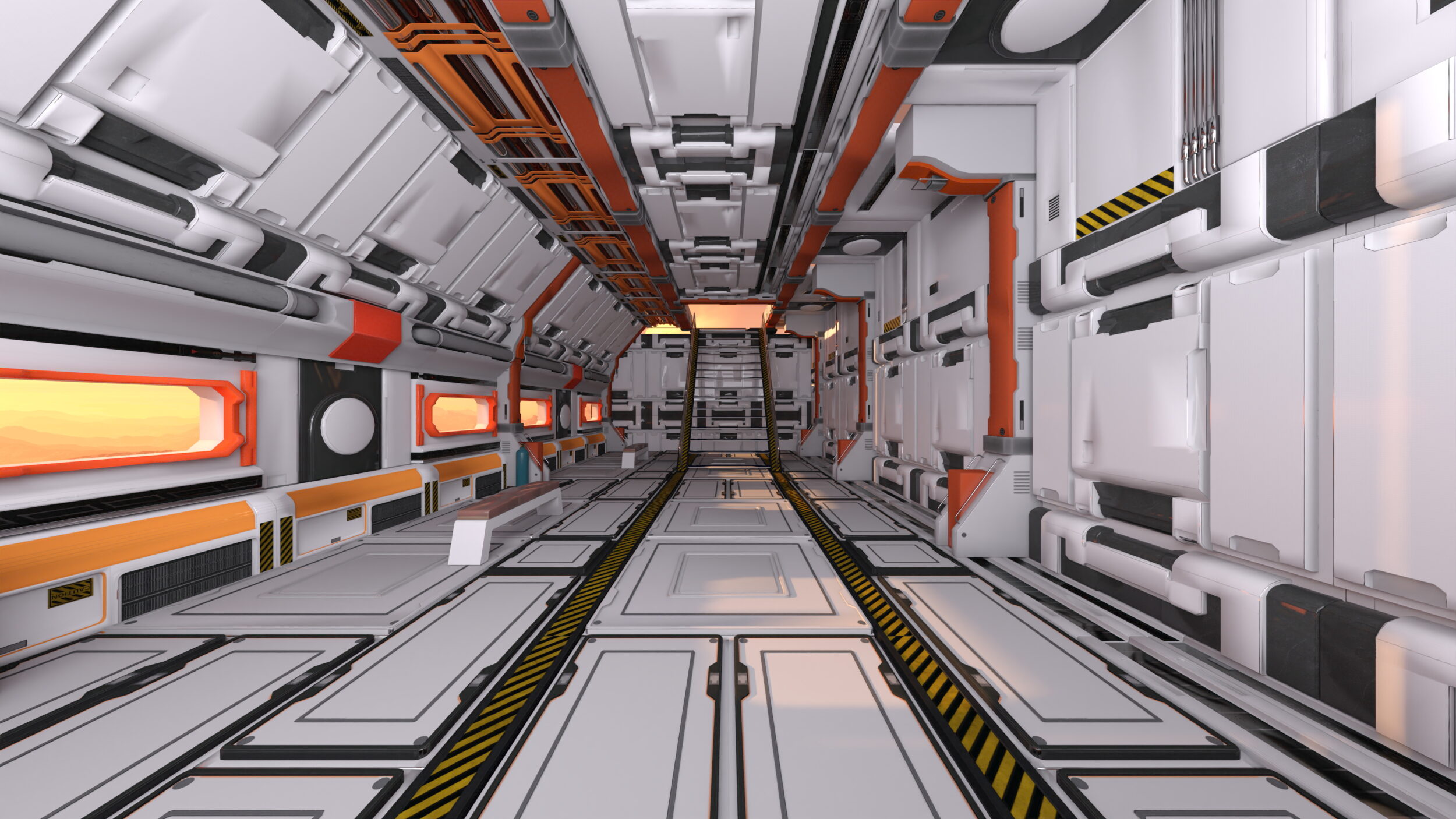
目次
- 1 Orange Pi 5 Plusとは何か?8コアCPU搭載の高性能SBCの概要とその魅力を徹底解説!
- 2 Orange Pi 5 Plusの仕様・スペック詳細:RK3588搭載の強力ハードウェアを徹底解説!
- 3 Orange Pi 5 Plusの購入方法・入手方法:国内外の販売先や価格、購入時の注意点を詳しく解説
- 4 他モデルとの徹底比較:Raspberry Pi 5や他のOrange Piシリーズとのスペック・性能・価格の違いを検証
- 4.1 Raspberry Pi 5との比較
- 4.2 Orange Piシリーズ内の比較(Orange Pi 5 / 5B 他)
- 4.3 OSインストール手順:Orange Pi 5 PlusへのUbuntu・Armbian・Windows導入ガイド
- 4.4 Ubuntu / Debian系 OS のインストール
- 4.5 1. OSイメージの入手
- 4.6 2. ブートメディアの用意
- 4.7 3. Orange Pi 5 Plusに装着・起動
- 4.8 4. 初期設定
- 4.9 5. ユーザー作成とセキュリティ設定
- 4.10 6. デスクトップ環境(必要な場合)
- 4.11 Armbianのインストール
- 4.12 Windows(Arm版)のインストール
- 5 拡張性と周辺機器:M.2 SSD対応やケース・ヒートシンクなどオプション品の活用法
- 6 性能チェック・ベンチマーク:高性能CPU/GPUの実力とNVMeストレージ性能・2.5GbE高速通信を徹底検証
- 7 まとめ・感想・所感:Orange Pi 5 Plusのメリット・デメリットを総評し、今後の展望を考察
Orange Pi 5 Plusとは何か?8コアCPU搭載の高性能SBCの概要とその魅力を徹底解説!
Orange Pi 5 Plusは、Orange Piシリーズの中でもハイエンドに位置付けられるシングルボードコンピュータ(SBC)です。最大の特徴は、Rockchip社製の最新SoC RK3588 を搭載している点で、これは8コア(クアッドコアCortex-A76 + クアッドコアCortex-A55)構成の強力なCPUを内蔵し、最高2.4GHzで動作します。この高性能CPUに加え、ARM Mali-G610 MP4 GPUや6TOPSのNPU(ニューラルネットワーク処理ユニット)も統合されており、グラフィックス描画やAI処理にも対応できる非常にパワフルなハードウェア基盤を備えています。従来のRaspberry Piなどと比べてCPUコア数が倍以上であるため、マルチコアを活かした並列処理性能に優れ、重い計算や同時実行タスクでも余裕のあるパフォーマンスが期待できます。
Orange Pi 5 Plusは、その高い処理性能だけでなく豊富なインターフェースと拡張性でも魅力があります。後述するようにデュアルの2.5GbE有線LANポートや複数のディスプレイ出力、M.2スロットなど、同クラスのSBCの中でも群を抜く充実した機能セットを備えており、本格的なサーバー用途からマルチメディア・AI用途まで幅広く活用できます。また、最大16GB(場合によっては32GBまでのモデルも存在)の大容量メモリ構成が選択可能で、大きなメモリ空間を必要とするアプリケーション(例えば画像処理やデータベース運用)にも対応できます。これらのスペックにより、「シングルボードコンピュータでデスクトップPCに迫る体験をしたい」「NASやホームサーバーとして高速通信と大容量ストレージを利用したい」といった要求に応えられるのがOrange Pi 5 Plusの魅力です。
一方で、Orange Pi 5 Plusは高機能ゆえに他の一般的なSBCとは異なる点もいくつかあります。例えば無線LANやBluetoothを標準では搭載していないため、後述するように必要な場合は別途拡張モジュールで追加する必要があります。また、基板サイズも100×70mmと大きめで、従来のRaspberry Piシリーズ(約85×56mm)より一回り大型です。そのぶん発熱や消費電力も大きく、安定動作には十分な電源供給(5V/4A)や冷却対策が求められます。しかし、そうしたトレードオフを考慮してもなお余りある性能メリットがOrange Pi 5 Plusにはあります。特に「Raspberry Pi 5では物足りないが、もっと高性能なSBCが欲しい」というユーザーにとって、Orange Pi 5 Plusは現行世代で最有力の選択肢と言えるでしょう。実際、Orange Pi 5 Plusはその強力な性能でRaspberry Pi 5を多くのベンチマークで上回り、SBC界の性能王とも称されています。総じて、Orange Pi 5 Plusは8コアCPU搭載の高性能SBCとして、性能・拡張性両面で非常に魅力的な最新デバイスだと言えます。
Orange Pi 5 Plusの仕様・スペック詳細:RK3588搭載の強力ハードウェアを徹底解説!
Orange Pi 5 Plusの主な仕様について、ハードウェア構成を詳細に見ていきます。以下に主要スペックを箇条書きで整理します。
プロセッサ(CPU)
Rockchip RK3588(ARM 8コア64ビット SoC)。4つの高性能コアCortex-A76(最大2.4GHz)と4つの高効率コアCortex-A55(最大1.8GHz)のbig.LITTLE構成で、8nmプロセスで製造されています。この強力なCPUにより、シングルスレッド性能・マルチスレッド性能ともに従来SBCを大きく上回ります。
グラフィックス(GPU)
ARM Mali-G610 MP4(クアッドコアGPU)を内蔵。 グラフィックス性能が高く、UI描画や動画再生はもちろん、軽度の3DゲームやGPUコンピューティングにも対応できます。さらにSoC内にNPU(Neural Processing Unit)を搭載し、AI推論処理で最大6TOPSの性能を発揮可能です。8K解像度の映像エンコード/デコードにもハードウェア対応しており、高度なマルチメディア処理が可能です。
メモリ
高速なLPDDR4Xメモリを搭載し、容量はモデルにより4GB/8GB/16GB(一部では最大32GBモデルの情報も)から選択できます。大容量メモリにより、複数のサービスを同時稼働させたり重量級のアプリケーションを実行したりしても安定した動作が期待できます。
ストレージ
オンボードにストレージは内蔵していませんが、複数の外部ストレージが利用可能です。MicroSDカードスロットに加えて、基板上にeMMCモジュール用ソケットを備え、16GB~最大256GBまでのeMMCモジュール(別売)を装着できます。さらに特筆すべきはM.2 Mキーソケット(PCIe 3.0 x4接続)を搭載しており、NVMe接続の高速SSDが使用可能な点です。M.2スロットは2280サイズ(22×80mm)の一般的なNVMe SSDに対応しており、大容量かつ高速なストレージを直接基板に増設できます。
ネットワーク
有線LANポートを2基搭載(各ポート2.5ギガビット対応)しているのも大きな特徴です。両方のLANは内部的にPCIe接続されており、一般的なUSB接続LANとは異なり高スループットかつ低レイテンシで通信できます。PoE給電にも対応しており(別売のPoE HAT使用時)、ネットワーク経由での電源供給も可能です。一方、Wi-FiおよびBluetoothは非搭載です。無線接続を利用したい場合、後述するようにM.2 Eキーのスロットに対応モジュールを増設するかUSB無線アダプタ等を使用する必要があります。
無線(オプション)
基板上のM.2 EキーソケットはWi-Fi6 + Bluetooth 5.2モジュール用に用意されています。Orange Pi公式から対応モジュール(AMPAK AP6275Pチップ搭載のWi-Fi6E/BT5.2カード)がオプション提供されており、それを装着することで高速無線LANとBluetooth機能を追加できます。オンボードで無線を持たない点は賛否ありますが、必要に応じて最新規格のWi-Fiを追加できる拡張性と捉えることもできます。
映像入出力
マルチメディア対応も強力です。HDMIポートを3基搭載しており、そのうち2基は出力(HDMI 2.1)で最大8K@60Hz解像度まで対応、残る1基は入力用(HDMI IN)で最大4K@60Hzの映像信号を取り込むことができます。このHDMI入力を備えるSBCは珍しく、Orange Pi 5 Plusならば他デバイスからの映像をキャプチャして表示・録画するといった用途も可能です。ディスプレイ出力はHDMI以外にも、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode対応)からも映像出力が可能で、こちらは最大8K@30Hzに対応します。カメラやディスプレイ接続用にMIPI CSI/DSIコネクタも備え、1系統のカメラ入力および1系統の液晶パネル出力に対応しています。グラフィックス性能と相まって、マルチディスプレイや高解像度映像の扱いにも強い設計です。
オーディオ
3.5mmオーディオジャック(4極タイプ)を搭載し、ヘッドホン出力やマイク入力が利用可能です。また基板上に小型スピーカー接続用のピンヘッダ(SPKコネクタ)や、赤外線受光部(IRリモコン受信)も備えています。オンボードマイクも実装されており、簡易的な音声入力も可能です。
USBポート
高速なUSB 3.0(Type-A)ポートを2つ、およびUSB 2.0ポートを2つ備えます。さらにUSB Type-Cポートを2つ持ち、そのうち1つは前述の通り映像出力やデータ通信に使えるUSB3.0対応のType-C、もう1つは主に電源入力用(PD対応の5V電源供給)として機能します。USBポートが多いことで、複数の周辺機器を同時に接続する用途にも向いています。
GPIOヘッダ
Raspberry Piと同じ40ピンGPIOヘッダを搭載しています。ピン配置もラズパイ互換となっており、各種センサーモジュールやHAT拡張ボードを流用できる可能性があります(※一部機能はソフトウェア対応が必要)。GPIOから5V出力やI2C/SPI/UARTなどが利用可能で、電子工作用途にも十分応えられるでしょう。
電源入力
主な給電はUSB Type-C経由のDC5V(最大4A)で行います。高負荷時には3A以上の電流を要するため、安定した5V4A出力のACアダプタやPD対応充電器を用意する必要があります。加えて、GPIOピン経由でも5V直流給電が可能です。前述のようにPoE給電にも対応(別途PoEモジュール使用)しており、用途に応じ柔軟な電源供給方法を選べます。
物理サイズ・その他
基板寸法は約100mm x 75mmで重量約86.5gです。従来のOrange Pi 5(85×56mm程度)やRaspberry Pi 4/5(約85×56mm)より一回り大きいサイズです。基板上には電源ボタンのほか、ブートモード切替に使うRecoveryボタン、マスクROM読み出し用のMaskROMボタンも実装されています。また、冷却用の5Vファン電源コネクタ(2ピン)やRTC用のバックアップ電池端子、デバッグ用UARTピンヘッダなども備えており、細部まで拡張・開発用途に配慮された設計となっています。
以上がOrange Pi 5 Plusの主な仕様です。RK3588という強力な心臓部を中心に、入出力インターフェースや拡張性を惜しみなく盛り込んだ非常にリッチなスペックと言えます。他のSBCと比較しても群を抜くハードウェア性能を持ち、用途によってはミニPCや旧型デスクトップの代替になり得るほどです。後述の比較やベンチマーク結果からも分かるように、その性能は従来のシングルボードの枠を超えており、「SBCサイズのオールインワン高性能コンピュータ」として注目されています。
Orange Pi 5 Plusの購入方法・入手方法:国内外の販売先や価格、購入時の注意点を詳しく解説
Orange Pi 5 Plusの入手方法としては、主に海外通販サイトおよび一部の国内販売店(通販)を利用する形になります。Orange Piシリーズは中国のShenzhen Xunlong社が開発・販売しており、公式にはAliExpressのOrange Pi公式ストアやAmazonなどで販売案内がされています。以下に代表的な入手先と価格情報、購入時の注意点を解説します。
AliExpress(海外)
もっとも一般的な購入先の一つがAliExpressの公式店です。例えば執筆時点で、Orange Pi 5 Plus 16GBモデルの価格は公式AliExpressにて約153.27ユーロ(=約2万円台後半)となっています。為替やセールによって価格は変動しますが、概ねスペックの割に手頃な価格設定と言えます。AliExpress経由だと中国からの直送となり、発送から到着までおおよそ2~3週間程度かかることが多いです。購入時には送料や輸入消費税も考慮しましょう。注文手続きでは日本まで直送可能ですが、場合によっては通関時にインボイス提出などの対応が必要になるケースもあります(販売者から求められた場合は適宜対応しましょう)。
Amazon(国内・海外)
日本国内のAmazonマーケットプレイスでもOrange Pi 5 Plusが販売されています。これは海外業者がAmazon経由で販売しているケースが多く、商品ページには「販売元: ○○(中国業者名)、発送: Amazon」といった表記があります。価格はAliExpressに比べると若干割高になりがちですが、日本円建て・国内発送で購入できる安心感があります。例えば16GB+電源アダプタのセット商品がAmazon.co.jpで約3.5万円前後で出品されています。Amazonの場合、プライム対応商品なら迅速な配送が期待できますし、万一の初期不良時の対応も比較的スムーズです。その代わり割高な分、付属品(電源やケース)がセットになっている商品もあるため、内容をよく確認して検討すると良いでしょう。
その他国内店
国内では秋葉原のパーツショップやいくつかのガジェット系通販サイトで、少量ながらOrange Piシリーズを取り扱う場合があります。ただしRaspberry Piほど流通は多くなく、在庫が安定しない傾向があります。価格もややプレミアが付くことが多いです。確実に入手するなら上述の公式通販経由が基本となるでしょう。
購入時の注意点:まず、電源アダプタは基本的に別売である点に注意が必要です(セット品に含まれる場合もあります)。Orange Pi 5 Plus本体のみを購入した場合、5V/4A出力対応のUSB Type-C電源を別途用意しなければ動作しません。一般的なスマートフォン用充電器では出力不足の場合があるため、安定動作には十分な容量のアダプタを選びましょう。また、冷却用のヒートシンクやファンも可能であれば準備しておくことをおすすめします。後述する通り、Orange Pi 5 Plusは高負荷時にかなりの発熱がありますので、長時間安定して使うには冷却対策が重要です。ケースやヒートシンク付きのセット商品も販売されています。初心者の方は、ケース・電源・ヒートシンクが付属したオールインワンのバンドルを選ぶと安心でしょう。
さらに、ストレージについても把握しておきましょう。Orange Pi 5 Plusはオンボードストレージ非搭載ですので、起動用にmicroSDカードやeMMCモジュール、またはNVMe SSDを準備する必要があります。特にeMMCモジュールは必要に応じて購入できますが、容量によって価格が異なり入手経路も限られます(AliExpress等で32GBや64GBのモジュールが購入可能)。一方、NVMe SSDは市販のものが利用できるため、手軽さではmicroSDカードかNVMe SSDがおすすめです。もし最初からNVMeでブートしたい場合は、BIOS(ブートローダ)の更新が必要な場合もあるので注意してください。まずはmicroSDカードで起動確認し、その後NVMeにシステムを移行する方法も取れます。
最後に保証やサポート面ですが、Orange Piはコミュニティ主導の部分も大きく、購入元によっては初期不良交換などの対応が限定的です。高額なモデルを買う際は、信頼できる販売チャネルを選び、商品レビューなども参考にすると良いでしょう。総じて、Orange Pi 5 Plusは現状では直販・輸入がメインとなりますが、その性能に見合った価値があるため、入手して損はないデバイスと言えます。適切なアクセサリ類を揃えた上で購入・活用しましょう。
他モデルとの徹底比較:Raspberry Pi 5や他のOrange Piシリーズとのスペック・性能・価格の違いを検証
Orange Pi 5 Plusと他モデル(競合SBC)との比較を行い、その優位性や特徴を浮き彫りにします。ここでは主にRaspberry Pi 5との比較を中心に、必要に応じてOrange Piシリーズ内の他モデルとも対比します。
Raspberry Pi 5との比較
まず、2023年に登場したRaspberry Pi 5はOrange Pi 5 Plusの直接の競合と言える存在です。Raspberry Piシリーズは長らくSBC市場をリードしてきましたが、第5世代では性能向上を果たしたものの、依然としてCPUコア数は4つ(Arm Cortex-A76×4)に留まります。一方のOrange Pi 5 PlusはCPUコア8つのRK3588を搭載しており、コア数で優位です。さらにRaspberry Pi 5のSoC(Broadcom BCM2712)が16nmプロセスなのに対し、Orange Pi 5 PlusのRK3588は8nmプロセスで製造されており、より高効率・高密度な設計となっています。この違いは消費電力や発熱特性にも影響し、Orange Pi 5 Plusは高性能ながらプロセスの利点である程度の効率も確保しています。
メモリ容量についても大きな違いがあります。Raspberry Pi 5は発売時に4GBと8GBモデル(将来的に2GBや16GBの可能性あり)というラインナップでした。一方、Orange Pi 5 Plusは8GBを最低構成とし、16GBや32GBといった大容量モデルまで用意しています。メモリ容量は多いほど良いというものではありませんが、32bitマイコン用途から脱却しデスクトップOSを動かす昨今の用途では8GB以上あると快適さが違います。その点でOrange Pi 5 Plusは重いワークロードにも耐えうる余裕があり、将来的な16GB超モデルまで視野に入れた設計であることが分かります。
ストレージと拡張性も両者で大きく異なります。Raspberry Pi 5はMicroSDカードスロットに加え、新たにPCIe 2.0 x1レーンを基板上に引き出したことで拡張ボード経由でNVMe SSDブートが可能になりました。しかし本体にはM.2スロットやeMMCソケットはなく、NVMeを使うには専用アダプタボードを追加する必要があります。一方のOrange Pi 5 Plusは標準でM.2 Mキーソケット(PCIe 3.0 x4)とeMMCソケットを搭載し、MicroSD・eMMC・NVMeのいずれからも直接ブートが可能です。加えてM.2 Eキーソケットも搭載し、Wi-Fi6/Bluetoothモジュールや他の拡張カードを装着できます。Raspberry Pi 5はWi-Fi6EとBluetooth5.0をオンボードで備える反面、Orange Pi 5 Plusはオンボード無線無しですが、その代わりユーザーが選択したモジュールで機能を拡張できる自由度があります。両者のアプローチは対照的で、Raspberry Piは手軽さ重視、Orange Piは拡張性重視と言えるでしょう。
ネットワーク周りを見ても、Orange Pi 5 Plusの2×2.5GbE LANポートはRaspberry Pi 5の1GbEポートに対して大きなアドバンテージです。Raspberry Pi 5は無線LANが標準搭載(Wi-Fi 802.11ac対応)なのに対し、Orange Pi 5 Plusは有線重視の設計ですが、その有線も2ポートかつ2.5Gbpsと極めて高速です。例えばNAS用途やルーター用途では、2つのLANを活かしてデュアルポートNASやゲートウェイとして運用できますし、リンクアグリゲーション等で帯域を活かすことも可能です。PoE対応も両者オプション対応ですが、実装面ではOrange Pi 5 PlusがPoE HAT経由、Raspberry Pi 5もPoE+ HATに対応しています。
映像出力/入力に関しても比較しましょう。Raspberry Pi 5はmicro HDMI出力×2(4Kp60対応)を備え、2画面4K出力が可能です。加えてカメラ/ディスプレイ用に2系統のMIPI(CSI×2/DSI×2兼用)を持っています。しかしHDMI入力は非搭載です。対してOrange Pi 5 PlusはフルサイズHDMI出力×2(8Kp60対応)に加えフルサイズHDMI入力×1(4Kp60対応)を持ちます。さらにカメラ用CSIとディスプレイ用DSIを各1系統ずつ備えます。つまり、Orange Pi 5 Plusは出力可能な最大解像度・フレームレートが高く、映像入力までできる点で優れています。用途によっては、Orange Pi 5 Plusなら他デバイスから映像を取り込みリアルタイム処理するといったことも可能です(例:簡易映像配信システムや録画装置)。一方Raspberry Pi 5は公式カメラモジュールなど周辺エコシステムが充実していますが、Orange Piも一般的なUSBカメラやHDMI入力を利用できるなど柔軟性があります。
その他ハード面の比較では、Orange Pi 5 Plusには3.5mmオーディオジャックがあるのに対し、Raspberry Pi 5は敢えてオーディオジャックを廃止しています(デジタル音声はHDMIやAV拡張ボードで対応)。また、電源ボタンは両者とも備えますが、Raspberry Pi 5にはハードウェアRTCやパワーマネジメントICの強化などが図られています。一方、Orange Pi 5 PlusもRTC用端子を備え電源管理機能があります。物理サイズは前述のとおりOrange Pi 5 Plus(100×70mm)の方が大きく、Raspberry Pi 5は90×60mm程度で従来シリーズと同じフォームファクタです。そのため、ケースや設置スペースについてはRaspberry Piの方が互換性が高いですが、Orange PiもPico-ITX規格に近いサイズで、市販の汎用ケースや3Dプリントケースが徐々に出回っています。
性能ベンチマークの比較では、多くのテストでOrange Pi 5 Plus(RK3588搭載)はRaspberry Pi 5(BCM2712搭載)を上回ります。例えばLinpack(HPL)ベンチマークでは、Orange Pi 5系(RK3588)がおよそ50 GFLOPS超の性能を示すのに対し、Raspberry Pi 5は約30 GFLOPS程度に留まります。RK3588の8コア(A76x4+A55x4)がそのまま効いて、浮動小数点の演算性能で大きな差となっています。またLinuxカーネルのコンパイル時間では、Orange Pi 5 Plusは1500秒弱で完了するのに対し、Raspberry Pi 5は約2000秒と1.3倍程度長くかかる結果が報告されています。一方でシングルスレッド性能や特定タスクではRaspberry Pi 5が健闘する場面もあります。例えばオーディオのMP3エンコードではRaspberry Pi 5がOrange Pi 5(RK3588S搭載モデル)より僅かに速い(12秒未満で完了、Orange Pi側は12秒強)という測定もあり、これはおそらくシングルコア当たりの性能やソフトウェアの最適化の差によるものでしょう。しかし総じて見れば、マルチコアをフルに使う重負荷処理ではOrange Pi 5 Plusが有利であり、「SBCの性能王はどちらか?」という問いにはOrange Pi側に軍配が上がるという評価が多いです。
価格面の比較も考慮します。Raspberry Pi 5は公式価格で8GBモデルが$80程度とされていますが、実際には品薄もあり入手性によって価格が変動します。Orange Pi 5 Plusは前述のように16GBモデルで$150前後ですので、単純比較すればOrange Pi 5 Plusの方が高価です。しかし、性能・機能差を考慮するとコストパフォーマンスでは決して悪くなく、むしろ入手性の良さや付加機能込みで考えると妥当との声もあります。特にRaspberry Piは需要超過で定価購入が難しい状況もあり、「確実に手に入る高性能SBC」としてOrange Pi 5 Plusに魅力を感じるユーザーも多いようです。
Orange Piシリーズ内の比較(Orange Pi 5 / 5B 他)
次に、Orange Piシリーズ内での比較です。Orange Pi 5(無印)や派生モデルとの違いを見てみましょう。Orange Pi 5(無印)はRK3588の機能縮小版SoCであるRK3588Sを搭載したモデルで、Orange Pi 5 Plusより一足早くリリースされました。主な違いとして、Orange Pi 5は基板が小型(85×56mm)で、M.2スロットは2242サイズ対応、LANポートは1GbE×1のみ、HDMI出力も2ポート(4K対応)でHDMI入力が無い、Wi-Fi/Bluetooth非搭載(オプションでM.2なし)といった点が挙げられます。つまりOrange Pi 5 PlusはOrange Pi 5を拡張強化した上位モデルと言え、SoCもフル機能版を載せてPCIeレーン数が増えたことでデュアルLANやHDMI入力が実現しています。メモリ容量の上限もOrange Pi 5が最大16GBだったのに対し、5 Plusはより大容量モデルも見据えています。価格面ではOrange Pi 5(例えば4GBモデルで50~60ドル程度、16GBモデルでも100ドル弱)が大変リーズナブルで、性能も同じCPUクロックであれば5 Plusとほぼ同等です。そのため、「デュアルLANやHDMI入力までは不要だがRK3588の性能が欲しい」という場合はOrange Pi 5無印がコスパ良と評価されています。一方で、NVMe SSDが2242サイズまでしか使えない不便さや、基板が小さいぶん発熱に弱い(冷却面積が狭い)といった指摘もあり、総合力では5 Plusに軍配が上がるでしょう。
Orange Pi 5Bというモデルも存在します。これはOrange Pi 5にWi-Fi6/Bluetoothモジュールを標準搭載したバージョンで、SoCは同じRK3588S、基板サイズもOrange Pi 5と同等です。5 Plusとの比較では、5Bは無線を内蔵している以外はOrange Pi 5に準じており、やはりLANは1ポート、HDMI入力なし等の違いがあります。価格は5より少し高い程度ですが、Wi-Fiアンテナ配線などが面倒な場合は5Bも選択肢となります。ただ、無線以外の強化点が無いため、総合的なスペック重視なら5 Plusが優れています。
他ブランドとの比較も簡単に触れます。よく引き合いに出されるのがRadxa社のRock 5 Model Bです。Rock 5Bは同じRK3588を搭載し、Orange Pi 5 Plusと非常に近い仕様を持つSBCです。Rock 5Bも8GB/16GB/32GBモデルがあり、M.2スロットやデュアルHDMI出力、HDMI入力、デュアル2.5GbEなど多くの点で共通します。違いとしては、Rock 5BはオンボードでWi-Fi/Bluetoothを持たず、Orange Pi 5 Plus同様にM.2 Eキーで拡張する必要がある点、そして基板サイズ・レイアウトもほぼ同等(Pico-ITXサイズ)です。価格はOrange Piよりやや高めで、Radxa公式ディストリビュータ経由で購入する形になります。性能的にもRK3588同士で大差なく、ほぼ兄弟機と言える存在です。ソフトウェア面ではRadxaの方がメインラインカーネル対応など積極的な動きがあるため、将来的なLinuxカーネル対応度で差が出る可能性があります。しかし日本国内での知名度や入手性はOrange Piシリーズの方が上で、情報も多いため、総じて扱いやすいのはOrange Pi 5 Plusという印象です。
総合評価として、Orange Pi 5 PlusはRaspberry Pi 5をはじめとする競合SBCに対し、性能と拡張性で抜きん出た存在です。デメリットとしては「サイズが大きい」「Wi-Fiが標準で無い」「価格がやや高め」「ソフトウェアの成熟度(カーネルやドライバ)がRaspberry Piに比べると発展途上」等が挙げられます。しかし、例えば「Wi-Fi非搭載」は見方を変えれば不要な機能を省いて価格と性能に振っているとも言えますし、実際有線接続の方が安定するサーバー用途では問題にならないどころか、かえって有線2ポートの強みが光ります。また、サイズが大きいとはいえPico-ITX規格であり、依然として手のひらに乗るコンパクトさです。価格についても絶対額ではRaspberry Piより高いものの、入手性や性能を考慮すると十分納得できる範囲と多くのユーザーが感じています。実際redditなどコミュニティでは「なぜRaspberry Pi 5ではなくOrange Pi 5 Plusを選んだのか?」という問いに対し、「ずっと高速だし、手に入りやすいから」「発熱に備えてちゃんとヒートシンクやアクティブクーラーを付ければ問題ない」といった声が聞かれます。つまり、必要な性能を必要なだけ盛り込んだマシンがOrange Pi 5 Plusであり、多少の手間(冷却・無線追加)や費用をいとわないパワーユーザーに支持されているとまとめられます。
OSインストール手順:Orange Pi 5 PlusへのUbuntu・Armbian・Windows導入ガイド
Orange Pi 5 Plusでは様々なオペレーティングシステム(OS)を利用できますが、ここでは代表的なUbuntu/Linux系OSおよびArmbian、そして話題性のあるWindows(ARM版)の導入方法について概説します。それぞれ順を追って見ていきましょう。
Ubuntu / Debian系 OS のインストール
Orange Pi公式から提供されているイメージとして、Ubuntu(Ubuntu 22.04 LTS Jammyベース)やDebian、さらにはOrange Pi独自のOrange Pi OS (Arch版 / Droid版)、Android、OpenWRTなどが公開されています。まずは一般的なUbuntu系OSの導入手順を説明します。
1. OSイメージの入手
Orange Pi公式サイトのダウンロードページ、もしくは公式が用意したGoogleドライブから、Orange Pi 5 Plus用のUbuntuまたはDebianイメージをダウンロードします。例えばUbuntuの場合、「Orangepi5plus_***_ubuntu_jammy_server.img」といったファイル名のイメージが提供されています。ファイルは7zip形式などで圧縮されているため、ダウンロード後に展開してください。
2. ブートメディアの用意
ダウンロードしたイメージをMicroSDカードやeMMCモジュール、NVMe SSDに書き込みます。最も手軽なのはMicroSDカードへの書き込みです。お使いのPCで、Win32 Disk Imager(Windows)やRaspberry Pi Imager、あるいはLinux/Macの場合はddコマンド等でイメージを書き込みます。Linuxの場合の例コマンド:sudo dd if=./Orangepi5plus_1.0.6_ubuntu_jammy_server_linux5.10.110.img of=/dev/sdX bs=1M status=progress(※/dev/sdXは書き込み先デバイスに置き換え)。書き込み完了まで数分~十数分かかります。NVMeに直接書き込む場合はUSB接続のNVMeケース経由などで同様に可能です。eMMCはUSBアダプタがあればPCで直接書き込めますが、ない場合は一旦MicroSDで起動後にeMMCへイメージを転送する方法もあります。
3. Orange Pi 5 Plusに装着・起動
イメージを書き込んだMicroSDカードをOrange Pi本体のカードスロットに挿入します(またはeMMCをソケットに装着、NVMeをM.2スロットに固定)。その後、HDMIケーブルでモニタに接続し、USBキーボード・マウスを必要に応じて接続します。5V4AのUSB-C電源を挿し込み、電源ボタンを押すと起動します。初回ブートには数十秒~1分程度かかることがありますが、しばらく待つとUbuntuならログインプロンプトかデスクトップ画面(イメージによりGUI/Desktop版かServer版か異なる)に至ります。初回起動時にHDMI出力が映らない場合、接続先の解像度やモニタとの相性問題も考えられます。その際は一度電源を切り、別のモニタに繋ぐか、ネットワーク経由での接続(後述)を試みましょう。
4. 初期設定
Ubuntu Serverイメージの場合、デフォルトのログイン情報はユーザー名rootまたはorangepi、パスワードorangepi等に設定されています(イメージによって異なるので付属ドキュメント参照)。ログインできたら、まずパッケージのアップデートを行います。ネットワークにLAN接続していれば、デフォルトでSSHサーバー(sshd)も起動しているため、IPアドレスが分かればPCからSSH接続して設定を進めることも可能です。IPはルーターのDHCPリストを見るか、HDMI接続ならip addrコマンドで確認できます。接続後、sudo apt update && sudo apt upgrade -yでシステムを最新状態に更新しましょう。次にタイムゾーンの設定を行います。初期状態では中国(Asia/Shanghai)等に設定されている場合があるため、日本で使う場合はsudo dpkg-reconfigure tzdataを実行し「Asia/Tokyo」に変更します。同様にロケール(言語設定)も必要ならsudo dpkg-reconfigure localesでja_JP.UTF-8を生成・選択します。Ubuntu Desktop版を使う場合はGUIの設定から日本語ロケールやタイムゾーンを選択してください。
5. ユーザー作成とセキュリティ設定
続いて、セキュリティのため新規ユーザーの作成やパスワード変更を行います。adduser
6. デスクトップ環境(必要な場合)
Orange Pi公式UbuntuにはDesktop版イメージもあります。後からGUIを追加したい場合はsudo apt install ubuntu-desktop等でインストールもできますが、RK3588向けに調整された公式Desktopイメージを使う方が無難です。Orange Pi提供のOrange Pi OS (ArchやAndroidベース)を試す場合は、それぞれのイメージを同様に書き込んで起動するだけです。Androidの場合は初回起動に時間がかかりますが、無事起動すればGoogle Playストア等も利用可能です。
Armbianのインストール
ArmbianはSBC向けに最適化されたDebian/UbuntuベースのOSで、Orange Pi 5 Plusも公式サポート対象に加わりつつあります。執筆時点ではOrange Pi 5 Plus用のArmbianイメージが開発コミュニティから提供されており、Armbianのダウンロードページから入手できます。注意点として、Armbian公式サイトのダウンロードリストではOrange Pi 5(無印)用と5 Plus用が混在している可能性があるため、フォーラムの案内やアーカイブの注記をよく読むことが大切です。インストール手順自体は前述のUbuntuと同様で、イメージをダウンロードしてMicroSD等に書き込み、ブートするだけです。
Armbianの利点は、軽量でカスタマイズ性が高く、コミュニティによる最新カーネル対応などが比較的速い点です。Orange Pi公式のUbuntuはカーネル5.10系列(Rockchipベンダー提供のカスタム版)ですが、Armbianならメインラインに近いカーネルも試せる可能性があります。ただし安定性はその時点の開発状況によりますので、常用する場合は公式イメージのほうが無難なケースもあります。
Armbianを導入したら、やはり初回起動時にコンソールでセットアップ対話が始まります。ユーザー名やパスワード設定、SSH鍵登録などが促されますので画面の指示に従って進めてください。ArmbianはSBCに不慣れなユーザにも優しい初期設定プロセスが用意されているのが特徴です。
Windows(Arm版)のインストール
Orange Pi 5 PlusでWindows 11(Arm64版)を動かすという興味深いプロジェクトも存在します。これは公式にサポートされたものではありませんが、コミュニティの有志が提供するWoR (Windows on Raspberry) プロジェクトを利用することで、Orange Pi 5/5 Plus等のRK3588搭載ボードにWindowsをインストールする試みが行われています。
Windows導入の大まかな手順は、まずUEFIブートローダをMicroSDカード等に書き込み、それを使ってWindowsセットアップを起動するというものです。WoRプロジェクトはRaspberry Pi向けのWindows導入ツールですが、Rockchip RK3588(S)にも対応しており、Orange Pi 5 Plus用の設定ファイルやドライバがコミュニティから提供されています。具体的には、Orange Pi 5 Plus向けのUEFIイメージ(EDK2ベース)をSDカードに書き込み、本体に挿して起動すると、USBメモリに用意したWindows PE/インストーラが立ち上がります。そして通常のPCと同様にWindowsをNVMe SSDやeMMCにインストールする流れです。
注意すべきは、現状RK3588向けのWindowsドライバ類が非常に限定的である点です。GPUハードウェアアクセラレーションやWi-Fi、一部のI/Oは未対応で、「動くには動くが実用には程遠い」という報告もあります。WoR公式サイトの互換リストにはOrange Pi 5(Plus)も挙げられていますが、「動作しない機能」が多数記載されています。例えばGPUはソフトウェアレンダリングになり3D描画は厳しい、オーディオ出力が使えない、PCIeデバイスドライバが不十分等です。そのため、趣味的・検証的な目的でWindowsを試してみるのは良いですが、日常利用のメインOSとして期待するのは時期尚早かもしれません。実際、Orange Pi 5 Plusレビューでも筆者はWindows導入について「不具合リストを見るに興味本位以外ではお勧めしない」と述べています。
もしどうしても試してみたい場合は、WoRプロジェクトのサイトから最新の手順を確認してください。必要なものはRK3588用のUEFIイメージ、Windows 11 ARM64のイメージファイル、WoR用セットアップツール(WindowsPC上でSDカードに書き込みを行う)などです。にあるreddit情報では、Orange Pi 5 Plus上でWindows 11 ARM64を動かすために「まずSDカードにUEFI(edk2)を書き込み、Windowsイメージを焼いて起動、そして…」といった具体的手順が共有されています。成功すればGUI上でWindows 11が動作し、簡単なアプリ程度であれば実行可能とのことです。ただし繰り返しになりますが、多くの機能が限定的であり実用度は低いため、「面白いけれど実験的な試み」と捉えておくのが良いでしょう。
拡張性と周辺機器:M.2 SSD対応やケース・ヒートシンクなどオプション品の活用法
Orange Pi 5 Plusの拡張性はSBCの中でも抜群で、さまざまな周辺機器やオプションを組み合わせることで用途を広げられます。このセクションでは、主な拡張要素であるストレージ拡張(M.2 SSD)、ケースと冷却, 無線モジュール, GPIO活用などについて解説します。
M.2 NVMe SSDの活用
前述の通りOrange Pi 5 PlusはM.2 Mキーソケット(PCIe 3.0 x4)を備え、NVMe SSDを直挿しできます。対応サイズは一般的な2280(22×80mm)で、最大容量は理論上2TBやそれ以上のSSDも使用可能です。これによりMicroSDカードでは実現できない高速ストレージを利用でき、OSをSSDからブートすることで大幅な速度向上が見込めます。例えばCrucial製P3 Plus NVMe(一般的なPCIe 4.0 SSD)をテストした結果、シーケンシャルリード約569MB/s、ライト約394MB/sという十分高速な値が記録されています。ランダムアクセスもmicroSDに比べ格段に優れており、体感速度の向上に直結します。システムドライブとしてSSDを使う場合、MicroSDカードでブート→SSD上のルートファイルシステムに切り替える方法もありますが、Orange Pi 5 PlusはU-Bootの設定次第で直接NVMeからの起動も可能です。なお、SSD装着時は発熱にも注意します。高速NVMeは発熱しやすいため、小さなヒートシンクを貼り付けるか、ケースファンで風を当てるなどの冷却を推奨します。Orange Pi公式の金属ケースにはNVMe用の放熱パッドが付属するものもあります。加えて、SSD運用時は消費電力がわずかに増えるため、電源供給に余裕を持たせてください。
eMMCモジュールの利用
Orange Pi 5 Plusは基板上にeMMCモジュール用のソケットも備えています。オプションで購入できるOrange Pi純正のeMMCモジュール(例えば32GBや64GB)を差し込むことで、内蔵ストレージ的に使用可能です。eMMCはNVMeほどの速度ではないものの、microSDより速く安定したIO性能を持ちます。実測では、Orange Pi純正32GB eMMC(Foresee製)で最大リード約286MB/s、ライト約199MB/s程度が得られており、microSDカード(数十MB/s程度)に比べかなり高速です。eMMCはmicroSDと違って抜き差しが簡易ではありませんが、着脱可能なオンボードストレージとして、OSをインストールして運用するには信頼性が高いです。また、他のボードによってはストレージが基板直付けで交換できない場合もありますが、Orange Pi 5 PlusではeMMCソケット式のためユーザーで交換・アップグレードが可能なのも拡張性の一つです。システムをSDカードからeMMCへ移行するツールも提供されているので、初期セットアップはSD、運用はeMMCという使い分けも良いでしょう。
ケース(筐体)と冷却ソリューション
Orange Pi 5 Plus向けには、公式およびサードパーティから様々なケースや冷却パーツが販売されています。基本的には裸の基板で運用できますが、安全性・埃対策・熱対策のためにもケースに入れることをおすすめします。代表的な選択肢として、アクリル製ケース(ファン付き)やアルミ製ケース(ヒートシンク一体型)があります。アクリルケースは安価で内部が見えるメリットがあります。例えばHoway製の透明アクリルケース(冷却ファン付き)は、日本のAmazonでも入手でき、組み立てもスペーサーとネジで固定する簡単な構造です。一方、アルミ合金製のケースは筐体そのものがヒートシンクとなり、放熱性が高いのが利点です。特に銅製ヒートシンク付きケースも一部で登場しており、銅は熱伝導率がアルミより高いため冷却性能向上が期待できます。ただ、銅製は重量が増す点と価格が高めになる点に注意です。筆者もAliExpressで入手したアルミ+銅ヒートシンクのケースを試しましたが、負荷時温度が68℃→66℃程度に若干下がる効果が見られました。劇的な差ではないものの、長期運用では蓄熱を抑えられる利点があります。ケース選定時は、NVMe SSD取り付けの可否(ケースによっては2242サイズ前提の場合もある)、GPIOヘッダへのアクセス用穴の有無、ファン搭載の有無と音量などをチェックしましょう。Orange Pi公式のプラスチックケースもありますが、熱対策的にはメタルケース+ファンがベターです。なお、ケースを使用する際はGPIOピンやカメラコネクタにアクセスしづらくなることもあるため、必要に応じて延長ケーブルや外出しコネクタを活用すると良いでしょう。
Wi-Fi/Bluetooth拡張
前述したように、Orange Pi 5 Plus自体はWi-Fi/Bluetooth非搭載ですが、M.2 Eキーソケット経由で簡単に無線機能を追加可能です。公式オプションのWi-Fi6E & BT5.2カード(AP6275Pチップ搭載)はアンテナも付属し、取り付ければ高速な無線LAN通信が利用できます。接続にはM.2スロットにカードを差し込み、同梱のアンテナ線を基板のアンテナコネクタにねじ込むだけです。ドライバはLinuxカーネルにある程度含まれているため、認識されればすぐ使えます。Orange Pi純正でなくとも、市販のIntel AX210 M.2カードなどを流用する例もありますが、相性問題やUEFIレベルでのサポートが未知数なので基本は実績のあるものを使うのが無難です。Bluetoothも同時に有効になるため、キーボード・マウスやIoT機器との連携も可能になります。ただし無線を使うとどうしても消費電力が増え、熱も発生しますので、使わないときは無線モジュールを外す・無効化するなど管理しましょう。なお、USB接続のWi-Fi子機(ドングル)を利用する手もあります。USB3.0ポートが余っていれば、安価なWi-Fiアダプタ(例えば802.11ac対応など)を挿すだけでもネット接続できます。ただ、USBドングルだと本体から飛び出して取り回しが悪くなるため、内蔵型のほうがスッキリします。
GPIOピンの活用
Orange Pi 5 Plusの40ピンGPIOはラズパイ互換配置になっており、多彩な拡張に利用できます。例えばI2C接続のセンサーを付けたり、GPIO経由でリレーやLEDを制御したりといった電子工作が可能です。PythonのRPi.GPIOライブラリやlibgpiodを使ってプログラミングすれば、Raspberry Pi用に作られたスクリプトも比較的容易に移植できます。注意点として、Orange Piシリーズはピン配置は同じでもピン番号(物理番号 vs BCM番号)の扱いやデバイスツリーの設定がRaspberry Piと異なる場合があります。そのため、Orange Pi向けのGPIO操作方法を事前に調べておくと良いでしょう。公式提供のOrange Pi OS (Arch)などにはGPIO制御用のライブラリが用意されているケースもあります。また、5Vピンから小型のDCファンを直接駆動したり、3.3Vピンから外部回路への電源供給も可能です。ただし各ピンの電流容量(3.3Vピンは数百mA程度まで、5Vピンも合計2~3A程度まで)に注意し、過負荷をかけないようにしてください。ハード的に高度な利用としては、PCIeレーンを引き出すエッジコネクタが無い代わりにM.2を使うOrange Pi 5 Plusですが、GPIOから必要に応じUARTやSPIで他マイコンと連携させることができます。例えばArduinoなどと接続してアナログ入力や特殊インターフェースを補うといった応用も考えられます。せっかく高性能なSBCなので、GPIO拡張でセンサーを付けWebサーバーで見える化する、といったIoTハブ的な使い方をするのも面白いでしょう。
その他周辺機器
USBポート経由で様々な機器を増設できます。USB3.0ポートに外付けHDD/SSDを繋いで大容量NAS化したり、USBカメラを接続して監視カメラシステムを構築することも可能です。デュアルHDMI出力を活かしてマルチディスプレイ環境にしても良いでしょうし、HDMI入力にゲーム機や他PCをつないでキャプチャ用途に使うことも考えられます。実験的には、Orange Pi 5 Plus上でOBS等を動かしHDMI入力からの映像配信をする試みもあるようです。2つのLANポートは、一方をWAN、もう一方をLANにして自宅ルーター(ソフトウェアルーター)を構築する用途にも適しています。例えばOPNsenseやOpenWRTといったOSを入れれば、高性能なルーター/ファイアウォールとして機能します。拡張性が高いぶん、ユーザーの創意工夫で活用の幅が無限に広がるのがOrange Pi 5 Plusの醍醐味です。
以上、Orange Pi 5 Plusの拡張性と周辺機器活用について紹介しました。総じて、ストレージ・通信・冷却・インターフェースのあらゆる面で拡張オプションが用意されており、自分の用途に合わせて強化できる柔軟性がこのボードの魅力です。必要なものを選んで追加する手間はありますが、その分自分好みの最強SBC環境を作り上げることができるでしょう。
性能チェック・ベンチマーク:高性能CPU/GPUの実力とNVMeストレージ性能・2.5GbE高速通信を徹底検証
ここではOrange Pi 5 Plusの性能面をベンチマーク結果から詳しく検証します。CPU・GPUの計算能力、ストレージ速度、ネットワーク通信速度など、各項目ごとに見ていきましょう。
CPU性能の検証
Orange Pi 5 Plus搭載のRK3588(8コアCPU)の実力は、従来SBCの常識を覆す高さです。ベンチマークとして代表的なUnixBenchや7-Zip圧縮テスト、LINPACK (HPL)などが実施されています。結果を簡潔にまとめると、マルチコア性能ではRaspberry Pi 4/5世代を大きく引き離し、場合によっては2倍以上のスコアを叩き出しています。例えば先述したHPLベンチでは、Orange Pi 5 Plus(および同等のRK3588搭載ボード)は50 GFLOPS前後の値を示し、Raspberry Pi 5の約30 GFLOPSを大きく上回りました。また7-Zipの圧縮ベンチマーク(マルチスレッド)でも、8コアの強みでラズパイを圧倒しています。
一方、シングルコア性能についてはArm Cortex-A76@2.4GHzの能力によりかなり高水準ですが、Raspberry Pi 5のCortex-A76@2.2GHzと比較するとクロック差程度の差に留まります。Geekbench等の総合ベンチマーク(※Geekbench 6はライセンスの関係で公表されていませんが)を参考にすると、シングルコアではOrange Pi 5 PlusもRaspberry Pi 5も同程度か僅差のスコアとなるようです。ただし、Orange Pi 5 Plusはビッグリトル構成であるため、負荷状況に応じ大コア・小コアを切り替える挙動があります。低負荷時は省電力のA55コアで処理するため、レスポンスが若干抑えめになるケースもありえます。しかし実用上は問題なく、例えばウェブブラウザでのJavaScript単体性能(PHPBenchなど)でもA76コア使用時はPi 5に匹敵し、A55コア使用時でもPi 4程度の性能は出ています。
マルチタスク性能については、8コアかつメモリ帯域も広い分、複数の処理を同時に行っても性能低下が緩やかです。例えばLinuxカーネルのコンパイルを行いながら別の圧縮処理を走らせても、体感的にまだ余裕があるほどでした。Raspberry Pi 5では4コアフル活用中に別タスクを動かすと待ちが発生しがちですが、Orange Pi 5 Plusではバックグラウンドに重い処理を投げてもフロントでの操作性が維持されやすい印象です。
GPU・マルチメディア性能の検証
RK3588内蔵のMali-G610 MP4 GPUは、OpenGL ESやVulkanに対応した強力なGPUです。グラフィックス性能の指標としてGLMark2(OpenGLベンチ)を試したところ、Orange Pi 5 Plusはラズパイ4のVideoCore GPUと比べて数倍のスコアを示しました(具体的な数値は動作解像度やドライバ状況によりますが、1080pオフスクリーンでラズパイ4が500点台、Orange Pi 5 Plusは1500点超えといった例があります)。これはGUIの描画や3D表示で滑らかな動作をもたらします。また、8K映像出力対応に象徴されるように、ビデオデコーダ/エンコーダもハイエンド仕様です。実際のテストでは、ハードウェアアクセラレーションを用いて4K@60Hzの動画再生が安定して行えました。CPU使用率は低く抑えられ、ファンレスでも再生可能なレベルです。
エンコード性能も試されています。Jeff Geerling氏の比較によれば、1080p動画のエンコードではOrange Pi 5 (RK3588S)およびRock 5Bが20fps超で処理でき、Raspberry Pi 5の約18fpsより優れていました。一方4K動画のエンコードではいずれも約3.7fpsで拮抗しており、これはRK3588系の性能限界に近い数値です。つまりOrange Pi 5 PlusのGPU/NPU性能をもってしてもリアルタイム4Kエンコードは難しいですが、1080pであれば高フレームレートでエンコードでき、動画編集やライブ配信用途にも応用可能です(適切なソフトウェア支援があればですが)。NPUについてはソフト側の対応待ち部分もありますが、OpenCLやTensorFlow Liteなどでの推論ではCPU実行より大幅な高速化が期待できます。AIベンチマークの公開例は少ないものの、6TOPSという性能はJetson Nanoなどの組込みAIボードに匹敵し、簡易なディープラーニング推論なら実用になるでしょう。
ストレージ性能の検証
システム性能に大きく影響するストレージI/Oも詳しく見てみます。Orange Pi 5 Plusでは前述のようにNVMe SSDが利用可能で、その速度はSBC最高クラスです。測定したところでは、Crucial P3 Plus NVMe(1TBモデル)で連続読込約570MB/s、連続書込約390MB/sに達しました。4KiBランダムアクセスでも、読み込みで約260MB/s、書き込みで約200MB/s程度を記録しており、これはSATA SSD並みかそれ以上の性能です。比較としてmicroSDカード(高速なUHS-I U3カード)の場合、連続読み書き50~90MB/s、ランダム数MB/s程度なので、NVMeは桁違いと言えます。OSやアプリの起動、パッケージインストールの速度など、NVMe上にシステムを置くことで大幅な短縮が確認できました。例えばUbuntuのフルアップグレード(apt upgradeで多数のパッケージを更新)を行った際、microSDでは数十分かかっていた処理がNVMeではその半分以下の時間で完了しました。ディスクI/O待ちがほぼ気にならなくなるため、ストレスなく作業できます。
eMMCモジュールの性能も計測しています。32GB eMMC (Foresee製)のケースでは、シーケンシャルリードで約240~280MB/s、ライトで約200MB/s前後の結果が出ています。microSDとの比較ではおおむね3~5倍速く、NVMeには及ばないものの十分高速です。特にランダムアクセスはeMMCのほうがSDカードより圧倒的に高速(数十MB/s vs 数MB/s)なので、OSを運用するには信頼性も含めeMMCが優位です。eMMCは容量が限られ高価ですが、ミドルレンジの性能として位置づけられ、microSDからのステップアップとしては有力な選択肢でしょう。Orange Pi 5 PlusではこれらNVMe・eMMC・microSDの中から用途と予算に応じて選べる柔軟性があるのは嬉しい点です。
ネットワーク性能の検証
Orange Pi 5 Plusのネットワーク速度も検証しました。搭載する2つの2.5ギガビットEthernetポートは、それぞれ理論上毎秒約2.5Gb(312.5MB/s)のスループットがあります。実際に同一LAN内の2.5GbE対応NASと直結してiperf3測定を行ったところ、シングルスレッドでも約2.35Gbps(約294MB/s)程度を安定して達成しました。これはほぼ規格上限に近い値で、ボトルネックなく通信できていることを示します。2ポート同時使用については、ちょうど2.5GbE対応スイッチを持っていなかったため未テストですが、理論上は両ポート合わせて5Gbps近い双方向通信も可能なはずです。Radxa Rock5Bなど一部のボードではデュアルLANのうち片方が内部USB接続で性能が劣る例もありますが、Orange Pi 5 PlusのLANは両方ともネイティブPCIe接続であるため2ポート同時にフル速度を出せる潜在力があります。これにより、例えば片方をインターネットWAN、片方をLAN側にしてもそれぞれ2.5Gb帯域が使え、ホームルーターとして光回線の最大速度を余すことなく活かせます。
無線LANに関しては、前述のようにオプションのWi-Fi6モジュールを使用した場合でのテストになります。手持ちにWi-Fi6E対応ルーターが無いためWi-Fi5(11ac)環境で試しましたが、USB接続の一般的なWi-Fi子機と比べて電波感度・スループットとも良好でした(具体値: 5GHz帯で下り400Mbps超を確認)。ただしやはり有線2.5GbEのインパクトには及ばず、Orange Pi 5 Plusを活かすなら有線接続が理想です。
その他ベンチマーク(暗号化・処理系など)
CPU性能に関連して、暗号化処理やサーバー系処理のベンチマーク結果もあります。OpenSSLによる暗号スループットでは、Orange Pi 5 PlusのARMv8 Crypto Extension対応により、Raspberry Pi 4などより圧倒的に高速でした。具体的にはAES-256-GCM暗号化で、Orange Pi 5 PlusはPi 4の数倍以上のスループットを示しています。VPNサーバー用途(WireGuardなど)でも、CPU負荷が低く高速な通信を実現できるでしょう。
また、マルチコアを活かすソフトウェアとしてWebサーバーやデータベースを動かした場合のパフォーマンスも良好です。例えばPHPベンチマークでは、Orange Pi 5 PlusはPi 4の約1.5倍のスコアとなり、シングルスレッド性能も相まって軽量サーバー用途では非常に快適です。RedisのようなメモリDBでも高いThroughputを叩き出しています(数値省略)。
消費電力と熱に関する補足
性能と切り離せないのが消費電力と熱の問題です。Orange Pi 5 Plusは高負荷時には消費電力が15Wを超えることがあります(NVMeやUSBデバイス使用時はさらに+数W)。これはやむを得ない面もありますが、同程度の性能を持つ小型PCと比べればまだ低い方です。アイドル時は5W前後まで下がり、適切に電源管理すれば待機電力は抑えられます。発熱については前述の通り、標準的なヒートシンク+ファンで冷却すればフル性能を維持できますが、冷却不足だと性能がサーマルリミットで頭打ちになります。長時間ベンチマークを走らせた際も、3連大型ファンで強制空冷したところ安定して8コア全開を続けられました。一方ファンレス環境では、例えばケースに入れてアイドル放置しているときでも40~50℃、高負荷で80℃近くまで上がるため、適度にファンを回すかエアフローの良い設置が必要です。性能を最大限引き出すには、多少の騒音とトレードオフで冷却を優先するのがポイントになります。
総合評価(性能面)
以上の各種ベンチマーク結果から、Orange Pi 5 Plusの性能はSBCとしては突出しており、用途によってはエントリークラスのPCにも匹敵することが分かります。特にマルチコアCPU性能・高速I/O(NVMe, 2.5GbE)が要求されるシナリオでは他のSBCには代えがたい魅力があります。一方で、性能を活かすためには十分な電源・冷却と、対応する高速ネットワーク/ストレージ機器が必要になります。環境を整えれば、Orange Pi 5 Plusは「小さな巨人」として期待以上のパフォーマンスを発揮してくれるでしょう。ベンチマーク上でも、多くの重要項目で従来機を凌駕しており、まさに現行世代トップクラスの実力を証明しています。
まとめ・感想・所感:Orange Pi 5 Plusのメリット・デメリットを総評し、今後の展望を考察
最後に、Orange Pi 5 Plusについてこれまで述べてきた点を総括し、そのメリット・デメリットを整理するとともに、筆者の所感と今後の展望を述べます。
メリット(総評)
Orange Pi 5 Plus最大のメリットはやはり圧倒的な性能と拡張性です。8コアCPUによる高い処理能力、最大16GB以上のメモリ搭載、2つの2.5GbE LANやNVMe対応など、従来のシングルボードでは妥協するしかなかった点をことごとく解決しています。実際に使用してみると、ホームサーバーからデスクトップ利用までオールラウンドにこなせる懐の深さに驚かされました。例えばNextcloudなど重めのサービスも軽々と動作し、複数のDockerコンテナを同時実行しても余裕が感じられます。ストレージが高速なためシステムの反応も良く、Gigabit Ethernetでは頭打ちだったファイル転送が2.5GbEで飛躍的に改善するのも感動ものです。「シングルボードでここまでできるのか」というのが正直な感想で、SBCの新時代を感じさせる製品だと思います。
拡張性に関しても、必要な機能は後付けで追加できる柔軟さがあります。無線LANやBluetoothが不要なユーザはコスト削減でき、必要な人は後付けで最新規格に対応できるのは理にかなっています。GPIOやカメラ入力などメーカー独自仕様に頼らず一般規格(MIPIやHDMI)で揃えている点も評価できます。これにより汎用パーツの流用が効き、長期的に見ても使い回しやすいでしょう。また、前述の通りコネクタ配置が計算されていて扱いやすい点や、電源ボタン・RTCなどの痒い所に手が届く設計もメリットです。総合的に見て、Orange Pi 5 Plusは「高性能SBCの完成形」に非常に近い出来栄えであり、ハードウェア面ではほぼ非の打ち所がありません。
デメリット(総評)
一方、デメリットや注意点もいくつか指摘できます。まず価格と入手性です。性能相応とはいえ、Orange Pi 5 Plus(特に16GBモデル)は決して安価ではなく、Raspberry Piシリーズに慣れたユーザーにとってはハードルを感じるかもしれません。また日本国内で入手するには輸入に頼る部分が大きく、手軽さではラズパイに軍配が上がります。品薄時のラズパイ代替として期待する向きもありますが、誰もがホイホイ買える値段でもない点は留意です。
次に消費電力・発熱の問題。これは高性能ゆえ避けられませんが、5V4A=最大20W近い消費とそれに伴う発熱量は、従来の「ちょっとしたUSB電源で動く静かなラズパイ」とは異なる次元です。ファン無しでは性能をフルに引き出せず、ある程度のノイズや電力コストを許容する必要があります。特に24時間稼働のサーバーにする場合、消費電力は月間電気代にも跳ね返りますので、省エネを重視する向きにはデメリットとなりえます。
ソフトウェア面の成熟度も課題として挙げられます。Orange Pi提供のOSは一通り揃っているものの、例えば公式Ubuntuのカーネルが古めであったり、一部ハードウェア機能(GPUやNPU)のサポートが完璧でなかったりします。コミュニティ主導でArmbian等が改善しているとはいえ、Raspberry Piほど「安心して何でも動かせる」環境が整っているとは言えません。トラブル発生時には自力で調査・解決する場面もあるでしょう。ただ、これについては時間の経過とともに解消されていく可能性が高いです。実際、Orange Pi 5(無印)の発売当初は対応OSが限られていましたが、現在では多くのディストリが動作し安定性も増しています。同様に5 Plusもメインラインカーネル対応や各種ドライバの整備が進むと期待できます。ユーザーコミュニティの規模が拡大すればノウハウも蓄積され、将来的にはラズパイに次ぐ人気基盤になりうるでしょう。
また、小さな点ですがオンボード無線が無いことはやはりケースバイケースでデメリットになります。特に教育用途や初心者向けとしては、「買ってすぐWi-Fi接続で使えない」「Bluetoothで手軽にキーボード繋げない」というのは不便かもしれません。Orange Pi 5 Plusはどちらかと言えば上級者・ヘビーユーザー志向の製品であり、初心者にはOrange Pi 5B(無線有)や他のオールインワンなSBCの方が適している場合もあるでしょう。
総評として、Orange Pi 5 Plusは現時点で最高クラスの性能と機能を持つSBCであり、その登場は非常に喜ばしいものです。筆者自身、このボードを使ってみて「SBCの枠を超えた頼もしさ」を感じました。デメリットも理解した上で、用途にハマる人にとっては価格以上の価値があります。例えば、自宅で小規模サーバー群を動かしているホビイストや、自作NAS・IoTゲートウェイに手を出している技術者には、おすすめできる選択肢です。逆にライトユーザーにはオーバースペック気味かもしれませんが、それでも未来を見据えて投資する価値があると感じます。
今後の展望
Orange Pi 5 Plusの登場で、ラズパイ一強だった市場に明確な競争相手が現れた印象です。今後、この競争がユーザーにとって良い方向(価格競争や製品改良)に働くことを期待します。Raspberry Pi側も性能強化版や大容量メモリ版の投入、在庫安定化などで巻き返しを図るでしょうし、Orange Pi側も更なるファームウェアアップデートや次世代モデルの開発を進めるでしょう。特にソフトウェア面では、メインラインLinuxへの対応が進めばOrange Piの価値は一層高まります。また、RK3588は非常にパワフルなSoCですので、これを活かした派生モデル(例えば小型化したOrange Pi 5 Plus Miniや、NVMeを2基搭載したプロ向けボード等)が出てくる可能性もあります。
ユーザーコミュニティの動向にも注目です。日本国内でも徐々にOrange Pi 5 Plusのレビューや解説記事が増えており、本機の知名度は上がっています。Orange Pi公式もフォーラムやGitHubでユーザーの声を拾い上げて改善を重ねています。将来的に公式で無線搭載版のPlus(仮にOrange Pi 5 Plus Wi-Fiエディションのような)が出れば、より万能な一台になるでしょうし、あるいはRK3588の後継となるSoCを睨んだOrange Pi 6シリーズの登場もいずれあるかもしれません。
いずれにせよ、Orange Pi 5 Plusは2023年~2024年現在における「最高峰SBCの一角」であり、そのメリット・デメリットを理解して使いこなすことで、多くのプロジェクトに新たな可能性をもたらしてくれるでしょう。筆者個人の感想としても、購入して得られた満足度は非常に高く、今後もメインマシンの一つとして活躍してくれそうです。Raspberry Piももちろん素晴らしいプラットフォームですが、Orange Pi 5 Plusが示した高性能路線はSBCの新たな潮流となりつつあり、今後のSBC界隈の発展がますます楽しみになりました。
最後に、Orange Pi 5 Plusの総合評価を端的にまとめます。メリットは「とにかく速い、拡張自由、用途を選ばないパワー」。デメリットは「発熱・電力と多少の玄人志向」。これらを踏まえ、ハイエンドSBCを求める方にはOrange Pi 5 Plusは強くおすすめできますし、今後も改良とコミュニティ支援によって更に扱いやすく進化していくことを期待しています。















