Raspberry Pi Imagerのインストール方法 (Windows・macOS・Linux対応)
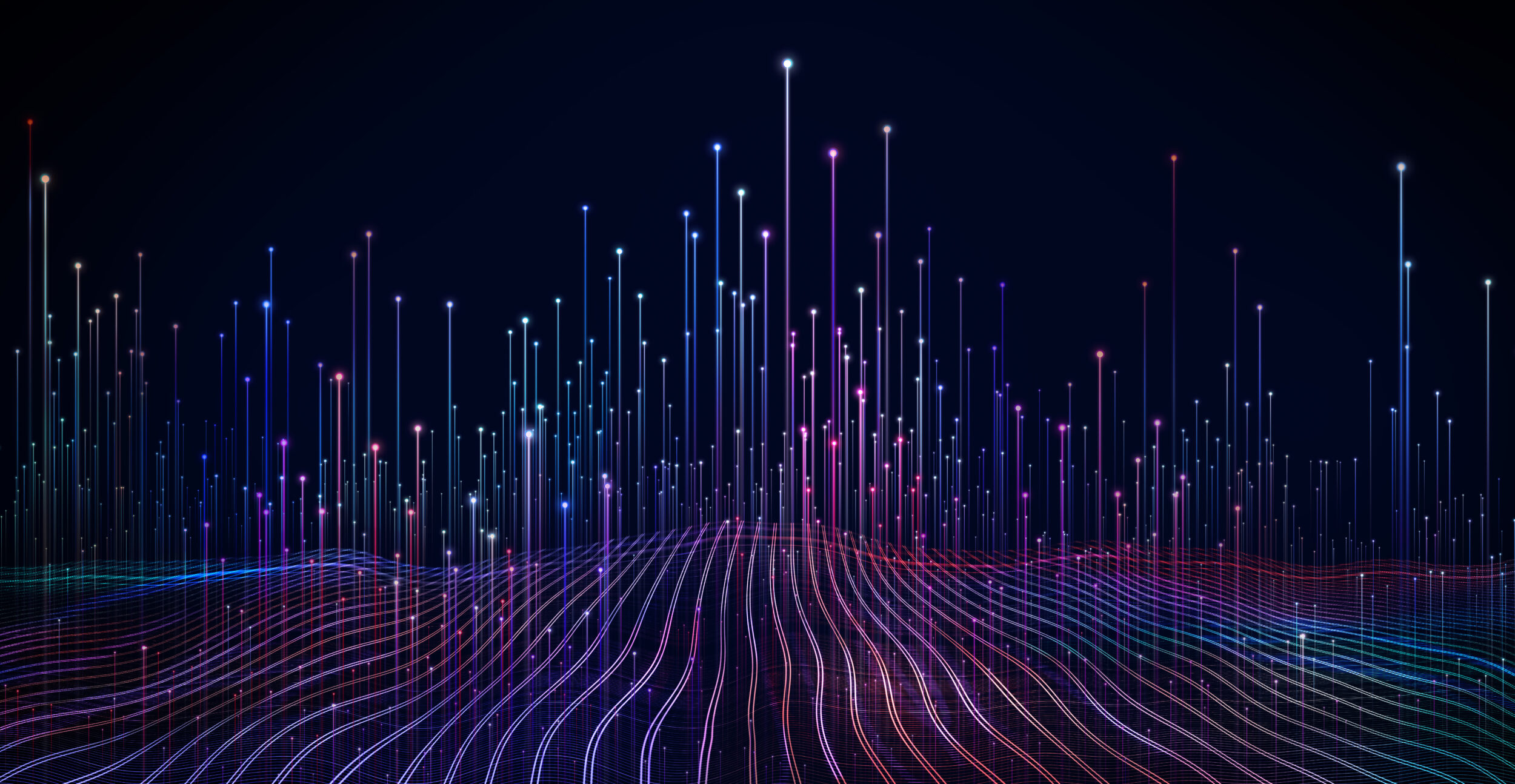
目次
- 1 Raspberry Pi Imagerのインストール方法 (Windows・macOS・Linux対応)
- 1.1 Raspberry Pi Imagerインストールの前提条件と準備 (必要なシステム環境・権限とSDカードリーダーの用意)
- 1.2 Windows版Raspberry Pi Imagerのダウンロードとインストール手順 (公式サイトから入手とセットアップ)
- 1.3 macOS版Raspberry Pi Imagerのインストール手順 (ディスクイメージのマウントとアプリ配置)
- 1.4 Linux (Ubuntu/Raspberry Pi OS)環境へのRaspberry Pi Imagerインストール (パッケージ管理APTによる簡単実行)
- 1.5 Linuxその他ディストリへのImager導入 (スナップパッケージやソースビルドによるインストールオプション)
- 2 Raspberry Pi Imagerの使い方(基本操作とOSイメージ書き込み手順の徹底解説ガイド)
- 3 SDカードへのOSイメージ書き込み手順 (Raspberry Pi Imagerを使用した詳しい手順)
- 4 Raspberry Pi Imagerの主な特徴と便利な機能の紹介 – 知っておきたいメリットと活用例
- 4.1 公式ツールならではのシンプルなUIと直感的操作性がもたらす使いやすさと初心者へのメリット
- 4.2 豊富な対応OSリストと自動ダウンロード機能による利便性 (手動ダウンロード不要の快適さ)
- 4.3 先進的なカスタマイズ機能(事前設定オプション)でセットアップを効率化
- 4.4 マルチプラットフォーム対応(Windows/macOS/Linux)とオープンソースならではの拡張性がもたらす利点
- 4.5 その他の便利機能(イメージ検証・自動メディア排出・完了音通知・利用統計オプションなど)の紹介
- 4.6 Raspberry Pi Imagerを活用した具体的ユースケースとメリット(複数デバイスへの一括OS展開例など)
- 5 Raspberry Pi ImagerでサポートされているOS一覧と各OSの選択方法を詳しく解説します
- 5.1 Raspberry Pi OS(公式OS)フル版・Lite版など各エディションの特徴とImagerでの選択方法
- 5.2 他の汎用Linuxディストリビューション (Ubuntuなど)をImagerで選択する手順と留意点の詳細解説
- 5.3 メディアセンター向けOS (LibreELEC)とレトロゲーム向けOS (RetroPieなど) のImagerでの選択手順と特徴
- 5.4 IoTや産業用途など専門向けOS (例: Home Assistantやk3OS) のラインナップとImagerでの各OS選択ポイント
- 5.5 Imagerの“Use custom”機能による任意のOSイメージファイルの書き込み手順と注意点の詳細解説
- 6 Raspberry Pi Imagerの詳細設定とカスタマイズ方法(ユーザー名・Wi-Fi・SSH設定など)
- 7 Raspberry Pi Imagerのバージョンアップ情報 – 最新機能と更新内容を徹底解説します
- 7.1 Raspberry Pi Imagerのリリース履歴とバージョンアップの重要性 (機能強化の歩み)
- 7.2 Ver 1.6: Advanced Optionsメニュー初搭載による事前設定機能の実現 (2021年)
- 7.3 Ver 1.7: UI改善とデフォルトユーザー廃止対応などの主な変更点 (2022年)
- 7.4 Ver 1.8: モデル選択画面・タブ式設定UI導入など最新機能の追加 (2023年)
- 7.5 Ver 1.9: Qt6への移行とAppImage提供など最新バージョンの更新内容 (2024-2025年)
- 7.6 定期的なバージョンアップのメリットとアップデート方法 (最新機能の活用のために)
- 8 Raspberry Pi本体へのセットアップと初期起動手順 – SDカード挿入から初期設定までの解説
- 9 Raspberry Pi OSの日本語化・ローカライズの手順 – 言語設定と表示を日本語にする方法を解説
- 10 Raspberry Pi ImagerとRaspberry Pi本体のトラブルシューティングとよくある質問(FAQ集)
Raspberry Pi Imagerのインストール方法 (Windows・macOS・Linux対応)
Raspberry Pi Imagerインストールの前提条件と準備 (必要なシステム環境・権限とSDカードリーダーの用意)
Raspberry Pi Imagerをインストールする前に、いくつかの前提条件と準備事項を確認しておきましょう。まず対応するホストPCのOSですが、Windowsの場合は64ビット版Windows 10以降、macOSの場合はバージョン11(Big Sur)以降が推奨されます。LinuxではUbuntu 22.04やDebian Bookworm(それ以降)など比較的新しいディストリビューションが必要です。古いOSでは正常に動作しない可能性があるため、事前にご自身の環境を確認してください。
次にハードウェアの準備です。作業するPCにSDカードリーダーが搭載されているか、あるいはUSB接続のカードリーダーが用意できていることを確認します。これは、Raspberry Pi用のmicroSDカードにOSを書き込むために必要です。また、Raspberry Pi ImagerでSDカードに直接書き込む際には管理者権限(Administrator/root)が求められる場合があります。例えばWindowsでは、書き込み開始時にユーザーアカウント制御(UAC)の許可を求められることがあります。Linuxでもポリシーによりルート権限を要求されることがあるため、適宜パスワード入力やsudoの利用が必要です。さらに、後述するようにImagerはOSイメージをインターネットからダウンロードするため、安定したネットワーク接続も必須です。以上の準備が整っているか確認した上で、各OSごとのインストール手順に進みましょう。
Windows版Raspberry Pi Imagerのダウンロードとインストール手順 (公式サイトから入手とセットアップ)
Windows環境でRaspberry Pi Imagerをインストールするには、まず公式サイトからインストーラを入手します。Raspberry Piの公式ダウンロードページにアクセスし、「Download for Windows」ボタンをクリックすると、インストーラ実行ファイル(imager_※※※.exe)のダウンロードが始まります。ダウンロードが完了したら、その.exeファイルをダブルクリックして実行してください。インストーラが起動したら、画面の指示に従ってセットアップを進めます。
インストーラでは、使用許諾への同意やインストール先フォルダの確認などが順に求められます。特に変更がなければデフォルト設定のまま「Install(インストール)」ボタンをクリックすることで、自動的に必要ファイルのコピーが行われます。インストールは数秒〜数十秒程度で完了し、最後に「Finish(完了)」をクリックするとRaspberry Pi Imagerを起動することもできます。初回起動時にはWindowsのセキュリティ警告(「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」)が表示される場合がありますが、「はい」を選んで先に進んでください。以上でWindows環境へのインストールは完了です。以降はスタートメニューから「Raspberry Pi Imager」を検索・選択してプログラムを起動できます。
macOS版Raspberry Pi Imagerのインストール手順 (ディスクイメージのマウントとアプリ配置)
macOSでRaspberry Pi Imagerを利用する場合も、まず公式サイトからmacOS向けのディスクイメージ(DMGファイル)をダウンロードします。公式ダウンロードページで「Download for macOS」ボタンをクリックすると、imager_※※※.dmgファイルのダウンロードが開始されます。ダウンロード完了後、このDMGファイルをダブルクリックしてマウントしてください。すると仮想ディスクとしてRaspberry Pi Imagerのインストーラが開きます。
ディスクイメージがマウントされると、その中にRaspberry Pi Imager.appが表示されるはずです。このアプリケーションアイコンをApplications(アプリケーション)フォルダにドラッグ&ドロップしてコピーします。これでシステムへのインストールは完了です。DMGをマウントした際に表示されたウィンドウは閉じ、仮想ディスクを「取り出し」てください。その後、Applicationsフォルダ内にコピーしたRaspberry Pi Imagerアプリをダブルクリックすれば起動できます。
初回起動時、macOSでは「インターネットからダウンロードされたアプリケーションです」という警告ダイアログが表示される場合がありますが、「開く」を選択して先に進みます。また、macOS版Imagerでは、Wi-Fi設定時にキーチェーンへのアクセス許可を求めるダイアログが出ることがあります。これは現在Macが接続しているWi-FiのSSIDやパスワード情報をImagerが自動取得するための機能です。必要に応じて「Yes(はい)」をクリックし、キーチェーンへのアクセスを許可してください。以上でmacOSへの導入は完了です。
Linux (Ubuntu/Raspberry Pi OS)環境へのRaspberry Pi Imagerインストール (パッケージ管理APTによる簡単実行)
Linux環境では、ディストリビューションに応じてインストール方法が異なりますが、Debian系(UbuntuやRaspberry Pi OSなど)の場合はAPTパッケージマネージャを使うのが簡単です。例えばUbuntuなら、まずターミナルでパッケージリストを更新し、その後rpi-imagerパッケージをインストールします:
sudo apt update
sudo apt install rpi-imager上記コマンドを実行すると、リポジトリからRaspberry Pi Imager(および必要な関連ライブラリ)がダウンロード・インストールされます。インストール後は、デスクトップ環境のアプリケーションメニューから「Raspberry Pi Imager」を起動するか、ターミナルでrpi-imagerコマンドを入力してGUIを立ち上げます。Raspberry Pi OS(旧Raspbian)の場合も同様に、標準リポジトリにImagerが含まれているためsudo apt install rpi-imagerでインストール可能です。
Ubuntu以外のDebian系Linuxでも、APT経由でインストールできる場合があります。ただしディストリビューションのバージョンによっては公式パッケージが古い可能性があるため、最新機能を使いたい場合は公式サイトから提供されている最新のDebパッケージを直接ダウンロードしてインストールする方法もあります。公式サイトではUbuntu用としてDebパッケージが配布されていますので、必要に応じてダウンロード後sudo dpkg -i コマンドでインストールしてください。
Linuxその他ディストリへのImager導入 (スナップパッケージやソースビルドによるインストールオプション)
Ubuntu/Debian系以外のLinuxディストリビューションでも、Raspberry Pi Imagerを利用できます。公式には複数の方法が用意されており、その一つがSnapパッケージの利用です。Snapに対応する環境であれば、ターミナルからsudo snap install rpi-imagerと実行することでImagerをインストールできます。Snap版は依存関係込みで配布されるため、FedoraやArchなどDebパッケージが使えないディストリビューションでも容易に導入可能です。Snapインストール後にデバイスが認識されない場合は、snap connect rpi-imager:removable-mediaで外部メディアへのアクセス権限を付与してください。
また、Raspberry Pi Imagerはオープンソースであり、ソースコードがGitHubで公開されています。そのため、開発者や高度なユーザーはソースからビルドして利用することもできます。ただし通常は、公式が提供するバイナリを使う方が簡単でしょう。なお、最新のバージョン1.9以降ではLinux向けにAppImage形式での配布も始まっています。AppImageはほぼ全てのライブラリをバンドルした実行ファイルで、ダウンロード後に実行権限を与えるだけで動作します。これにより、さまざまなLinuxディストロで煩雑な依存解決なしにImagerを起動できる利点があります。以上、自身の環境に合った方法でRaspberry Pi Imagerをインストールしてください。
Raspberry Pi Imagerの使い方(基本操作とOSイメージ書き込み手順の徹底解説ガイド)
Raspberry Pi Imagerの起動方法とユーザーインターフェース画面の基本構成と各機能の概要
インストール後、さっそくRaspberry Pi Imagerを起動してみましょう。Windowsではスタートメニューから、macOSではLaunchpadもしくはアプリケーションフォルダから、Linuxではアプリケーションメニューや端末からrpi-imagerコマンドで起動できます。起動すると、Imagerのメイン画面が表示されます。このユーザーインターフェースは非常にシンプルで、上部に「OSを選ぶ」(Choose OS)ボタン、次に「ストレージを選ぶ」(Choose Storage)ボタン、そして下部に「書き込む」(Write)ボタンが配置されています。画面右下には歯車アイコンのボタンもあり、これが後述する詳細設定(Advanced Options)メニューの入り口です。
各UI要素の役割を整理すると、まず「OSを選ぶ」ボタンは書き込みたいオペレーティングシステムのイメージを選択するためのものです。その下の「ストレージを選ぶ」ボタンは、書き込み先となるSDカードやUSBメモリなどのターゲットデバイスを指定するためのものです。そして「書き込む」ボタンをクリックすると、選択したOSイメージが指定したストレージデバイスに対して書き込みされます。一連の操作は数クリックで完了するように設計されており、初めてでも直感的に使えるでしょう。Imagerは公式ツールだけあって無駄のない洗練されたUIを持ち、基本的には画面の指示に従って上から順に設定を選んでいけばOKです。
Imagerを起動した直後はまだ何も選択されていない状態です。画面中央には「OSを選択してください」や「ストレージを選択してください」といったメッセージが表示されます。これから行う手順としては、(1) OSイメージの選択、(2) 書き込み先デバイスの選択、(3) 詳細設定の必要に応じた設定、(4) 書き込み実行、という流れになります。それでは次の節から、各操作を順を追って詳しく解説していきます。
「OSを選択」メニューの使い方とImagerで利用可能なOSイメージ類型の詳細解説 (各OSカテゴリーの特徴)
まず最初のステップは、書き込みたいOSイメージを選ぶことです。メイン画面の「OSを選ぶ」ボタンをクリックすると、利用可能なOS一覧メニューが表示されます。Raspberry Pi Imagerには、公式が提供する主要なOSのリストが組み込まれており、ユーザーは自分で事前にイメージファイルをダウンロードしておかなくても、このリストから選ぶだけで自動的にネット経由でOSイメージを取得してくれます。
表示されるメニューはカテゴリー別に分かれています。最上部には「Raspberry Pi OS」があり、これはラズパイ公式の標準OSです。メニューでは最新版の32bit版Raspberry Pi OSが推奨OSとして表示され、さらに「Raspberry Pi OS (other)」という項目の中に64bit版やLite版(最小構成でデスクトップ無しの版)、過去のリリースなどが含まれています。例えばデスクトップ環境が不要なサーバ用途なら「Raspberry Pi OS Lite」を、4GB以上のRAMを活かすなら64bit版を選ぶなど、用途に応じたエディションを選択できます。Imager上でOSを選択すると、そのOSイメージはオンラインから自動ダウンロードされるため、ユーザーが別途ブラウザで探す手間を省ける点は大きな利点です。
Raspberry Pi OS以外にも、多様なOSがカテゴリごとに用意されています。例えばUbuntuカテゴリでは、ラズパイ向けに公式提供されているUbuntuのServer版やDesktop版を選択可能です。メディアプレイヤー向けOSとしては、Kodiメディアセンター用のLibreELECがリストされています。またレトロゲーム向けOSには、RetroPieやRecalboxなど、ラズパイをレトロゲーム機にするためのカスタムOSも含まれています。さらにスペシャリスト向けOSのカテゴリには、IoTや産業用途など特殊な用途に最適化されたディストリビューションが並んでいます。例えばリアルタイム性を重視したものや、ネットワーク機器としての利用に特化したものなどが該当します。さらにはRISC OSといったLinuxではないOSも用意されており、教育用途やレガシーな環境再現に興味がある方に提供されています。
このようにImagerで直接選択できるOSは非常に豊富で、公式OSからサードパーティの専門OSまで網羅されています。各カテゴリーの中で気になるOSをクリックすると、そのOS名の横に説明が表示される場合もあります。例えばUbuntuであれば「popular Linux distribution provided by Canonical」といった紹介文が表示され、概要を知ることができます。目的のOSが決まったら、それをクリックすることでメイン画面に選択が反映されます。
「ストレージを選択」メニューの操作方法とSDカード、USBドライブ選択時の注意点と誤削除防止の確認方法
次に、OSを書き込む先のストレージを選びます。「ストレージを選ぶ」ボタンをクリックすると、PCに接続されているリムーバブルドライブの一覧が表示されます。典型的にはSDカードリーダーに挿入したmicroSDカードや、USBメモリが候補として現れます。ここで注意すべきは、正しいデバイスを選択することです。誤ってPCの内蔵ドライブや外付けHDDなどを書き込み先に指定すると、その内容を消去してしまう恐れがあります。Imagerは基本的にシステムドライブ(C:ドライブ等)はリストに表示しない設計ですが、USB接続のSSD等は表示される場合がありますので十分に確認してください。
デバイス一覧にはドライブ名や容量が表示されるので、それを手掛かりに選択します。例えば「Generic Mass Storage – 16 GB」などのように容量が分かれば、自分が挿したSDカードかどうか判断できます。それでも自信がない場合は、選択前に一度エクスプローラーやファイルマネージャで該当ドライブのドライブレターやボリューム名を確認しておくと安心です。また、書き込み対象のSDカード内に重要なデータが残っている場合は、この時点でバックアップを取っておいてください。Imagerによる書き込みは対象ディスクの内容を全て上書きします。一度書き込みを開始すると元のデータは復元困難になるため、必ず事前に必要なファイルの退避を済ませましょう。
ストレージ選択が終わると、メイン画面には選択したデバイスの名称やドライブレターが表示されます。これでOSイメージと書き込み先デバイスの指定が完了しました。なお、万一間違ったデバイスを選んでしまった場合は、再度「ストレージを選ぶ」をクリックして正しいものを選び直すことができます。最後にもう一度、選択中のデバイス名と容量を見て、誤りがないか確認してください。
OSイメージ書き込みの開始操作手順と進行状況のモニタリング方法の詳細について (進捗バーやログの確認など)
OSイメージと書き込み先デバイスを選択し終えたら、いよいよ書き込み処理を開始します。メイン画面右下の「書き込む」ボタンをクリックすると、最終確認のダイアログが表示されます。このダイアログには選択中のOS名とデバイス名が表示され、「このデバイスに書き込みを行います。よろしいですか?」といった内容の確認を求められます。内容を確認し問題なければ、「はい」あるいは「Yes」をクリックして処理を開始します。
書き込みが始まると、進行状況を示すプログレスバーが表示されます。Imagerは選択したOSイメージをインターネットからダウンロードしながら、同時にそのデータをSDカードに書き込んでいきます。そのため、ファイルサイズやネットワーク速度によって所要時間は変わりますが、一般的には数分から十数分程度で完了します。例えば4GB程度のRaspberry Pi OSイメージの場合、5〜15分程度が目安です。進行中はプログレスバーの下にパーセンテージや残り時間の推定が表示されるので、それを目安に待ちましょう。Imager 1.8以降では圧縮ファイルの実サイズを考慮した精度の高い進捗表示が行われるため、途中で止まったように見える現象も緩和されています。
書き込み中はPCやカードリーダーからSDカードを抜いたりしないよう注意してください。万一途中で処理を中断すると、イメージが壊れ起動できなくなる可能性があります。また、Imagerのウィンドウには詳細ログやメッセージが表示されることがあります。エラーが出た場合はそのメッセージを確認してください。正常に進めばプログレスバーが徐々に右端まで伸びていき、「書き込み完了」の旨のダイアログかメッセージが表示されます。
OS書き込み完了後の結果確認、メディア(SDカード/USB)の安全な取り外し手順と次のステップについて
書き込みが100%に達し完了メッセージが表示されたら、まず結果を確認しましょう。Imagerでは書き込み完了時に「Write Successful」等のダイアログが表示され、必要に応じて「続行」(Continue)ボタンを押すことでメイン画面に戻ります。また、設定によっては書き込み完了時に効果音で通知する機能や、自動的にメディアを排出(アンマウント)する機能もあります。例えば「完了時に音を鳴らす」「完了時にメディアを取り出す」といったオプションを有効にしていれば、このタイミングでPCが通知音を鳴らしたりSDカードを安全に取り外せる状態にしてくれます。
次に、SDカード(またはUSBメモリ)をPCから取り外します。自動排出機能を使っていない場合、Windowsではエクスプローラーで該当ドライブを右クリックして「安全に取り出す」を実行するか、タスクトレイのハードウェアイジェクトの安全取り外しアイコンからメディアを停止してください。macOSではFinderのサイドバーからSDカードをEject(⏏マークをクリック)してアンマウントします。Linuxでもファイルマネージャ上で「取り出し」を行うか、umountコマンドでアンマウントしてください。これにより書き込みキャッシュがすべてフラッシュされ、データ破損のリスクなくカードを抜くことができます。
メディアを安全に取り外したら、いよいよ次のステップはRaspberry Pi本体でのセットアップです。準備したmicroSDカードをラズパイのカードスロットに挿入し、ラズパイを起動します(この手順については後述の「8. Raspberry Pi本体へのセットアップと初期起動手順」で詳しく説明します)。以上が、Raspberry Pi Imagerを使ったOSイメージ書き込みの一連の基本操作になります。
SDカードへのOSイメージ書き込み手順 (Raspberry Pi Imagerを使用した詳しい手順)
OS書き込み用SDカードの事前準備と接続方法(カードリーダー使用・容量/性能の目安とフォーマット確認)
Raspberry PiにOSをインストールするために使用するmicroSDカードを準備します。一般的に容量8GB以上、できれば16GB以上のカードを用意するとよいでしょう。容量が小さすぎると最新のOSイメージを書き込めない場合があります。また、速度クラスも重要です。最低でもClass 10(U1相当)以上の高速なカードを選ぶことで、書き込みやRaspberry Pi動作時の性能が安定します。
SDカードをPCに接続する際は、内蔵のSDカードスロットがあればそこに、無い場合はUSB接続のカードリーダーを使用します。microSDカードはアダプター(SDカードサイズのケース)に装着してから挿入してください。カードを挿入する向きにも注意しましょう。カードリーダーの端子面とSDカードの金色の接点がきちんと接触する向きで差し込みます。挿入後、PCのエクスプローラー(またはFinder)でカードのドライブが認識されているか確認します。
必要に応じてSDカードのフォーマットを確認しておくこともおすすめします。新品のカードや以前に他のOSを書き込んでいたカードでも、Raspberry Pi Imagerを使えば自動で上書きされるため事前フォーマットは必須ではありません。しかし、カードの論理容量が正しく認識されているか、破損したパーティションが無いかを確認する意味で、一度FAT32形式でフォーマットしておくと安心です。Windowsなら「SD Card Formatter」ツールを用いてクイックフォーマットするか、エクスプローラーからFAT32でフォーマットします(64GB以上のカードはexFATになるため、そのままでOKです)。macOS/Linuxでも必要ならfdiskやディスクユーティリティでパーティション情報を確認できます。
以上の準備が整ったら、PCにSDカードを接続した状態でRaspberry Pi Imagerを起動しましょう。Imager側でSDカードが正しく検出されれば、書き込み手順に進むことができます。
Raspberry Pi Imagerで書き込むOSイメージの選択手順(公式OS一覧から選ぶ場合とローカルイメージを使う場合)
Raspberry Pi Imagerを起動したら、まず書き込むOSイメージを選択します。「OSを選ぶ」ボタンをクリックすると公式が提供するOS一覧が表示されます。通常は最上位にある「Raspberry Pi OS (32-bit)」がデフォルトの推奨OSとして選択可能です。そのままこの最新のRaspberry Pi OSを使う場合はそれをクリックします。一方、64ビット版やLite版(CLIのみの軽量版)を使いたい場合は、一覧の「Raspberry Pi OS (other)」カテゴリを開き、その中から目的のエディションを選択します。例えば64ビット版Liteを使いたい場合、「Raspberry Pi OS (other) > Raspberry Pi OS Lite (64-bit)」という順序で選びます。
Raspberry Pi OS以外の公式イメージを利用する場合も、同様に一覧から選べます。Ubuntuを使いたい場合は「Ubuntu」カテゴリをクリックすると、Ubuntu ServerやUbuntu Coreなど複数の選択肢が表示されます。レトロゲームエミュレータを構築したいなら「RetroPie」や「Recalbox」といった項目を選びます。メディアセンター用途なら「LibreELEC」が該当します。それぞれのOSには簡単な説明が付いているものもあるので、初めて使うOSの場合は参考にしてください。
リストにないOSを使用したい場合、Imagerはカスタムイメージにも対応しています。OS一覧メニューをスクロールして最下部にある「Use custom (カスタムイメージを使用)」を選択すると、ファイル選択ダイアログが開きます。ここで事前にダウンロードしておいたOSイメージファイル(.imgや.zip形式)を指定します。ファイルを選ぶとImagerの画面にカスタムイメージのパスが表示され、以降は公式イメージと同様に書き込み操作が可能です。対応フォーマットはRAWイメージ(.img)、ZIP圧縮、ISOなど一般的な形式に対応しています。
なお、Imager v1.8以降では、イメージファイルをImagerウィンドウ上にドラッグ&ドロップすることでも「Use custom」を自動的に選択できます。このドラッグ&ドロップ機能を使えば、エクスプローラーから直接ファイルを放り込むだけで対象イメージがセットされるので便利です。カスタムイメージを利用する際は、公式サイトから取得した信頼できるファイルかどうか確認してください。不正なOSイメージを書き込むとセキュリティ上のリスクがありますので、出所には注意しましょう。
書き込み対象となるSDカードの選択と上書き時の注意事項(重要データのバックアップ確認など)
OSイメージを選択したら、次は書き込み先となるSDカードを指定します。「ストレージを選ぶ」ボタンをクリックし、接続中のデバイス一覧から該当のSDカードを選択します。このとき容量表示などを見て、自分が用意したカードに間違いないか確認してください。万が一リストに正しいカードが見当たらない場合、SDカードリーダーの接続不良やカード認識の問題が考えられます。カードを挿し直したり、別のUSBポートにリーダーを差し替えてみてください。
正しいデバイスを選んだら、上書きによるデータ消失に注意します。選択したSDカード上の既存データは書き込みによってすべて消去されます。重要なファイルが入っている場合は必ず事前にバックアップを取っておきましょう。また、誤ってシステムの別ドライブを選択していないか、今一度確認してください。Imagerでは選択後のメイン画面にデバイス名が表示されています。例えば「Generic SD Card Reader – 16 GB」など容量付きで表示されているので、容量が自分のカードと一致するかチェックします。
ストレージ選択に問題がなければ、後は書き込みを実行するだけです。ただし、初めて使用するSDカードの場合、一度フォーマットが必要になるケースもあります。一般にImagerが自動で処理するため手動フォーマットは不要ですが、もしImagerでエラーが出る場合はOS標準のフォーマッタでFAT32フォーマットを試みてください。それでも解決しない場合、カード自体の不良も疑われます。その際は別のカードを用意するか、新しいカードに交換して再度試します。
OSイメージ書き込みプロセスの実行と完了までの所要時間の目安(進捗状況の確認方法)
準備が整ったら「書き込む」ボタンを押してOSイメージの書き込みを開始します。クリック後、確認ダイアログで内容を承諾すると実行が始まります。Imagerは自動的に指定したOSイメージをダウンロードしつつ、SDカードへの書き込みを行います。そのため、書き込み中はネットワーク帯域とストレージ速度の両方に依存します。一般に、高速な回線とUSB3.0対応カードリーダーを用いても、4GB程度のイメージでは5~10分程度はかかります。
Imagerの画面には進捗バーが表示され、現在の処理状況が可視化されます。例えばダウンロードフェーズと書き込みフェーズで2段階に進むような挙動を示す場合もありますが、Imager 1.8以降では.xz圧縮ファイルの実サイズを把握した上で正確な残り時間を計算できるよう改良されています。そのため、進捗バーが途中で長時間止まったままになる、といった状況は減少しています。なお進捗バー下に表示されるパーセンテージ表示や速度表示も参考にするとよいでしょう。
書き込みプロセスが完了すると、Imager上で通知が行われます。設定で「完了時にサウンドを鳴らす」をオンにしている場合はビープ音が鳴り、また「完了時にメディアを排出する」をオンにしていれば自動的にSDカードがアンマウントされます。そうでない場合も、画面に「書き込みが成功しました」等のメッセージが表示されます。これが表示されたら「続行」ボタンを押してダイアログを閉じてください。以上でOSイメージの書き込み処理は完了です。
書き込み成功の確認方法とSDカードの取り外し(PC上での内容確認と安全な取り出し操作)
Imagerが書き込み完了を報告した後、念のため成功しているか検証する方法があります。一つは、エクスプローラーやFinderでSDカードの内容を覗いてみることです。書き込み直後のSDカードには、OSごとに異なりますがブートローダ用のパーティション(FAT32)やLinuxのルートファイルシステムが書き込まれているはずです。Windowsからはブート用のFAT領域だけ見える場合が多いですが、そこにbootやconfig.txt等のファイルが見えれば書き込み成功の目安となります。ただし、中身を誤って変更しないよう注意してください。
内容確認が終わったら、SDカードをPCから安全に取り外します。Windowsではタスクバーの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし、該当ドライブを停止してから抜いてください。macOSではFinderでSDカードを右クリックし「取り出す」を選択します。LinuxでもumountコマンドやGUIでアンマウントしてから抜きます。Imagerの自動排出機能を有効にしていた場合、書き込み完了時点で既にアンマウント済みなのでそのまま抜いて構いません。
カードを取り外したら、いよいよRaspberry Piに挿入して起動します。この先はRaspberry Pi本体側での初期設定に移ります(詳細は次の「8. Raspberry Pi本体へのセットアップと初期起動手順」で解説します)。以上が、SDカードへのOSイメージ書き込み手順の詳細な流れとなります。
Raspberry Pi Imagerの主な特徴と便利な機能の紹介 – 知っておきたいメリットと活用例
公式ツールならではのシンプルなUIと直感的操作性がもたらす使いやすさと初心者へのメリット
Raspberry Pi Imager最大の特徴の一つは、そのシンプルで直感的なユーザインタフェースです。公式ツールとして設計されているため、専門知識がなくても迷わず操作できる配慮が随所に見られます。実際、OSの選択と書き込み先デバイスの指定、そして書き込み開始という一連の手順は3〜4回のクリックで完了します。画面も大きなボタンと分かりやすいテキストで構成されており、初めてRaspberry Piを触るユーザーでも戸惑うことがほとんどありません。
この使いやすさは、特に初心者にとって大きなメリットです。以前はOSイメージを書き込むのにddコマンドや他社製のイメージ書き込みソフト(例えばbalenaEtcher等)を使う必要があり、ファイルの入手や選択に注意が必要でした。しかしImagerでは公式サイトから必要なOSを直接選べてしまうため、誤ったファイルをダウンロードしてしまうリスクも低減します。またGUI操作のため、タイピングに不慣れなユーザーでも安心です。全体として、Raspberry Pi Imagerは「シンプルさ」を追求することで、ラズパイのセットアップを初めて行う人々のハードルを大きく下げています。
さらに、Imagerは公式にサポートされているツールであるという点も安心材料です。Raspberry Pi財団自身が開発・提供しているため、信頼性が高く、変な広告や不要なバンドルソフトも一切ありません。こうしたクリーンで洗練されたUI/UXは、趣味で扱う学生やメイカーから業務で大量展開するプロフェッショナルまで、幅広い層に受け入れられる重要な要素となっています。
豊富な対応OSリストと自動ダウンロード機能による利便性 (手動ダウンロード不要の快適さ)
Raspberry Pi Imagerが多くのユーザーに愛用される理由の一つに、その豊富な対応OSリストと自動ダウンロード機能があります。Imagerには主要なOSのイメージ情報があらかじめ組み込まれており、ユーザーは一覧から選ぶだけでOKです。例えば、公式のRaspberry Pi OSをはじめ、Ubuntu、LibreELEC、RetroPie、さらにはRISC OSなど、多岐にわたるOSが利用可能です。これらはRaspberry Pi財団や各プロジェクトが公式に提供するものであり、Imagerはそのリンク先から最新のイメージを自動取得してくれます。
この仕組みのおかげで、ユーザー自身が個別にOSイメージを探してダウンロードする手間が省けます。「どのサイトからOSを落とせばいいのか」「最新バージョンはどれなのか」といった心配をする必要がありません。Imager上のリストは最新情報にアップデートされており、例えばRaspberry Pi OS 64-bit版の正式リリースに伴ってImagerも64-bit版の各エディションをサポートしました。32-bit版が依然推奨ではありますが、選択肢として64-bit版もメニューから直接ダウンロード・書き込みできます。
また、ImagerはOSごとの公式リポジトリと連携しているため、安心感があります。第三者のミラーサイトからダウンロードする場合に比べ、信頼性の高いソース(例えばラズパイ公式サイトやUbuntu公式など)から取得するため、改ざんやウイルスの心配が極めて低いです。複数のOSを試したい場合にも、Imager一つで完結するため非常に効率的です。こうした包括的なOS対応と自動化により、Raspberry PiのマルチOS環境構築が容易になっている点は、Imagerの大きなメリットでしょう。
先進的なカスタマイズ機能(事前設定オプション)でセットアップを効率化
Raspberry Pi Imagerには、単なるイメージ書き込みツールの枠を超えて高度なカスタマイズ機能が備わっています。これはバージョン1.6で導入された「詳細設定 (Advanced Options)」メニューで、OSを書き込む際に各種初期設定をあらかじめ仕込んでおけるという強力な機能です。例えば以下のような事柄をImager上で設定可能です:
- ホスト名の変更: デフォルトは
raspberrypiですが、ネットワーク上で識別しやすい名前に変更できます。 - SSHの有効化: ヘッドレス運用のために、初回起動時からSSHサーバを起動し、リモートから接続できるようにします。
- ユーザー名・パスワードの事前設定: 最近のRaspberry Pi OSではセキュリティ向上のためデフォルトユーザー
piが存在しないので、Imagerで新しい管理ユーザーを作成できます。 - Wi-Fi接続設定: SSID(ネットワーク名)とパスワード、国コードを入力しておけば、ラズパイ起動時に自動でWi-Fiに接続可能です。
- ロケール/タイムゾーン設定: 言語やタイムゾーン、キーボードレイアウトを指定し、初回ブート時に適用させることができます。
これらの設定をImagerで仕込んで書き込みを行うことで、Raspberry Piを起動してから行う初期設定の手間を大幅に省くことができます。特に複数台のラズパイを展開する場合、一度設定内容を保存しておけば、以降の書き込みですべて同じ設定を適用できるため非常に効率的です。従来、ヘッドレス運用のためにSDカードのbootパーティションに手動でsshという空ファイルを置いたり、wpa_supplicant.confを作成してWi-Fi情報を書き込んだりする必要がありました。しかしImagerの詳細設定機能の登場によって、これらがGUI上のチェックボックス操作だけで完結するようになったのです。
高度な事前設定オプションは上級者にとっても便利ですが、初心者にとっても有用な場合があります。例えばキーボードレイアウトを英語配列から日本語配列に変えておく、タイムゾーンを最初から「Asia/Tokyo」にしておく、といった設定は、日本のユーザーにとって手間を減らすポイントです。Imagerではこのようなローカライズ設定も簡単に行えるため、初回起動後すぐに自分の望む環境で作業を始められます。こうしたカスタマイズ性の高さも、Raspberry Pi Imagerが持つ大きな利点の一つです。
マルチプラットフォーム対応(Windows/macOS/Linux)とオープンソースならではの拡張性がもたらす利点
Raspberry Pi Imagerは、Windows・macOS・Linuxという主要なデスクトップOS全てで利用できるよう提供されています。これは利用者にとって非常にありがたい点です。たとえば職場ではWindowsマシン、家ではMacBook、ラボではLinuxワークステーション、といった環境が分かれている場合でも、どの環境でも同じImagerツールを使ってSDカードを作成できます。UIや操作手順もプラットフォーム間でほぼ統一されているため、一度使い方を覚えれば他のOSでも違和感なく作業できます。
また、本ソフトウェアがオープンソースで開発されている点も重要です。GitHub上でソースコードが公開され、世界中の開発者からの貢献やフィードバックを受けながら改良が続けられています。その結果、マルチプラットフォームへの最適化やバグ修正、機能追加が活発に行われています。例えばバージョン1.7ではQtライブラリの更新によるUI刷新やApple M1チップへの対応、Linux向けAppImage配布などが行われました。オープンソースであることで新機能の提案や地域語翻訳の追加も進みやすく、実際にスロベニア語の追加翻訳などコミュニティ発の改良も取り込まれています。
拡張性という観点では、Imagerは現状GUIアプリとして提供されていますが、将来的にコミュニティによってCLIから利用するためのツールや、Imagerの機能を活用した自動化スクリプトが生み出される可能性もあります(※現時点で公式にCLIモードは提供されていませんが、オープンソースであるため実現の余地があります)。総じて、マルチプラットフォーム対応の利便性と、オープンソース由来の拡張性・透明性によって、Raspberry Pi Imagerは多様なユーザー層・利用シーンに適応できる柔軟性を備えています。
その他の便利機能(イメージ検証・自動メディア排出・完了音通知・利用統計オプションなど)の紹介
Raspberry Pi Imagerには、他にもユーザー体験を高めるための細かな便利機能が用意されています。その一つが書き込み後のイメージ検証です。Imagerはデータを書き込んだ後、自動的に内容を読み出して正しく書けたかチェックする機能があります(※特に明示的な検証フェーズがUI上に現れるわけではありませんが、進捗バーが100%に達した後もしばらくアクセスLEDが点滅するのは検証を行っているためです)。これにより、物理メディアの不良などで正しく書き込めなかった場合にも検知でき、ユーザーは安心してSDカードをRaspberry Piに投入できます。
また先述したように、書き込み完了時の通知音や自動メディア排出もImagerの地味ながら便利な機能です。大量のカードを書いているとき、進捗をずっと見ていなくても音で終わりを知ることができますし、完了後に毎回手動で「ハードウェアの安全な取り外し」をしなくても良いのは手間が省けます。これらは詳細設定のオプションで任意に有効化できます。
さらに、Imagerには利用統計(Telemetry)の送信オプションも実装されています。デフォルトでは無効ですが、ユーザーが許可すれば、どのOSイメージを書き込んだかといった匿名化された統計情報や、使用しているホストOSの種類・Imagerのバージョン等がRaspberry Pi財団に送信されます。このデータはImagerの機能改善や人気のOS把握などに役立てられており、ユーザー体験向上に貢献します。プライバシーに配慮し利用したくない場合は、詳細設定でチェックを外しておけばデータは送信されません。
その他、画面表示上の工夫としては長いOSリストの折り返し表示対応(1.7で実装)や、サブカテゴリの入れ子構造対応など、UIの洗練も重ねられています。細かな点ですが、例えばOS選択画面で以前は文字列が途切れて見えなかったのが、現在では適切に改行されるため読みやすくなっています。また、Imager v1.7ではZstandard形式(.zst圧縮)のイメージにも対応し、最新の圧縮フォーマットで配布されるOSにもシームレスに対応しました。このようにRaspberry Pi Imagerは基本機能以外の部分でも、ユーザーの利便性を高めるための様々な工夫と機能拡張がなされています。
Raspberry Pi Imagerを活用した具体的ユースケースとメリット(複数デバイスへの一括OS展開例など)
最後に、Raspberry Pi Imagerの特徴を活かした実際の活用例をいくつか紹介します。まず考えられるユースケースは、複数デバイスへの一括OS展開です。例えば教育現場や製品開発で、同じ設定のRaspberry Piを10台、20台と用意する必要がある場合があります。Imagerの詳細設定でホスト名やWi-Fi情報、ユーザー資格を設定し「常にこの設定を使う」に保存しておけば、次々とSDカードを差し替えて書き込みボタンを押すだけで、全て同じ環境のOSイメージを作成できます。手作業で各カードに設定を書き込む必要がなく、大幅な時間短縮とヒューマンエラー防止につながります。
別のユースケースとしては、各種OSの試用やベンチマーク比較があります。Imagerに揃っているOS一覧を活用すれば、Raspberry Pi上で動く様々なシステムを手軽に試すことが可能です。たとえば「Raspberry Pi OSとUbuntuとではどちらが自分の用途に適しているか」「RetroPieでどの程度エミュレーション性能が出るか試してみたい」といった場合、それぞれのOSを順番に書き込んでブートするだけで比較検証できます。Imagerは公式の最新OSを自動取得してくれるため、ユーザーは常に最新バージョンで試行でき、インターネット上の古いイメージを誤って使ってしまう心配もありません。
さらに、ヘッドレスIoTデバイスの迅速セットアップという場面でもImagerは力を発揮します。例えば工場のセンサーや自宅のNASなど、画面やキーボードを接続しない前提でRaspberry Piを設置する場合、Imager詳細設定でSSH有効化とWi-Fi接続設定を施してSDカードを焼けば、ラズパイ本体に挿して電源を入れるだけで即座にネットワーク経由でアクセス可能になります。これにより、ディスプレイを用意したり有線LANで一時接続する手間を省けます。現場での機器交換時にも、あらかじめ用意したImager設定でSDカードを差し替えるだけで復旧でき、ダウンタイムを最小限にできます。
以上のように、Raspberry Pi Imagerは単なる書き込みツールに留まらず、多台数・多用途のシナリオでその機能を活かせる存在です。公式の信頼性と豊富な機能を兼ね備えたImagerを使いこなすことで、Raspberry Piを用いたプロジェクトの効率と安定性が大きく向上するでしょう。
Raspberry Pi ImagerでサポートされているOS一覧と各OSの選択方法を詳しく解説します
Raspberry Pi OS(公式OS)フル版・Lite版など各エディションの特徴とImagerでの選択方法
Raspberry Pi OSはラズパイ公式の標準OSであり、Imagerで最も目立つ位置に表示されています。Raspberry Pi Imagerでは、まず推奨OSとして32ビット版の「Raspberry Pi OS (32-bit)」がトップに表示されます。このフル版はデスクトップ環境を含む完全版で、一般的な用途に向いています。クリック一つで選択できるので、初めての方は迷ったらこれを選ぶと良いでしょう。
さらに詳細な選択肢として、メニュー内の「Raspberry Pi OS (other)」カテゴリを開くと、公式OSの別エディションが並んでいます。例えばGUIを含まない軽量版のLite版(32-bit Liteおよび64-bit Lite)や、デスクトップ環境込みだが推奨ソフトウェアを省いた「Raspberry Pi OS (Lite Desktop)」版などが見つかります。また、過去の旧安定版(レガシー版)もこの中に含まれている場合があります。Imager上でこれらを選択すると、それぞれ対応する最新のイメージがダウンロードされます。
各エディションの特徴を簡単に押さえておくと、フル版(デスクトップ版)はGUI環境と各種ユーティリティがプリインストールされており、初心者や一般的デスクトップ利用に適しています。Lite版はCUIのみで動作するため、サーバ用途やリソース節約したい場合に向いています。64-bit版は4GB以上のRAMを有するモデル(Pi 4やPi 400など)で恩恵があり、より重い処理や将来的な互換性を重視する場合に選択されます。ただし、一部のソフトウェアは未だ32-bit環境を前提としていたりするため、特殊な要件がなければ標準の32-bit版でも十分です。
ImagerでRaspberry Pi OSを選択すると、自動的にその最新版イメージをダウンロードします。例えば2022年に64-bit版OSが公式リリースされた際も、Imagerはすぐにそれに対応し、64-bit各版の選択が可能になりました。複雑なことを考えず、単に希望するエディションをクリックするだけでよい点はImagerの便利さと言えます。
他の汎用Linuxディストリビューション (Ubuntuなど)をImagerで選択する手順と留意点の詳細解説
Raspberry Pi OS以外にも、Imagerは様々な汎用Linuxディストリビューションをサポートしています。その代表例がUbuntuです。ImagerのOS一覧には「Ubuntu」カテゴリがあり、ここをクリックするとCanonical社提供のUbuntuイメージが現れます。典型的にはUbuntu Server版(GUI無し)やUbuntu Desktop版(GUI有り)が選択肢として表示されます。Raspberry Pi向けのUbuntuは公式に最適化されており、Imager経由でインストールすれば最新のリリース(例えばUbuntu 22.04 LTSや22.10など)が自動的に書き込まれます。
Ubuntuを選択する際の留意点として、Raspberry Piのモデルによってどのイメージが動作するか確認することが挙げられます。ImagerのUbuntu項目は、基本的にARM64アーキテクチャ用が提供されており、Pi 3以降(64-bit対応のSoC)での使用が前提です。32-bit Pi(Pi Zeroなど旧モデル)の場合はUbuntuは公式サポート外となるため、そうした場合はRaspberry Pi OSなど別のOSを選ぶ必要があります。
ImagerではUbuntu以外にも、FedoraやKali Linux、Arch Linuxなどの汎用ディストロが「Other general-purpose OS」や「Specialist OS」カテゴリに含まれている場合があります。例えばKali Linux(セキュリティテスト向けOS)や、Manjaroなども提供されています。これらを選択する際も操作自体はクリックするだけですが、利用目的に応じて適切なものを選ぶようにしましょう。特にUbuntu以外のディストロは、一部公式サポートが限定的だったりコミュニティビルドだったりするケースもあるため、初回起動時に多少の追加設定が必要になる可能性があります。
総じて、Imagerの汎用OSカテゴリはRaspberry Piを小型Linuxマシンとして活用したい開発者にとって有用な選択肢を提供します。サーバを構築したり特定のLinux環境を試したい場合、ImagerからUbuntu等を選ぶことで、PCと同様のOSをラズパイ上で簡単に展開できます。
メディアセンター向けOS (LibreELEC)とレトロゲーム向けOS (RetroPieなど) のImagerでの選択手順と特徴
Raspberry Piはメディア再生やレトロゲーム機エミュレーションなど、娯楽用途にも活用されています。Raspberry Pi Imagerはそうしたニーズに応えるOSもリストアップしています。まずメディアセンター向けOSとして代表的なのがLibreELECです。LibreELECはKodiというメディアセンターソフトを組み込んだ軽量Linuxで、ラズパイをホームシアターPCのように使えます。Imagerでは「LibreELEC」を選択するだけで、その最新版イメージが書き込まれます。初回起動後はすぐにテレビなどに接続してKodiのセットアップが可能です。
レトロゲーム向けOSとしては、RetroPieが有名です。ImagerのOS一覧に「RetroPie」が用意されている場合、これを選択して書き込むことで、何百種類ものクラシックゲームコンソールをエミュレートできる環境が構築できます。RetroPieにはEmulationStationという統合フロントエンドがあり、ゲームROMを用意すればゲーム機ライクな操作感で楽しめます。同様に、RecalboxやBatoceraなどRetroPie系統のOSもImagerで提供されていることがあります。
これらメディア・ゲーム系OSの選択手順自体は単純で、Imagerのカテゴリ一覧から該当の名前をクリックするだけです。ただ、使用上の特徴として、LibreELECやRetroPieはそれぞれ専用の設定や使い方があります。LibreELECの場合、ネットワーク経由でファイルを共有したりKodiのアドオンを導入することになりますし、RetroPieの場合はゲームコントローラの初期設定やROMの転送方法を学ぶ必要があります。ImagerはあくまでOSの書き込みを手助けするものなので、これら用途別OSを使用する際は各プロジェクトのドキュメントを参照してセットアップを進めてください。
とはいえ、Raspberry Pi Imagerにより以前より格段に簡単にこうしたOSを試せるようになりました。数クリックでmicroSDカードに書き込み、ラズパイに挿して起動するだけで、それぞれ専門のシステムが立ち上がるのは驚くほど手軽です。メディアプレイヤー端末やゲーム機を自作したいユーザーにとって、Imagerの存在は大きな助けとなるでしょう。
IoTや産業用途など専門向けOS (例: Home Assistantやk3OS) のラインナップとImagerでの各OS選択ポイント
Raspberry Piは個人の趣味だけでなく、産業用途やIoTプロジェクトでも多用されています。そうした分野向けの特殊なOSやプラットフォームも、Raspberry Pi Imagerの中で選択可能となっています。例えばHome Assistantは家庭内IoTデバイスを一元管理するプラットフォームですが、ラズパイ向けに専用OSイメージ(Home Assistant OS)が提供されています。Imagerの「Other specific-purpose OS」カテゴリ等にHome Assistantがリストされている場合、クリックして書き込むだけでラズパイをホームオートメーションハブに変身させられます。
また、産業用途ではUbuntu Core(スナップパッケージベースの組込み向けOS)やBalenaOS、k3OS(Kubernetes組込み向けOS)などが挙げられます。Imagerには必要に応じてこうしたOSも登録されており、選択するだけでSDカードに展開できます。それぞれのOSは一般的なLinuxというよりは専用環境(アプライアンス)に近いので、使用前に公式ドキュメントに目を通し、セットアップ手順や必要なハードウェア構成を確認することが重要です。
Imagerで専門向けOSを選択する際のポイントは、そのOSが自分のRaspberry Piモデルに対応しているか確認することです。例えばHome Assistant OSはラズパイ4向けのイメージとラズパイ3以下向けで分かれていたり、64bitのみサポートの場合があります。また、これらのOSは起動後にブラウザから設定したり、専用の管理ツールを使ったりするものが多いため、初回起動後のネットワーク設定方法なども事前に把握しておくとスムーズです。
Imagerの専門用途OSリストは、利用者から見るとまさに「知る人ぞ知る」ものが揃っている印象です。以前であればGitHubやフォーラムから自力でイメージを探して書き込んでいたようなものが、Imagerで公式に選択できるというのは非常に心強いでしょう。今後も需要に応じて新たなOSがリストに追加される可能性がありますので、プロジェクトに適したOSがないかImager上でチェックしてみると良いかもしれません。
Imagerの“Use custom”機能による任意のOSイメージファイルの書き込み手順と注意点の詳細解説
ImagerにリストされていないOSや、自分でカスタマイズしたOSイメージを書き込みたい場合には、「Use custom」機能が役立ちます。「OSを選ぶ」メニューを開き最下部までスクロールすると、「Use custom (カスタムイメージを使用)」という項目があります。これを選択するとファイル選択画面が現れるので、任意のOSイメージファイル(拡張子が.img、.zip、.isoなど)を指定します。Imagerは指定したファイルをそのままSDカードに書き込みます。
カスタムイメージを使う場合、いくつか注意点があります。まず、選択したファイルが正しい形式であることを確認してください。一般的なディスクイメージであれば問題ありませんが、例えばインストーラISOなど一部のPC用イメージはラズパイでは起動できません。また、zip圧縮されたイメージはImagerが自動で解凍して書き込みますが、7zなど非対応の圧縮形式の場合は事前に解凍が必要です。
次に、信頼できるソースから入手したイメージを使うようにしましょう。Imager公式リスト以外のOSは玉石混交で、中には非公式改造版や古いバージョンも存在します。プロジェクトのGitHubや開発元のサイトから直接ダウンロードしたイメージを使うよう心がけ、第三者サイトからの転用は避けた方が無難です。セキュリティ上も、出所不明なOSは避けるのが賢明です。
Imagerでカスタムイメージを書き込むとき、ファイルサイズによっては進捗バーの動きが分かりにくい場合があります。特に大容量ファイルだと完了まで時間がかかりますが、Imagerウィンドウを閉じずに気長に待ちましょう。Imager v1.8.1以降ではドラッグ&ドロップにも対応し、エクスプローラーから直接ファイルをImager上にドラッグするだけでカスタムイメージがセットされるため、この方法も試してみてください。
最後に、カスタムイメージを書き込んだ後の挙動はイメージ次第であることを念頭に置いてください。公式OSであれば初回起動ウィザードが走るなど統一された体験がありますが、独自イメージでは初回SSHログインの手順や初期設定が異なります。必要なら開発元の手順書を参照してセットアップを続けてください。
以上の点に留意すれば、Use custom機能は非常に強力です。ユーザー自身が作成したバックアップイメージを書き戻す用途や、ベータ版OS、他プロジェクトの試験的イメージを試す際など、活用の幅が広がります。
Raspberry Pi Imagerの詳細設定とカスタマイズ方法(ユーザー名・Wi-Fi・SSH設定など)
詳細設定 (Advanced Options) メニューの表示方法 (ショートカットキー利用) と全設定項目の概要
Raspberry Pi Imagerには、通常の書き込みオプションに加えて詳細設定(Advanced Options)と呼ばれるカスタマイズメニューがあります。これを使うと、書き込むOSの初期設定をあらかじめ指定しておくことが可能です。詳細設定メニューを開くには、Imagerメイン画面で右下の歯車アイコンをクリックします。なお、Imagerのバージョンによっては歯車アイコンが表示されない場合がありますが、その場合はCtrl + Shift + X(macOSではCmd + Shift + X)のショートカットを押すことでウィンドウが表示されます。
Advanced Optionsのウィンドウが開くと、設定項目がいくつか並んでいます。Imager v1.7まではスクロール形式で全項目が一画面に表示されていましたが、v1.8以降は「General」「Services」「Options」等のタブに分かれています。しかし設定できる内容自体は概ね共通です。主な項目は以下のとおりです:
- ホスト名 (Hostname): 初期状態では
raspberrypiとなっているラズパイのネットワーク名を変更できます。ネットワーク上で識別しやすい名前やユニークな名前にすると良いでしょう。 - SSHを有効化 (Enable SSH): チェックを入れると、OS起動時にSSHサーバが有効になります。オプションで「パスワード認証を使う」か「公開鍵認証のみを許可」かを選択可能です。
- ユーザー名とパスワードを設定: ここにチェックを入れると、新しいユーザーを作成できます。デフォルトではユーザー名
pi・パスワードraspberryですが、セキュリティ向上のため自分で異なるユーザー名・強力なパスワードを設定することを推奨します。 - Wi-Fiを設定 (Configure wireless LAN): SSID(ネットワーク名)とパスワードを入力し、Wi-Fi接続国(Wireless LAN country)を選択します。例えば日本のWi-Fiに接続するならSSIDとパスワードを指定し、国は「JP」に設定します。
- ロケール設定 (Set locale settings): タイムゾーンとキーボードレイアウトを設定できます。地域と言語を反映するため、日本の場合タイムゾーンは
Asia/Tokyo、キーボードは一般的なUS配列なら「us」を選びます。 - ブート時動作: (Imager v1.7以前)自動ログインやデスクトップ自動起動、Overscan(画面の余白)設定などが含まれていました。v1.8以降ではこれらはOptionsタブに再編されています。
- 完了後の動作: 書き込み完了時に音を鳴らすか、メディアを自動排出するか、匿名統計を送信するか(Enable telemetry)などのImager自身の動作設定です。
これらすべての設定項目は必要に応じて有効化・入力します。項目横にあるチェックボックスにチェックを入れると入力欄が活性化する仕組みです。すべて設定し終えたら、「保存」(Save) ボタンをクリックして内容を適用します。一度保存した設定は既定ではそのセッション(アプリを閉じるまで)にのみ有効ですが、Imager v1.7から追加された「Always use」オプションを有効にすると、次回以降Imager起動時にも設定が保持されます。複数のSDカードに同じ設定を書き込みたい場合はこの機能を活用すると便利です。
以上がAdvanced Optionsで設定できる項目の概要です。次節以降では、特に重要な項目について個別に詳しく解説します。
SSH接続機能の有効化と公開鍵認証設定の手順(ヘッドレス接続の準備)
ヘッドレス(キーボード・ディスプレイ無し)でRaspberry Piを運用したい場合、SSHを有効化しておくことが不可欠です。Imagerの詳細設定で「SSHを有効化する」にチェックを入れると、書き込まれるOSは初回起動時からSSHサーバが起動した状態になります。これにより、LAN経由で別のPCからターミナル接続が可能になります。
SSHを有効化する際、認証方法として「パスワード認証を使う」か「公開鍵認証のみを許可」のどちらかを選択できます。手軽さを求めるならパスワード認証で問題ありませんが、必ず強力なパスワードを設定してください。公開鍵認証を選ぶ場合、Imager上で公開鍵文字列を入力するフィールドが現れます。ここにあらかじめ生成したSSH公開鍵(id_rsa.pubなどの内容)を貼り付けます。この方法を使うと、ラズパイ起動時にその鍵がauthorized_keysに登録され、パスワードレスで安全にログインできます。Imager 1.8では「Generate keys」ボタンが追加され、ワンクリックで鍵ペアを生成し公開鍵欄にセットすることも可能になりました。
SSH有効化に伴う注意点として、ネットワーク環境の準備があります。ヘッドレスの場合、ラズパイが起動してもディスプレイがないため、正しくネットワークに繋がっているか確認しづらいです。確実にSSH接続するには、後述するWi-Fi設定や有線LAN接続が成功している必要があります。また初回ログイン時には指定したユーザー名・パスワード、もしくは公開鍵に対応する秘密鍵が必要です。パスワードを設定した場合は決して忘れないようにしてください。公開鍵認証の場合、鍵ペアの秘密鍵(id_rsaなど)は厳重に管理しましょう。
ImagerでSSHを有効化して書き込みを行い、ラズパイに挿して起動したら、PC側からssh ユーザー名@ホスト名.local(例: ssh pi@raspberrypi.local)で接続を試みます。ホスト名やmDNSが有効でない環境では、ルーターのDHCPリストからラズパイのIPアドレスを調べてssh pi@192.168.X.Yのように接続してください。正常にログインできればヘッドレス環境の準備は完了です。
新規ユーザー名とパスワードの事前設定(デフォルトユーザー無効化への対応)
Raspberry Pi OSの2022年以降のバージョンでは、セキュリティ向上のためデフォルトユーザー「pi」が最初から存在しない仕様になりました。そのため、初回起動時に手動で新規ユーザーを作成する必要があります。しかしRaspberry Pi Imagerの詳細設定を使えば、OS書き込み時にあらかじめ新しいユーザー名とパスワードを設定しておくことが可能です。
詳細設定の「ユーザー名とパスワードを設定する」にチェックを入れると、入力欄が現れます。ここで任意のユーザー名を指定し、パスワードを入力します。ユーザー名は自由ですが、システムの制約上半角英数字で記載し、先頭は英字、記号類は使用しない方が無難です(例:pi、user1、aliceなど)。パスワードは8文字以上で推測されにくいものを設定しましょう。Soracomブログでは安全なパスワード生成サービス(1Passwordなど)で作ったランダムパスワードを利用することを推奨しています。
これらを設定しておくことで、書き込み後のOSには指定したユーザーアカウントが作成された状態になります。つまり初回ブート時にユーザー作成プロンプトやOSセットアップウィザードのユーザー設定ステップをスキップできるわけです。大量展開時にも全デバイスで共通の管理ユーザーを作ることができて便利です。ただし共通パスワードを使い回すのはセキュリティ上危険なので、デバイスごとにパスワードを変えるか、後から変更することを検討してください。
なお、Imagerでユーザー設定をせずに書き込んだ場合、Raspberry Pi OSはブート時にセットアップウィザードで新規ユーザー作成を促します。対してImagerでユーザーを仕込んだ場合、ウィザード内のそのステップがスキップされるか、そもそもウィザード自体が簡略化されます。これは挙動として正常なので驚かないでください。また、デフォルトユーザーが存在しない分、ssh接続時にもこの新規ユーザー名を使う必要がある点は覚えておきましょう。
Wi-Fi接続情報の埋め込み設定(SSID・パスワード・国設定)
ラズパイを無線LANに繋ぐ場合、Imagerの詳細設定でWi-Fi接続情報を事前にセットアップできます。これはヘッドレス起動時に自動的にWi-Fiに接続させるのに非常に有用です。「Wi-Fiを設定する」にチェックを入れると、SSID(ネットワーク名)、パスワード、Wi-Fiを使用する国(国コード)の3つのフィールドが現れます。
まずSSIDには、ラズパイに接続させたい無線ネットワークの名前を正確に入力します(大文字小文字も区別されます)。次にパスワード欄には対応するWi-Fiパスフレーズを入力します。これも誤りがないよう注意してください。最後にWi-Fiの国コードですが、日本国内のWi-Fiルーターに接続する場合は「JP」を選択します。国コードは電波法に関わる設定で、必ず適切に設定する必要があります。例えばJPを選ぶことで、日本のチャネル(1-14ch)が有効になり、逆に米国(US)だと1-11chのみになるなどの違いがあります。
ImagerでWi-Fi情報を仕込んで書き込むと、起動したラズパイOSは自動的にwpa_supplicant.confを生成し、指定されたSSIDのネットワークへの接続を試みます。これが成功すれば、ディスプレイやキーボード無しでもラズパイがネットワークに現れるので、前節のSSH設定と組み合わせることで完全ヘッドレスセットアップが可能となります。なお、Soracomブログによれば、macOS版Imagerでは現在接続中のWi-Fi情報をキーチェーンから読み込んで自動入力する便利機能も実装されています。「Yes」を押して許可すれば、SSIDとパスワード欄に今Macが使っているWi-Fi情報がそのまま反映されるので、手入力を省けます。
Wi-Fi設定で注意すべき点は、公衆無線LANや認証が特殊なWi-Fiには対応できないことです。たとえば、ブラウザ認証が必要なホテルやカフェのWi-Fiには、自動では繋がりません。Imagerで設定できるのはプレシェアードキー型の一般的なWi-Fiだけです。また、SSIDがステルス(非公開SSID)の場合、Imagerの標準機能では設定が難しいため、書き込み後に手動でwpa_supplicant.confを編集する必要があるかもしれません(Imager v1.7で隠しSSID対応が追加されました)。
これらの設定を済ませたSDカードを使ってラズパイを起動すると、LEDの点滅パターンなどからWi-Fi接続が成功したか判断できます(モデルによりますが、Pi4ではアクティビティLEDが素早く点滅した後落ち着く、などがあります)。無事にネットワークに参加できたら、あとはSSHでログインするなり、LAN内の他サービスにアクセスするなりしてラズパイを活用できます。
ロケール設定およびタイムゾーン・キーボードレイアウトのカスタマイズ手順(初期言語環境の指定)
Imager詳細設定の「ロケール設定をする」では、システムのロケールやキーボード設定を事前に行えます。具体的にはタイムゾーンとキーボードレイアウトの2つを指定可能です。ラズパイを日本で使用する場合、タイムゾーンは「Asia/Tokyo」に設定しましょう。これにより、時計が日本標準時(JST)になります。キーボードレイアウトについては、お使いの物理キーボード配列に合わせます。例えばUS配列キーボードを接続するなら「us」、日本語JIS配列なら「jp」を選択します。Soracomの例では「us」が表示されていることを確認せよとありますが、これは使用中PCの設定に引きずられてusになっているだけなので、自分の環境に応じ変更してください。
ここで注意点として、Imagerのロケール設定項目は現時点で「言語(ロケールそのもの)」の指定までは含んでいないようです。つまり、タイムゾーンとキーボードは設定できますが、システム言語(メッセージを日本語表示にする等)はOS側の初回セットアップで行う必要がある場合があります。Raspberry Pi OSの場合、初回起動時の設定ウィザードで言語を日本語に変更するプロンプトが表示されます(Imagerでユーザー作成まで済ませていると表示されないこともあります)。その際に「日本語」を選択すれば、UIも含め日本語化されます。詳細は後述の「9. Raspberry Pi OSの日本語化・ローカライズの手順」で解説します。
タイムゾーンとキーボードレイアウトを正しく設定しておくことは、地味ですが便利です。タイムゾーン未設定だと、ログのタイムスタンプや時計表示がUTCのままになり困惑することがあります。また、キーボード配列が合っていないと、記号入力(特に@や”など)がずれて入力されてストレスになります。Imagerでこれらを先に合わせておけば、書き込み後にすぐ快適に操作を開始できます。
もしImagerで設定し忘れても、後からraspi-configコマンドやデスクトップの「Raspberry Piの設定」画面から変更可能です。しかし、どうせなら書き込み時に済ませておく方が二度手間にならず効率的でしょう。
その他の詳細オプション設定 (ホスト名・自動ログイン・オーバースキャン解除・サウンド通知・テレメトリ等) の活用方法
Advanced Optionsには上記以外にも細かなオプションがいくつか存在します。ここではそれら「その他」の設定について補足します。
まずホスト名設定について。Imagerではホスト名を自由に変更できますが、特に複数のラズパイを同一ネットワークに接続する際には、衝突を避けるために個別のホスト名を与えるのが望ましいです。例えばraspberrypiのまま複数台を起動するとmDNS名が重複してしまうため、pi-kitchen、pi-livingのように役割に応じた名前にすると管理しやすくなります。Imagerでホスト名を設定すると、OSの/etc/hostnameおよび/etc/hostsが書き換えられ、初回からその名前で動作します。
自動ログインと自動起動オプションについて。これはRaspberry Pi OS(デスクトップ版)の場合に有効な設定で、GUIへの自動ログイン(毎回パスワード入力なしでユーザーがログイン状態になる)や、起動ターゲットをDesktopではなくConsole(CLI)にするか等の選択が可能でした。Imager 1.6ではこれらをチェックボックスで設定でき、例えばキオスク端末を作る際に自動ログイン&専用アプリ自動起動などの構成を容易にしていました。Imager 1.7以降ではRaspberry Pi OS側の初回セットアップ仕様変更に伴い、この自動ログイン設定(初回セットアップのスキップ)は削除されています。そのため現在は細かい自動ログイン制御はImager上でなく、OS起動後に手動設定(raspi-config等でのBoot Options設定)する形になります。
Overscanの無効化も以前はImagerで設定可能でした。Overscanとはディスプレイの四辺に余白(黒枠)が出る現象で、古いテレビ等で生じます。Imager経由で「Overscanを無効にする」にチェックすると、disable_overscan=1がconfigファイルに書き込まれ、表示領域がフルに使われます。こちらもImager 1.7.2でオプションから外されたようですが、必要なら手動で/boot/config.txtを編集することで同様の効果が得られます。
最後に、完了時のサウンド通知・メディア排出・テレメトリ設定についてです。これらはImagerアプリ自体の動作に関するオプションで、詳細設定画面の下部にあります。サウンド通知は書き込みタスク終了時にPCからピッという音で知らせてくれる機能で、複数カードを連続で作業しているときに便利です。メディア排出は書き込み完了後に自動的にSDカードを安全にアンマウントする機能で、ユーザーはそのままカードを抜くだけで次のカードを入れられます。テレメトリは前述したように匿名利用データの送信です。Imager開発チームにフィードバックを送る目的で、書き込んだOS種別やImagerバージョン等が送信されます。オフにしておけば送信されませんので、気になる場合はチェックを外しておきましょう。
このように、Advanced Optionsの「その他」設定は細かいニーズに応えるもので、一見地味ですが場合によっては役立ちます。Imagerはバージョンアップでこれら設定項目が増減していますので、最新バージョンのImagerを使用しつつ、必要なオプションが提供されているか確認すると良いでしょう。
Raspberry Pi Imagerのバージョンアップ情報 – 最新機能と更新内容を徹底解説します
Raspberry Pi Imagerのリリース履歴とバージョンアップの重要性 (機能強化の歩み)
Raspberry Pi Imagerは2020年に初版が公開されて以来、継続的にアップデートが行われてきました。新機能の追加や使い勝手の改善、バグ修正など、バージョンを重ねるごとに進化しています。主要なリリースの履歴を追いながら、その重要な変更点を見ていきましょう。
2020年3月頃に最初のRaspberry Pi Imager v1.0がリリースされ、以降1.2、1.3といったマイナーアップデートが続きました。当初は基本的なイメージ書き込み機能のみでしたが、2021年3月に公開されたv1.6が大きな節目となります。v1.6では後述する詳細設定(Advanced Options)メニューが初めて搭載され、ユーザーはイメージ書き込み時にオプション設定を埋め込めるようになりました。またUIや操作フローも洗練され、この頃からImagerは“公式推奨ツール”としての完成度を高めていきます。
続いてv1.7は2022年2月にリリースされました。このバージョンでは、Raspberry Pi OSの64-bit正式版公開に合わせてImagerも64-bit OSの全エディションに対応しました。さらに詳細設定項目の強化が図られ、ユーザー名の指定(デフォルトpi以外の任意ユーザー作成)やクラウド向け設定(Ubuntu Server用のcloud-initサポート)、隠しSSIDへの対応、複数行のSSH公開鍵登録などが追加されています。これにより、例えばユーザー名とSSH有効化を別々に設定でき、デフォルトユーザー廃止に伴うニーズに応えました。またUI面では詳細設定ボタンが、選択中OSがその機能をサポートする場合にのみ表示されるよう変更されています。これは、例えば汎用Linuxイメージには適用不要な設定をユーザーが混乱しないよう隠すための工夫です。
v1.7でもう一つ注目なのがテレメトリオプションの導入です。Imager v1.7から、ユーザーが許可すれば使用状況データを匿名送信する機能が入りました。送信されるのは書き込んだOS名やカテゴリ、ホストPCのOS種別やImagerのバージョン、ラズパイの型番(書き込み中に接続されている場合)などです。これらはImagerの改善に役立てられる情報であり、ユーザー数の多いOSの把握などに用いられています。このテレメトリは詳細設定でオプトイン(明示的許可)制になっているので、プライバシーが気になる場合は送信無効のままで問題ありません。
さらにv1.7ではZstandard圧縮形式への対応や、OSリストのワードラップ対応、サブカテゴリ階層表示のサポートなど、細部の改良が加えられています。Linux版では特定ディストリビューションでの自動マウント処理改善やエラー処理強化など、いくつかの不具合修正も含まれました。v1.7.1〜1.7.5にかけてはバグフィックスと小機能追加のマイナーリリースが行われ、特に1.7.1では保存済みWi-Fi設定が機能しない不具合が即座に修正されました。このようにv1.7系統はImager成熟の一つの到達点で、機能豊富かつ安定したバージョンとなりました。
Ver 1.6: Advanced Optionsメニュー初搭載による事前設定機能の実現 (2021年)
先に触れたように、バージョン1.6(2021年3月リリース)はImagerの機能性を飛躍させた重要なアップデートでした。それまでイメージ書き込み専用だったImagerに、隠しコマンドから呼び出す形でAdvanced Optionsメニューが実装されたのです。CTRL+SHIFT+Xを押すと出現するこの秘密の設定画面は、当時大きな話題を呼びました。
v1.6のAdvanced Optionsでは、SSHやWi-Fi、ロケール設定、Overscan設定など基本的な事前設定項目が網羅されました。特筆すべきは、これによりユーザーが手動でsshファイルを作成したりwpa_supplicant.confを書き込む必要がほぼ無くなったことです。Imager上でチェックを入れるだけで同等の効果が得られるようになり、ヘッドレスセットアップが格段に容易になりました。Tom’s Hardwareの記事でも「Experienced Pi users can now quickly and easily set these settings and then write the OS, rather than tweak config files」という趣旨で歓迎されています。
また、v1.6ではUIの改善も行われ、例えば選択可能なOSのラインナップに「Misc utility images」(ブートローダ更新やSDカード消去用イメージ)カテゴリが追加されました。この時期、公式ブログ等でもImager v1.6の新機能紹介がなされ、ユーザベースが一気に拡大した印象があります。実際、Imager以前はbalenaEtcherなどサードパーティ製ツールを使う人も多かったのですが、v1.6以降は公式Imagerに乗り換えるユーザーが増えたようです。それだけインパクトの大きいアップデートだったと言えるでしょう。
Ver 1.7: UI改善とデフォルトユーザー廃止対応などの主な変更点 (2022年)
バージョン1.7(2022年2月リリース)は、Raspberry Pi OSの環境変化に対応するためのアップデートと言えます。最大のトピックは、前述のようにRaspberry Pi OS 64-bit正式版への対応です。Imager v1.7では64-bit版OSの各種エディションが公式リストで選択可能になり、加えてUbuntu等他の64-bitイメージも更新されました。32-bit版が引き続き推奨とされつつも、ユーザーに幅広い選択肢を提供した形です。
機能面では詳細設定(Advanced Options)のさらなる強化が図られました。Raspberry Pi OSでデフォルトユーザーが廃止された流れを受け、Imager側でもカスタムユーザー作成に正式対応しました。具体的には「Username」フィールドが追加され、SSH有効化とは独立してユーザー名・パスワードを設定できるようになりました(v1.6以前はSSHを有効にするとpi/raspberryまたは公開鍵のみという前提だった)。これにより、ユーザーが自分で設定した名前の管理者アカウントを初回起動から使えるようになりました。
また、隠れSSID対応もv1.7のポイントです。従来はSSIDブロードキャストしていないWi-FiにはImager設定が対応できませんでしたが、v1.7ではcloud-init形式のネットワーク設定などのサポートを通じて、Ubuntu Server用のクラウド設定やステルスSSID指定が可能になりました。さらにSSH公開鍵認証も複数行(複数鍵)に対応し、一度に複数の鍵を登録できる柔軟性が加わりました。
Imager v1.7ではUI上の小変更もありました。Advanced Optionsの歯車ボタンは、選択したOSがその機能をサポートする場合のみ表示されるようになりました。例えばRaspberry Pi OSなど一部の公式イメージでは詳細設定に対応していますが、他の汎用OSでは無意味なのでボタンが出ない、という挙動です。これは一般ユーザーの混乱を避ける良い改善と言えます。加えて、各言語翻訳の更新(スロベニア語追加など)、Imagerアイコンのリフレッシュ、Linux固有のバグ修正など、細かなチューニングも行われています。
もう一つの重要な変更はテレメトリ(匿名利用統計)の導入です。v1.7からImagerはオプトインで動作情報を収集するようになりました。これに対し、一部のユーザーからプライバシー懸念の声もありましたが、送信内容は匿名化され個人を特定するものではない旨が明言されています。いずれにせよユーザーの許可無しには送られませんし、統計送信自体もAdvanced Optionsで無効化できます。
総じてv1.7は、Raspberry Piエコシステムの変化に追従しつつ、Imagerをより洗練させたアップデートでした。クラウド環境やセキュリティへの対応などプロユースを強く意識した内容となっており、Imagerが趣味の域を超えて現場でも使われ始めた時期とも重なります。
Ver 1.8: モデル選択画面・タブ式設定UI導入など最新機能の追加 (2023年)
バージョン1.8系(2022年末〜2023年にかけてのリリース)は、Imagerに大幅なUI変更と新機能をもたらしました。まず注目すべきはデバイスモデル選択画面の導入です。Imager v1.8.3では起動直後に「どのモデルのRaspberry Pi向けにOSを書き込みますか?」と尋ねるホーム画面が新設されました。これによって、ユーザーが自分のRaspberry Piモデル(Pi 4、Pi 3、Pi 400、Compute Moduleなど)を選ぶと、そのモデルで動作保証されたOSのみがOS一覧に表示されるようになりました。これは誤って非対応のOSをフラッシュするミスを防ぐ効果があり、初心者に優しい機能と言えます。もちろん上級者向けには「No filtering(フィルタ無し)」オプションも用意され、全OS一覧を見ることも可能です。
次に、Advanced OptionsのUI刷新があります。v1.8.0では歯車アイコンが廃止され、代わりにOS選択・ストレージ指定の後に「Next」を押すと表示されるOS Customization画面に変わりました。設定項目は「General」「Services」「Options」の3つのタブに整理され、一つの長大なスクロール画面だった旧UIより操作しやすくなりました。例えばGeneralタブにはホスト名やユーザー名・ロケール設定、ServicesタブにはSSHや公開鍵、OptionsタブにはImager自身の動作オプションが配置されています。このタブ化によって設定項目間を行き来しやすくなり、また画面上の情報密度も下がって見通しが良くなりました。
機能追加としては、SSH鍵ペアの自動生成ボタンが挙げられます。v1.8のServicesタブに「Generate keys」ボタンが設けられ、これを押すだけでImagerが裏でssh-keygenを実行し新しい鍵ペアを生成、その公開鍵をフィールドに挿入してくれます。今まではユーザー自身がOpenSSHで鍵を作ってコピペする必要がありましたが、この自動化で手順が簡略化されました。
書き込みプロセス面でも改善がありました。v1.8.1では、プログレスバーの精度向上が図られています。具体的には.xz圧縮ファイルのメタ情報から非圧縮サイズを予測し、進捗%をより正確に表示できるようになりました。また、書き込み完了時にサウンドを鳴らす機能がオンの場合は効果音で通知するようになり、画面を凝視していなくても終わりが分かるよう配慮されています。
その他の改良として、ドラッグ&ドロップでのイメージ選択が正式にサポートされました。これにより、ユーザーはエクスプローラーからImagerウィンドウへイメージファイルを放り込むだけでUse customを使えます。また多言語対応の拡充も行われ、スペイン語やウクライナ語などが新たに追加されました。日本語もこの頃UI翻訳が更新され、メニュー表記などが改善されています(完全ではないものの、多くが日本語化されました)。加えて、キーボードナビゲーションの改善(タブキーでフォーカスが当たらなくなる問題の修正など)や、Raspberry Pi 5への公式対応、Arch Linux環境でのカードリーダ認識改善など、多岐にわたるアップデートが報告されています。
v1.8系のアップデートは、UI/UX向上と新ハード対応がメインでした。特にPi 5が登場した2023年には、そのサポートを含めたImager v1.8.3がリリースされ、Pi 5ユーザーも引き続きImagerを利用できる状態が整えられました。全体として、v1.8はImagerの完成度をさらに高め、新規ユーザーにも配慮したリリースとなりました。
Ver 1.9: Qt6への移行とAppImage提供など最新バージョンの更新内容 (2024-2025年)
バージョン1.9系(2024年〜2025年にかけてのリリース)は、内部基盤の刷新と配布形態の変更が目立つアップデートです。最大の変更点はImagerのGUIフレームワークがQt5からQt6へ移行したことです。Qt6によりUI全体が微妙にリフレッシュされ、各プラットフォームでよりネイティブな外観や高DPIディスプレイでの表示改善が図られました。また、Qt6対応に伴いImagerのWindowsビルド要件がWindows 10以上になり、macOSは11.0以上(Apple Siliconにもネイティブ対応)といったシステム要件の変更が行われています。
配布形態の変更としては、Linux向けにAppImageが公式提供されるようになりました。従来、LinuxユーザーはDebパッケージかSnapでImagerを入れていましたが、AppImage版Imagerは他のディストロでも簡単に実行できます。これにより、ArchやFedoraなどDeb系以外の環境でも最新版Imagerを利用しやすくなりました。加えて、署名鍵がRaspberry Pi財団からRaspberry Pi Ltdの新鍵に更新され、セキュリティ面でも最新の状態が保たれています。
Imager 1.9では内部実装の大幅な見直しもありました。依存するライブラリ類(libarchiveやcurl、zstd等)が最新バージョンにアップデートされただけでなく、ビルドシステムにおいて依存関係をリポジトリ内に取り込む戦略が取られました。これによりプラットフォーム間の差異が減り、一貫した動作が期待できます。また、macOS版ではUniversalバイナリ(IntelとARM両対応)が提供されるようになり、M1/M2 MacでRosettaを使わずネイティブ動作可能になりました(v1.7まではRosettaが必要な場合があった)。
ユーザー向け機能という点では、v1.9自体は目立つ新機能は少なめです。どちらかというと1.8で出揃った機能群を、内部刷新とともに安定化させたアップデートと言えます。ただし、いくつかのバグ修正や微調整はもちろん含まれており、例えばIssue Trackerで報告されていた「usernameに許可されない文字を入力するとエラーなく無視される問題」の対策や、SDカードデバイスが大量にあるシステムでのタイムアウト修正など、痒い所に手が届く改善が加えられています。
2025年8月現在、最新バージョンは1.9.4がリリースされています。1.9系では機能追加は控えめなものの、Qt6移行による将来への布石が打たれているため、今後のアップデートでまた新たな機能拡張が期待されます。ユーザーとしては、Imagerを最新版に保つことで最新のRaspberry Piハードウェア(Pi 5や今後登場するモデル)やOSへの対応を享受でき、また安心して使い続けられるでしょう。
定期的なバージョンアップのメリットとアップデート方法 (最新機能の活用のために)
以上、主要なバージョンごとの変遺を見てきましたが、最後に定期的にImagerをアップデートしておくメリットを強調します。Raspberry Pi ImagerはRaspberry Pi財団が公式にメンテナンスしており、新しいRaspberry Piボードの登場やRaspberry Pi OSの更新に追随して適宜アップデートがリリースされます。従って、常に最新バージョンを使うことで、最新ハード・ソフトに対する互換性問題や不具合に遭遇しにくくなります。例えばPi 5発売時にImagerを更新していなかった場合、古いImagerではPi 5固有のブートローダ書き換えが反映されておらず正常に起動メディアが作れない、といったことが起こり得ます。
Imager自体のアップデート方法は、環境によって異なります。Windows/macOSでは公式サイトから新しいインストーラ/アプリをダウンロードして上書きインストールすればOKです。バージョン確認はImagerメニュー内の「About」等で行えます。Linux(Debian系)ではsudo apt update && sudo apt upgrade rpi-imagerで最新に更新できます。Snap版はsnap refresh rpi-imager、Flatpak版がもしあればflatpak updateとなります。GitHubのReleasesページでは変更履歴(Changelog)も公開されているので、新機能や修正内容をそこで確認することもできます。
Imagerのバージョンアップに伴ってユーザーインターフェースが変わったり設定項目が増減することがありますが、本ガイドで紹介したように概ね改善方向の変更です。新しい機能は積極的に取り入れて、より便利に活用してみてください。公式ツールであるImagerを活用することで、ラズパイのセットアップ作業はこれからもますます効率化されていくでしょう。
Raspberry Pi本体へのセットアップと初期起動手順 – SDカード挿入から初期設定までの解説
作成したmicroSDカードをRaspberry Pi本体に挿入する方法と周辺機器の接続準備
Raspberry Pi ImagerでOSを書き込んだmicroSDカードの準備が整ったら、次はいよいよRaspberry Pi本体でのセットアップです。まずは電源を入れる前に、Raspberry Piに必要な周辺機器をすべて接続します。一般的なセットアップでは、HDMIケーブルでモニターまたはテレビと接続し、USBポートにキーボードとマウスを接続します。インターネットに有線接続する場合はLANケーブルも挿します(Wi-Fiを使う場合は後で設定するのでこの時点では不要です)。
周辺機器の準備ができたら、先ほど書き込んだmicroSDカードをRaspberry Piのカードスロットに挿入します。microSDカードスロットの場所はモデルによって異なりますが、ラズパイ4やPi3 B+では基板裏面にスプリング式のスロットがあります。カードの金属端子面を下に向け、ゆっくりと押し込んでください。正しく挿入されると「カチッ」と軽い手応えがあり、カードが固定されます(旧モデルの摩擦式スロットではカチッとは言いませんが、抜け落ちない程度に押し込めばOKです)。
microSDカードを挿入し終えたら、ラズパイ本体上の全ての接続を再確認します。ディスプレイが正しい入力に切り替わっているか、キーボード・マウスはしっかり差さっているか、LANケーブルはルーターと繋がっているか、といった点です。特にRaspberry Pi 4にはHDMIポートが2つありますが、初期起動時は左側(HDMI0)のみがブート画面を表示することに注意してください。右側(HDMI1)に接続すると起動画面が映らず戸惑うことがあります。
Raspberry Piの接続 (電源・周辺機器) と初回起動準備 (ディスプレイ/キーボードなどの接続)
すべてのケーブルとSDカードの準備が整ったら、電源の接続に移ります。Raspberry PiのMicroUSB(Pi3以前)またはUSB-C(Pi4以降)電源ポートに、適切な電源アダプタを接続してください。推奨される電源容量はモデルにより異なりますが、Pi4では5V/3A程度、Pi3では5V/2.5A程度です。電源供給が不安定だと起動途中でリブートしたり、不定動作の原因となります。
電源ケーブルをつなぐと、Raspberry Piは自動的に起動を開始します。電源投入時には基板上のLEDが点灯します。モデルBの場合、赤いPWR LEDが常時点灯し、緑色のACT(アクセス)LEDがSDカードアクセスに合わせて点滅します。初回起動では緑LEDが断続的に激しく点滅し、ブートローダがOSを読み込む様子が見て取れるでしょう。ディスプレイを接続している場合、HDMI経由でブートメッセージやロゴが表示され始めます。
ここで、もし電源を入れても何も表示されない・LEDも付かない場合は、配線やSDカードの挿入を再度確認してください。赤LEDが点かない場合は電源供給自体がうまくいっていない可能性があります(ケーブル不良や電源不足)。赤LEDは点くが緑LEDが一度も点滅しない場合、SDカードが読み込めていません。カードの挿し直しやOS書き込みの確認(イメージが壊れていないか)をしてください。
初回ブート時の挙動とセットアップウィザードの概要 (Raspberry Pi OSデスクトップでの設定画面)
Raspberry Pi OS(デスクトップ版)であれば、初回起動時にセットアップウィザード(Welcome to Raspberry Pi画面)が自動で起動します。これはユーザーに地域と言語、パスワード設定、ネットワーク接続、ソフトウェア更新などの初期設定を対話的に行わせるためのものです。画面に従って順に設定を進めましょう。
まず表示されるのは言語とロケールの設定です。言語(Language)、国(Country)、タイムゾーン(Time zone)を選びます。日本で使う場合はLanguageを「Japanese」、Countryを「Japan」、Timezoneを「Tokyo」に設定すると、システムの表示言語が日本語になり、時刻も日本時間になります。キーボードレイアウトも、この段階でJIS配列を使うなら「Japanese」に変更しておくと良いでしょう。
次に、新しいユーザーの作成またはログイン情報の設定画面が現れます(Raspberry Pi OS Bullseye以降ではデフォルトユーザーが無いため)。ここで希望するユーザー名とパスワードを入力し、パスワードの確認入力をします。Imagerで既にユーザーを設定して書き込んでいた場合、このステップは表示されないか、自動でスキップされている可能性があります。その場合は何もせず次に進みます。
続いて画面設定に関する質問が出ることがあります。具体的には「スクリーンが四隅に黒い枠(オーバースキャン)がある場合はチェックを入れてください」という内容です。普通のPCモニターでは不要ですが、古いテレビにHDMI接続していて黒枠が出る場合はここでチェックを入れると改善します。
次にネットワーク接続の設定です。有線LANを挿している場合は自動的にDHCPで接続されているはずなので、Wi-Fi設定はスキップできます。Wi-Fiで繋ぐ場合はSSIDの一覧から自分のネットワークを選び、パスワードを入力して接続します。ImagerでWi-Fi情報を仕込んでいた場合、既に接続済みになっていることもあります。
その後、ソフトウェアのアップデートを行う確認画面が表示されます。インターネットに接続されていれば、ここで「Update」を実行することで最新のパッケージに更新されます。時間に余裕があれば行っておくと良いでしょう。終わったら再起動を促される場合があります。
以上で初期セットアップウィザードは完了です。全体として15分程度で終わるでしょう。ウィザードが終了すると、Raspberry Pi OSのデスクトップ画面(またはLite版ならコマンドライン)が現れます。
初回設定ウィザードでの主要項目 (ロケール/ユーザー設定/アップデート等) の実施
前節でウィザードの流れを追いましたが、ここで特に重要な項目について補足します。まずロケールと言語設定です。日本語表示にする場合、LanguageをJapaneseに変えるとシステムメニューやウィンドウの表記が日本語化されます。ただし完全な日本語表示には追加の言語パック(フォントやIME)が必要な場合があります。ウィザードでは最低限のロケールのみ設定するため、必要に応じて後述の「9. Raspberry Pi OSの日本語化」で説明する追加手順を行ってください。
ユーザー設定では、ユーザー名とパスワードを間違いなく入力しましょう。パスワードのタイポを防ぐため2回入力になっています。このユーザーはラズパイの管理者(sudo権限を持つ)として登録されます。デフォルトでは「pi」ですがBullseye以降は任意名となりました。慣例にとらわれず、セキュリティの観点からは他と被らないユニークな名前にするのも良いでしょう。
アップデートの実行も非常に大切です。出荷時点のイメージから時間が経っていると、セキュリティ更新やバグ修正が多数蓄積されています。初回セットアップの段階でaptアップデート・アップグレードを行うことで、最新の安定状態にしておくことができます。アップデート中は多少時間がかかりますが、一度実行しておけば以降の作業中に予期せぬ不具合に遭遇するリスクが減ります。
アップデート完了後、再起動の案内が出れば従ってください。再起動後は、設定したユーザーで自動ログイン(デスクトップ版の場合)してホーム画面が表示されます。この時点でインターネット接続が有効なら、ブラウザを開いてウェブ閲覧したり、ターミナルを使って各種コマンドを実行したりと、自由に使い始められます。
ヘッドレス環境での初期セットアップ手順(SSHログインやPi Finderの利用方法)
ディスプレイやキーボードを用意できない、あるいは物理的に接続しない前提でRaspberry Piをセットアップするケースも多々あります。これをヘッドレスセットアップと呼びます。ヘッドレスの場合でも、Imagerで事前にSSH有効化やWi-Fi設定を済ませていれば、ラズパイ起動後すぐにネットワーク経由でアクセス可能です。ここではヘッドレス時の初期設定ポイントを解説します。
まず、Imager詳細設定でSSHとWi-Fiを有効にしたSDカードを挿入してラズパイを起動します。接続は有線でもWi-Fiでも構いません。ラズパイが起動して1〜2分ほど待った後、別のPC(同じLAN内)からSSHクライアントで接続を試みます。WindowsならPuTTYやWindows Terminal、macOS/Linuxならターミナルからssh ユーザー名@ホスト名で接続します。ホスト名はデフォルトraspberrypi.localですが、Imagerで変えていればその名前、もしくはIPアドレスを使います。無事ログインプロンプトが表示され、パスワードを入力して入れれば成功です。
SSHで入った後、対話式の初期設定ウィザード(raspi-config CLI版)が自動で起動する場合があります。Bullseye以降はSSH経由初回ログイン時にユーザー作成を要求されることもありましたが、Imagerで既にユーザーがある場合はスキップされます。もしraspi-configが起動しない場合は自分でsudo raspi-configを実行し、そこでロケールやタイムゾーン設定、パスワード変更等を行っても良いでしょう。ヘッドレスだとGUIのウィザードが使えないため、このraspi-configツールが初期設定に役立ちます(raspi-configはテキストベースですがメニュー形式で操作できます)。
また、ラズパイがネットワーク上に見つからない場合に便利な方法として、Pi Finder系ツールの利用があります。Raspberry Pi公式の「Pi Finder」は現在メンテされていませんが、第三者製で同様の機能を持つアプリ(例えばAdvanced IP ScannerやFingなど)が役立ちます。ネットワーク内のraspberrypiというホストを探し出し、IPを表示してくれるので、それを元にSSH接続できます。
ヘッドレス運用では初期セットアップが完了した後もSSHで操作することになるため、sudo apt update && sudo apt upgradeでアップデートするなどの作業もすべてコマンドラインで行います。必要に応じて、sudo raspi-configでインターフェイスオプションからVNCを有効にし、RealVNC Viewerでリモートデスクトップ接続することも可能です。これにより、画面無しでもデスクトップ環境を操作できます。
総じて、Imagerのおかげでヘッドレスセットアップは以前に比べ飛躍的に簡単になりました。適切に準備すれば、ラズパイ本体に触れるのはSDカードを挿して電源を入れるだけで済み、あとの設定は全て遠隔から行えるのです。
初回起動時のトラブルシューティング (起動しない・画面が出ない場合の対処)
最後に、Raspberry Pi初回起動時によくあるトラブルとその対処法をQ&A形式でまとめます。
- 電源を入れても全く起動しない: 赤LEDが点灯しない場合は電源アダプタやケーブルの問題です。十分な電流容量のある公式推奨電源を使ってください。赤LEDは点くが緑LEDが瞬きしない場合、SDカードが読み込めていません。カードの挿入状態を確認し、別のカードリーダーでPCから中身が見えるか検証しましょう。またOSイメージが正しく書き込まれていない可能性もあるので、Imagerでもう一度書き込み直しを試みます。
- ブートエラーの虹画面やLEDエラーパターンが出る: 画面にカラフルな四角(レインボースクリーン)のまま進まない場合、ブートローダがOSを見つけられていない可能性があります。緑LEDの点滅パターン(例えば4回点滅の繰り返しは
start.elfが無い、など)を確認し、Raspberry Pi公式ドキュメントのエラーコードに照らし合わせます。対処としては正しいOSを書き込む、カード相性を疑って別メーカー品を試す、ブートローダ自体のリカバリ(EEPROM書き換え)を行う、等があります。 - HDMIに何も映らない: 電源投入後もモニターが真っ暗な場合、まず接続ポートを確認します。Pi 4なら左のHDMI0を使用してください。また、ディスプレイ側の入力切替が正しいかも確認します。さらに、稀に解像度の初期設定がモニター非対応だと映らないことがあります。この場合、
boot/config.txtに安全モード(hdmi_safe=1)を有効にしてみるか、別のモニターで設定変更する必要があります。 - キーボードが効かない: USBキーボードが反応しない場合、ポートを変えてみます。また、電源不足だとUSB給電が不安定になりますので、セルフパワーUSBハブ経由にするか電源を見直します。無線キーボードの場合、レシーバの接続や電池もチェックしましょう。
- Wi-Fiに繋がらない: SSIDやパスワードを間違えていないか再確認します。ImagerでWi-Fi設定したが繋がらない場合、国コード設定漏れが原因で無線LANがブロックされている可能性があります。有線LANでログインして
raspi-configからWi-Fi国設定をしてください。また5GHz帯に古いPi(Pi Zero等)は対応していないことも要注意です。 - SSH接続できない: 「ネットワーク経由でホストが見つからない」場合、ラズパイとPCが同じネットワーク内にいるか確認します。Wi-Fi経由だとルーターのクライアント隔離設定により見えないこともあります。IPアドレスを直接指定する、あるいは一時的に有線接続する手もあります。また、ImagerでSSHを有効にし忘れた場合はSDカードのbootパーティションに空の
sshというファイルを作成して再起動するとSSHが有効になります。
以上のような対処を行っても問題が解決しない場合、一度原点に立ち返って手順を確認することも重要です。OSの選択を誤っていないか(例えばPi 2に64-bit OSを書いていないか)、ハードウェアの接続は正しいか、などを総ざらいします。それでも不明な場合は、Raspberry Pi公式フォーラムや各種コミュニティで類似のトラブル事例を検索してみると良いでしょう。
Raspberry Pi OSの日本語化・ローカライズの手順 – 言語設定と表示を日本語にする方法を解説
Raspberry Pi OSを日本語環境にするための基本設定項目 (言語・ロケールの変更)
Raspberry Pi OSを使用する際、日本語環境で使いたい場合は言語と言地域の設定(ロケール設定)を変更する必要があります。Raspberry Pi OS(デスクトップ版)であれば初回起動時のWelcomeウィザードでLanguageとLocationを設定できます。ここでLanguageを「日本語(Japanese)」に、Location(国)を「日本(Japan)」に設定すれば、システムの表示言語が日本語になり、通貨や日付の表示形式なども日本向けにローカライズされます。既にウィザードを終えてしまった場合でも、あとから変更可能です。
ウィザードをスキップした、またはLite版(CLIのみ)を使っている場合には、ターミナルからsudo raspi-configコマンドを用いて設定します。raspi-configのメニューから「Localisation Options」を選び、次に「Locale」を選択します。すると使用可能なロケールの一覧が表示されるので、スクロールしてja_JP.UTF-8(日本語UTF-8)を選びスペースキーでマークします。その後、デフォルトロケールに何を使うか聞かれるのでja_JP.UTF-8を選択してEnterします。これによりシステムロケールが日本語に設定されます。
デスクトップ環境では、GUIで設定することも可能です。メニューから「Raspberry Piの設定」を開き、「ローカライゼーション」タブに移動します。ここでLocale(言語/国)、Timezone(タイムゾーン)、Keyboard(キーボードレイアウト)、WiFi country(無線LAN国)の各ボタンを押して日本向けに設定を変更します。Localeボタンではリストから「ja_JP.UTF-8」を選択、Timezoneでは「Asia/Tokyo」、Keyboardでは「jp(日本語キーボード)」またはUSキーボードを使うなら「us」、WiFi countryは「JP」を選びます。設定を適用するとシステムに反映されます。
初回セットアップ画面で日本語を選択する方法とポイント (インストールウィザード上での設定)
Raspberry Pi OS Desktop版の初回セットアップウィザードでは、最初に言語と言地域を選択する画面が出ます。この画面で日本語化を行うのが最も簡単な方法です。具体的には、Languageドロップダウンから「Japanese」を選び、Countryドロップダウンから「Japan」を選択します。Timezoneも自動的に「Asia/Tokyo」が選ばれるはずです。さらに「Use US keyboard」をオフにして「Japanese keyboard」をオンにすると、キーボード配列も日本語キー配列(JIS)になります(物理的にUSキーボードを使っている場合はここはUSのままで構いません)。
これらを設定して「Next(次へ)」進むと、システムは一旦日本語ロケールに切り替わる処理を行います。その後のウィザード画面表示も日本語になります。例えば「パスワードの設定」や「ソフトウェアの更新」といった表示に変わるでしょう。以降、ユーザーアカウント名などはアルファベット入力となりますが、GUI表記は日本語で案内されるため理解しやすくなります。
初回ウィザードで日本語を選択する際のポイントは、ロケール生成に多少時間がかかる場合があることです。特にSDカードの速度が遅いと、ja_JPロケールを生成する処理で数十秒待たされることがありますが、フリーズではないのでしばらく待ってください。処理が終われば自動的に次の画面に進みます。
一度日本語設定を済ませておけば、その後システム全体が日本語表記で動作するようになります。ただしコマンドラインのメッセージなど一部は英語のままです。また、日本語入力システムのセットアップは別途必要になる点に注意してください(これについては後述します)。
ラズパイ起動後にraspi-configを使ってロケールを日本語に変更する手順 (CLI操作)
Lite版などGUIの無い環境や、ウィザードを飛ばしてしまった場合でも、前述のようにraspi-configツールを使ってロケール設定を変更できます。SSHや直付けのキーボードでラズパイにログインし、以下の手順で行います。
sudo raspi-configを実行。- カーソルキーで「5 Localisation Options」を選択しEnter。
- 「L1 Locale」を選択しEnter。
- ロケール一覧が表示されたら、
ja_JP.UTF-8 UTF-8を探し、スペースキーで選択([*]印を付ける)。 - Tabキーで
- デフォルトロケールの選択画面で
ja_JP.UTF-8を選びEnter。 - 処理が実行され、「Generating locales… ja_JP.UTF-8」等と表示されるので完了まで待つ。
- 完了メッセージが出たら
raspi-configメニューに戻るので、Escキーで終了。 - 念のためシステムを
sudo rebootで再起動。
再起動後、localeコマンドを実行するとLANG=ja_JP.UTF-8などと設定されていることが確認できるはずです。また、dateコマンドで曜日や月の表記が日本語(例えば「月」で始まる)になっていれば成功です。
CLI環境で日本語ロケールを有効にすると、日本語ファイル名の表示や日本語のテキスト処理で文字化けしにくくなる利点があります。ただし、ターミナル上で日本語入力するには別途コンソール用IMEのセットアップが必要となることもあります。基本的にはサーバ運用なら英語のままでも問題ありませんが、必要に応じて設定してください。
デスクトップ環境から日本語設定に変更する方法 (GUIのRaspberry Pi設定での操作)
デスクトップ環境を利用している場合、前述した通りGUIから設定変更が可能です。メニューの「設定」→「Raspberry Piの設定」を開き、「ロケライゼーション」タブに移ります。そこには「ロケール」「タイムゾーン」「キーボード」「Wi-Fi国設定」の各ボタンがあります。
ロケール: ボタンを押すと言語/地域選択ダイアログが表示されるので、言語から「ja 日本語」を、国から「JP 日本」を選択します。文字コードはUTF-8のままでOKです。タイムゾーン: ボタンを押し、「Asia」→「Tokyo」の順に選びます。キーボード: 使用キーボードの種類に合わせて設定します。日本語配列キーボードなら「jp」、英語配列なら「us」あるいはデフォルトのままで構いません。最後にWi-Fi国設定: ボタンで「JP Japan」を選択します。
設定を終えたら「OK」をクリックすると、「設定を反映するため再起動しますか?」といった旨のダイアログが表示されます。再起動を実行すると、新しいロケールがシステム全体に適用されます。再起動後、メニュー表記などが日本語化されていれば成功です。
GUIで設定する利点は、視覚的に選択できるため間違いが少ないことです。一方で、バックグラウンドでは結局raspi-configと同様の処理を行っています。デスクトップ環境が利用できるならばGUI設定が手軽ですが、ターミナルに慣れているならばコマンドで済ませても結果は同じです。
日本語フォントのインストールと日本語入力(IME)を有効にする手順 (日本語入力の準備)
システムを日本語ロケールに設定しても、日本語フォントや日本語入力環境が整っていないと、文字表示や入力面で不便が残ります。そこで必要に応じて以下の追加設定を行います。
フォントのインストール: Raspberry Pi OSには基本的な国際フォント(おそらくNotoなど)が含まれているため、日本語の表示自体は可能な場合が多いです。しかし、より綺麗な日本語表示のためにフォントを追加することもできます。例えばsudo apt install fonts-vlgothicと実行すると、VLゴシックという定番の日本語フォントが導入され、システムで利用されます。同様にfonts-ipafontやfonts-noto-cjkなども人気のフォントパッケージです。大量の漢字も含まれるのでインストールには時間がかかりますが、一度入れておけば豆腐(□)表示になることはほぼ無くなるでしょう。
日本語入力IMEの導入: 日本語の表示だけでなく、キーボードからひらがな・漢字を入力できるようにするにはIME(日本語入力システム)が必要です。Raspberry Pi OS(Debian系)では、Fcitx + MozcやIBus + Mozcの組み合わせがよく使われます。MozcはGoogle日本語入力由来の変換エンジンで精度が高いです。インストール方法は例えばsudo apt install fcitx-mozcのように実行します。併せてデスクトップ環境の設定でFcitxを入力メソッドとして有効にする必要があります。メニューの「設定」→「Fcitx設定」などからMozcが有効になっているか確認し、キーボードの半角/全角キーやトグルキーで日本語入力モードに切り替えられることを確認します。
Lite版のようにGUIが無い場合はIMEは不要ですが、コンソールで日本語入力したい場合は特殊ですのでここでは割愛します。
日本語フォントとIMEの設定が完了すれば、ブラウザで日本語のWebページを閲覧しても文字化けせず表示され、LibreOfficeなどでも日本語文書が正しく扱えるようになります。さらにターミナルでファイル名に日本語を使用しても問題なく表示でき、SSH越しでもUTF-8でやり取りできるでしょう。これで真の意味でRaspberry Pi OSが日本語化・ローカライズされたと言えます。
日付・時間・キーボード配列など日本向けに設定すべきその他の項目
最後に、日本語化に関連して設定しておくと良いその他の項目を挙げます。
- 時刻同期の確認: タイムゾーンをTokyoに設定しても、システムクロックが正しく同期していなければ時刻がずれることがあります。通常Raspberry Pi OSはインターネット経由でNTP(時刻同期)を行いますが、LAN隔離環境では
sudo timedatectl set-ntp trueで有効化されているか確認してください。 - キーボードの英数・かな切替: 日本語キーボードの場合、半角/全角キーでIMEのON/OFFを切り替える設定にすることが多いです。Fcitxでは設定で「Mozc」を選び、Keybindingsで「半角全角でトグル」等を指定できます。慣れた挙動に合わせましょう。
- ターミナルの文字コード: 通常UTF-8で問題ありませんが、まれにシリアルコンソール等でShift_JISを扱う必要がある場合は注意が必要です。その際は環境変数LANG等を一時的に変更するかiconvで変換します。
- ソフトウェアロケール: アプリケーションによっては別途言語設定が必要な場合があります。例えばLibreOfficeを日本語UIにするには
libreoffice-l10n-jaパッケージを入れる、Manpagesを日本語化するにはmanpages-jaを入れる等です。 - 表示フォントの調整: 日本語表示でフォントが小さい/見づらい場合、デスクトップの「外観設定」からデフォルトフォントをVLゴシックなどに変更することもできます。見た目の好みに合わせて微調整してください。
以上の設定を行うことで、ラズパイ上での日本語利用体験は快適なものになるでしょう。特に日本語入力ができるようになると、ラズパイを使った日記作成やプログラミングコメントの記述などもスムーズに行えます。ラズパイはグローバルに使われていますが、このように日本語環境も公式にサポートされているので、安心して日本語で活用してください。
Raspberry Pi ImagerとRaspberry Pi本体のトラブルシューティングとよくある質問(FAQ集)
Raspberry Pi ImagerでSDカードが認識されない・表示されない場合の対処法
まず、Raspberry Pi Imagerを使用していてSDカードが一覧に表示されない、認識されない場合の対処方法です。この問題は複数の原因が考えられます。
一つ目は、SDカードリーダーやUSBポートの問題です。別のUSBポートに挿してみたり、他のカードリーダーを試してみてください。特にノートPC内蔵のSDカードスロットはLinux環境等で認識されにくい場合があります。その際はUSBカードリーダーを使用するとうまくいくことがあります。二つ目は、Imagerの権限の問題です。WindowsではImager起動時に管理者権限が必要になる場合があります(実際には書き込み開始時にUACプロンプトが出る)。もし何らかの理由で権限不足だとドライブリストを取得できないこともありえます。Imagerを右クリックして「管理者として実行」してみてください。
Linux環境の場合、Snap版を利用しているとリムーバブルメディアへのアクセスがデフォルトで制限されています。その際はsnap connect rpi-imager:removable-mediaを実行して権限を付与する必要があります。また、一般ユーザーでImagerを起動していてカードデバイスにアクセスできない場合、sudoでImagerを起動する(sudo rpi-imager)ことで認識するケースもあります。ただし、通常はPolkit経由でパスワード入力を促すため、GUI上でのプロンプトが出ていないか注意してみてください。
それでも認識しない場合、SDカード自体の不良の可能性もあります。別のカードやUSBメモリはImagerに表示されるか確認し、特定のカードだけダメならカードの寿命やフォーマット破損が考えられます。その場合はカードの交換を検討しましょう。また、意外な点として、カードに割り当てられたドライブレターが他と競合している場合(Windowsでネットワークドライブと競合等)はディスクの管理から手動でドライブレターを変更することで解決することもあります。
OSイメージ書き込み中のエラーやフリーズへの対処方法 (書込み失敗・フリーズ時の対応)
Imagerで書き込みを実行した際にエラーが発生したり、進捗が途中で止まってしまう場合の対処です。ありがちな原因を順に挙げます。
まずはSDカードの空き容量不足です。指定したイメージがカード容量をわずかに上回っていると、書き込み途中でエラーとなります。8GBカードに8GBイメージでは実容量不足の場合があるので、余裕を持ったカードを使用してください。また、PC側のストレージ容量にも注意が必要です。Imagerは一時ファイルとしてOSイメージをPCにダウンロードします。そのため、PCのCドライブ等に十分な空きがないと途中で失敗することがあります。特にWindowsの一時フォルダに数GBの空きが無いとダウンロードフェーズでエラーになることがあります。ディスククリーンアップを行い、空きを確保して再実行してください。
次に多いのが、SDカードの品質や寿命に起因するエラーです。低品質なカードや過去に酷使したカードだと、特定セクタへの書き込みで固まるケースがあります。別の新しいカードで試して改善するなら、カード不良の可能性大です。Imagerのログ出力(GUIには直接出ませんが、Windowsならイベントビューア、Linuxならターミナル出力でエラーコードが見えることがあります)にI/Oエラーが出ていたらカード交換を検討しましょう。
また、アンチウイルスソフトウェアが書き込み動作を妨害している場合も考えられます。リアルタイムスキャンが有効だと、大量の書き込みをチェックする過程でImagerの動作が極端に遅くなったり、失敗したりします。一時的にウイルス対策ソフトを無効化して再度試すのも手です。
Imager自体の不具合の可能性もゼロではありません。過去にはImager v1.6で一部環境において書き込み終了後にクラッシュするバグが報告されましたが、その場合は最新版への更新で改善するでしょう。もしImagerがどうしても機能しない場合、代替手段としてbalenaEtcherなど他の書き込みツールを利用する選択肢もあります。ただしImager専用の機能(詳細設定など)は使えませんので、問題切り分け目的で試す程度に留めると良いでしょう。
焼き込み完了後にRaspberry Piが起動しない場合のチェックポイント (OSイメージ・接続の確認)
ImagerでSDカードの作成は成功したように見えるのに、Raspberry Piに挿しても起動しないという場合の対処です。このシナリオではまず、正しいOSイメージを書き込んだかどうか確認してください。ラズパイのモデルによっては動作しないOSがあります。特に新しいPi 4/5に旧式のOS(例えばJessieやStretch世代)を書き込んでも起動しません。また、逆に古いPiに64-bit版OSを書いても起動しません。Imagerのモデルフィルタ機能はこれを防いでくれますが、自分でUse custom等で入れた場合は互換性を再確認しましょう。
次に接続周りです。電源供給が十分でないと、ブート途中で電圧低下によりリセットがかかって起動ループになることがあります。赤LEDが点滅したり、画面に虹色の四角が表示された場合は電源不足です。公式電源アダプタを使用するか、より太いUSBケーブルに変えてみてください。また、SDカードスロット周りの接触不良というケースも稀にあります。カードを差し直し、それでもダメなら別のカードスロットを持つラズパイで試すか、カード自体を変えてみます。
起動しない場合でも、LANには繋がっていることがあります。HDMI出力が出なくてもヘッドレスで動いている可能性を疑い、ルーターのDHCPクライアントリストに新しいエントリが無いか確認しましょう。もしIPが振られていれば、SSHで接続できるか試す価値があります。意外とHDMIケーブルやモニター側の不調で映像が出ないだけ、ということもあるからです。
それでも起動しない場合、最終手段として別のOSイメージで切り分けを行います。例えば公式のRaspberry Pi OS(問題が起きているOSとは別のもの)を書き込んでみて、そちらで起動するなら前のOS固有の問題と判断できます。その場合はOSのフォーラムやリリースノートを調べ、必要な追加手順(EEPROMアップデートやconfig.txt修正など)が無いか確認します。
Wi-FiやSSHログインがうまくいかない場合のトラブルシューティング (設定ミスやネットワーク環境の確認)
ImagerでWi-FiやSSHを設定したのに、実際には接続できず困るケースもあります。そのトラブルシューティングです。
Wi-Fi接続失敗: まずSSIDとパスワードが正確か確認します。特にSSIDにスペースや特殊文字が含まれている場合、Imagerの設定でエスケープが必要なことはありませんが、打ち間違いには注意です。Wi-Fiが有効にならない場合、多くは国コード設定漏れが原因です。Imagerで国(Regulatory Domain)を設定しなかった場合、Raspberry Pi OSはWi-Fiインターフェースを無効化します。SSHで有線経由ログインできるならraspi-configから無線LANの国コードを設定し直してください。また2.4GHz帯と5GHz帯の違いにも注意しましょう。古いPiは5GHz非対応、Pi 3B+以降は5GHz対応ですが電波の届きにくさなど物理要因も考えられます。
SSH接続不可: 「接続が拒否されました」「タイムアウトしました」等のエラーなら、SSHサービスが起動していない可能性があります。ImagerでSSHを有効にしたはずでも、選択したOSがAdvanced Options非対応だった場合(例えば他のLinuxディストロ)設定が効いていないことがあります。その際はSDカードのbootパーティションに空ファイルsshを作成してから再起動してみてください。接続自体はできるのにログインできない場合、ユーザー名/パスワードを間違えているか、Imagerでユーザーを設定したのに別の名前で入ろうとしていないか確認します。また、ufwなどファイアウォール設定をイメージが持っている場合もあり得ます。そのOSのドキュメントを確認し、標準でSSHポートがブロックされていないか調べます。
ネットワーク関連: 無線/有線に関わらず、ラズパイがネットワークに現れない場合、ネットワーク構成の問題の可能性があります。企業ネットワークや大学ネットワークではMACアドレス登録制限があったり、ゲストWi-Fiでは隔離されていて同一LAN内でもmDNSが通らないケースがあります。その場合はDHCPサーバのリース一覧からIPを特定し直接アクセス、またはネットワーク管理者に相談が必要です。
これらの問題は一つ一つ原因を潰すことが重要です。例えばWi-Fiが不安定なら一度LANケーブル接続で試してみる、SSHがダメならキーボードを繋いで直接ログインしてみる、など段階的に確認してください。
Raspberry Pi ImagerおよびRaspberry Piに関するその他のよくある質問集
最後に、Raspberry Pi Imagerとラズパイの利用にまつわる簡単なFAQを紹介します。
Q1: Imagerはインターネット非接続環境で使えますか?
A1: ダウンロード済みのOSイメージがあれば使えます。Imagerのリストから選ぶ方式ではネット接続が必要なので、オフライン環境では事前にイメージファイルを入手し「Use custom」機能で指定してください。
Q2: Imagerで書き込んだSDカードはWindowsから中身が見えませんが大丈夫?
A2: 正常です。Raspberry Pi OSのSDカードは最初に小容量のFAT32ブートパーティション、残りはLinuxのext4パーティションになります。ext4はWindowsでは読めないため、空に見えるだけです。
Q3: Imagerはどこに一時ファイルを保存していますか?
A3: OSによります。Windowsではユーザープロファイルの一時ディレクトリ(%TEMP%)にダウンロードキャッシュします。書き込み完了後自動で削除されます。Linuxでは/tmpに置かれることがあります。
Q4: テレメトリを有効にすると何が送られますか?
A4: 書き込んだOSの名前・カテゴリ、使用したImagerのバージョン、PCのOS種別など匿名化された統計情報です。個人情報やデータ内容は送信されません。
Q5: Imagerの代替となる公式CLIツールはありますか?
A5: 公式にはImagerのCLI版はありません(2025年現在)。ヘッドレス環境ではddコマンドでイメージを書き込む方法や、Ubuntuならubuntu-imageコマンドを使う方法もありますが、Advanced Options相当の機能は手動でスクリプトを書く必要があります。
Q6: SDカードではなくUSBストレージからブートしたいのですが?
A6: Raspberry Pi 3B以降はUSBマスストレージブートが可能です。ImagerでSDカードではなくUSB接続のSSD/HDD/USBメモリを選択してOSを書き込めば、そのデバイスからブートできます。Pi 4/400/CM4では標準で有効、Pi3B/3B+ではブートローダ設定が必要な場合があります。
Q7: Raspberry Piが起動しなくなったがデータを取り出したい。
A7: SDカードを取り出し、別のLinuxマシンに接続すればext4パーティションをマウントできます。Windowsしか無い場合、ext4読み取りソフト(Ext2Fsdなど)を使うか、Raspberry Pi OS上で別メディアにバックアップしておくことをおすすめします。
以上、よくある質問と回答でした。トラブルに遭遇しても慌てず、一つずつ原因を切り分けて対処すれば必ず解決に近づきます。必要に応じて公式フォーラムやコミュニティの知見も活用して、快適なRaspberry Piライフを送りましょう。














