FSx for NetApp ONTAPとは何か?クラウド向けONTAPストレージサービスの概要と仕組み
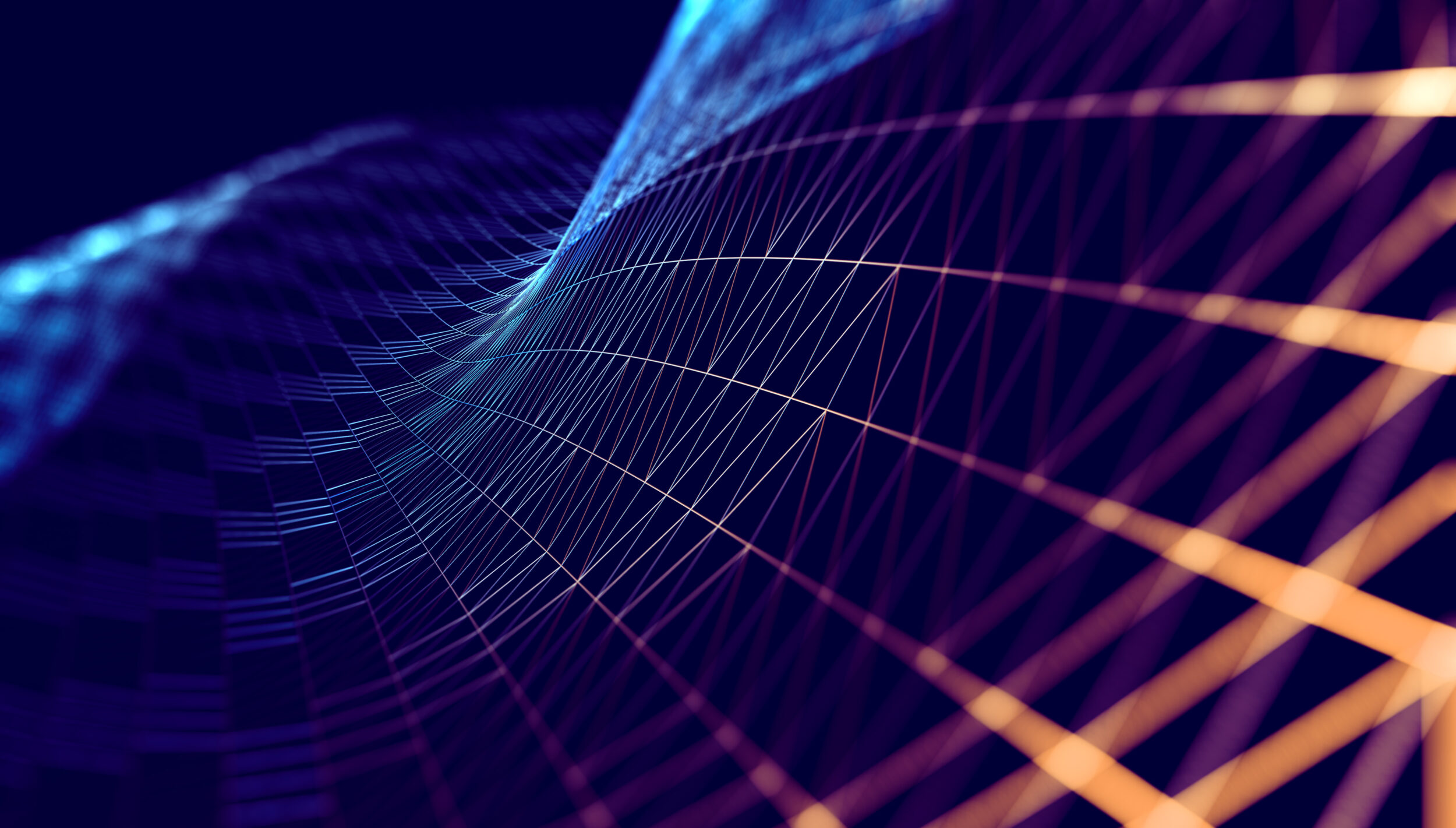
目次
- 1 FSx for NetApp ONTAPとは何か?クラウド向けONTAPストレージサービスの概要と仕組み
- 2 FSx for NetApp ONTAPの主な特徴とメリット:高性能・高可用性なクラウドストレージの利点
- 3 FSx for NetApp ONTAPの導入事例とユースケース:さまざまなシナリオでの活用例
- 4 FSx for NetApp ONTAPのアーキテクチャ概要:ONTAPストレージシステムの構成と仕組み
- 5 FSx for NetApp ONTAPの対応プロトコルと接続性:NFS、SMB、iSCSI、NVMeなど多様なアクセスに対応
- 6 マルチAZ・高可用性構成:可用性99.99%を実現するFSx for NetApp ONTAPの冗長構成
- 7 ストレージ仮想マシン(SVM)とは何か:マルチテナント環境を実現する仮想ストレージ機能の役割と活用方法の解説
- 8 FSx for NetApp ONTAPのデータ管理・運用機能:スナップショットやレプリケーションなど高度な管理機能
- 9 FSx for NetApp ONTAPの料金体系とコスト最適化:容量・性能に応じた課金モデルと節約ポイント
- 10 FSx for NetApp ONTAPの構築・利用の手順:基本設定からデータアクセスまでの流れ
FSx for NetApp ONTAPとは何か?クラウド向けONTAPストレージサービスの概要と仕組み
FSx for NetApp ONTAPは、NetApp社のエンタープライズ向けストレージOS「ONTAP」をAWSクラウド上でフルマネージドサービスとして提供するものです。ユーザーはハードウェア管理やソフトウェア更新を意識することなく、オンプレミス同等の高度なストレージ機能をクラウド上で利用できます。ONTAPは企業のデータ管理で定評のあるファイルシステムであり、そのデータ重複排除やスナップショットなどの機能をそのままAWS上で享受できる点が大きな特徴です。AWSがインフラ運用(ストレージのセットアップ、障害対応、バックアップ管理など)を代行するため、利用者は必要なファイルシステムを作成し、データを保存するだけで高機能な共有ストレージを簡単に利用できます。
FSx for NetApp ONTAPは2021年に発表された比較的新しいサービスで、既存のAmazon FSxファミリー(Windowsファイルサーバ向けやLustre向けなど)の一つとして位置付けられています。本サービスの登場により、長年ONTAPを使用してきた企業はクラウドへの円滑な移行が可能となりました。オンプレミス環境からクラウド環境へデータを移しても、アプリケーションから見たファイルシステムの機能・挙動は変わらないため、移行後も違和感なく運用できます。つまり、「FSx for NetApp ONTAPとは?」に対する答えは、「NetAppのONTAPストレージをAWSクラウドで完全管理型サービスとして利用できるようにしたもの」です。
このサービスにより、企業は自前でONTAPストレージを構築・維持する負担から解放されます。数クリックでペタバイト規模のファイルサーバを構築でき、必要に応じて性能や容量もスケール可能です。また従来ONTAPを扱ったことがないユーザーでも、AWSマネジメントコンソールのGUIやCLIを通じて比較的簡単に高度なストレージ機能を使い始めることができます。
NetApp ONTAPをAWSでフルマネージド提供:エンタープライズ向けストレージサービスの全容
ONTAPはNetApp社が提供する業界屈指のストレージOSで、オンプレミス環境では専用ストレージ装置(FASやAFFシリーズなど)上で稼働し、豊富なデータ管理機能を提供してきました。そのONTAPがAWS上でフルマネージドサービスとして提供されるのがFSx for NetApp ONTAPです。利用者はAWSが用意したONTAP環境を必要なときに作成し、容量や性能を指定して使うだけで済みます。ハードウェアの調達・設置やソフトウェアのインストール、パッチ適用などはすべてAWS側で管理されます。
フルマネージドであることから、ONTAPの高度な機能(スナップショットやレプリケーション、マルチプロトコル対応など)を自社で専門知識を持つ管理者なしに活用できる点がエンタープライズIT部門にとって魅力です。たとえば、これまでNetAppストレージの管理に習熟した人員が必要だったバックアップ設定やボリューム管理も、AWS標準の画面操作やAPIで簡潔に行えます。したがって、FSx for ONTAPはオンプレミス級のストレージ機能とAWSクラウドの利便性を両取りできるサービスと言えます。
オンプレミス同等の高度機能をクラウドで実現:FSx for ONTAPがもたらす利便性
FSx for NetApp ONTAPは、単なるファイル保存領域ではなくエンタープライズ向けの高度機能を備えています。例えばスナップショット機能によりポイントインタイムでのデータ保護ができ、FlexClone(クローン作成)機能で本番データの即時コピーを作成してテストに利用する、といった高度な活用がクラウド上で可能です。さらに、オンプレミスONTAPでお馴染みのSnapMirrorレプリケーションを用いて、他のAWSリージョンやオンプレミスのONTAPシステムとデータ同期を行うことで、ハイブリッドクラウド環境での災害対策(DR)構成も容易に組めます。
また、AWSサービスとの統合も利便性を高めるポイントです。FSx for ONTAPはAWSのIAM(アクセス管理)による権限制御やKMS(キー管理サービス)による暗号化キー管理に対応し、さらにCloudWatchでの監視やCloudTrailでの操作ログ記録など、クラウドネイティブな運用管理も可能です。これらにより、企業はクラウド上でセキュアかつガバナンスの効いた形でONTAPストレージを扱えます。総じてFSx for ONTAPは、ONTAPのパワフルな機能群をクラウドで手軽に活用できるようにし、インフラ担当者の運用負荷軽減とビジネスの迅速化に寄与するサービスだと言えます。
FSx for NetApp ONTAPの主な特徴とメリット:高性能・高可用性なクラウドストレージの利点
FSx for NetApp ONTAPには、エンタープライズ向けストレージとして優れた特徴が多数あります。本節では主要な特徴とそれによるメリットを解説します。フルマネージドサービスならではの運用面の利点から、複数プロトコル対応や高可用構成、データ効率化機能によるコスト削減、高性能スケーラビリティまで、FSx for ONTAPが企業ITにもたらす価値を見ていきます。
フルマネージドサービスで運用負荷を軽減:煩雑な管理タスクをAWSが代行
FSx for NetApp ONTAP最大の特徴の一つがフルマネージドサービスであることです。ストレージ装置のセットアップやソフトウェア更新、障害対応といった煩雑な管理タスクをAWSが代行してくれるため、利用者はストレージの容量・性能を指定し、必要なデータを保存・共有することに専念できます。オンプレミスでONTAPシステムを運用する場合、専任のストレージ管理者がバックアップ計画を立てたり、ディスク故障時の対応をしたりと大きな負担がかかりましたが、FSx for ONTAPではそれら運用負荷が大幅に軽減されます。
例えば、ハードウェア故障時にはAWS側で自動的に代替リソースへフェイルオーバーし、ユーザーへの影響を最小限に留めます。またソフトウェアアップデートもAWSが適用するため、セキュリティパッチ漏れやバージョン管理の手間もありません。これらにより、企業のIT担当者はストレージ自体の運用よりも、データ活用やサービス開発といった本来の業務に注力できるようになります。要するに、FSx for ONTAPは“手離れの良い”ストレージとして日々のメンテナンス作業を削減し、運用コスト(OPEX)の削減にもつながるのです。
NFS・SMB・iSCSI対応の統合ストレージ:ファイルとブロックを一元管理可能
FSx for NetApp ONTAPはNFSやSMBといったファイルアクセスプロトコルだけでなく、iSCSIによるブロックストレージ提供にも対応する統合ストレージです。一つのサービスでNAS(Network Attached Storage)的なファイル共有とSAN(Storage Area Network)的なブロックデバイス提供の両方をまかなえるため、用途に応じて別々のストレージを用意する必要がありません。Linux系システムからはNFSマウントでファイル共有として利用し、Windows環境にはSMB(CIFS)共有を提供、データベースなどブロックデバイスを必要とするワークロードにはiSCSIターゲットを割り当てる、といった柔軟な使い方ができます。
さらにONTAPの強みとして、単一のデータセットに対して複数プロトコルで同時アクセス可能なマルチプロトコル機能があります。例えば同じボリューム上のデータに、あるアプリケーションはNFSでアクセスし、別のサービスはSMBでアクセスするといったことも可能です。内部でアクセス権(ACL)の整合性を保ちつつ、異なるOS間でデータを共有できるため、異種環境が混在する企業システムでもデータの一元管理が進みます。このようにFSx for ONTAPは多彩なプロトコル対応によって、さまざまなアプリケーションの要件を一つのストレージ基盤で満たせるメリットを提供します。
マルチAZ対応による高可用性:障害時も自動フェイルオーバーで継続運用
信頼性の面でもFSx for ONTAPは優れています。特に本番業務で求められる高可用性(HA)に対応しており、AWSの複数アベイラビリティゾーン(AZ)にまたがってストレージを冗長化するマルチAZ構成を選択可能です。マルチAZ構成では、2つのAZにそれぞれONTAPファイルサーバーのHAペア(アクティブとスタンバイ)が配置され、同期的にデータが複製されます。万一一方のAZで障害や停止が発生した場合でも、自動的にスタンバイ側にフェイルオーバーし、サービスを継続します。これにより99.99%の可用性が実現されており、非常に高いサービス継続性を誇ります。
フェイルオーバーは通常数秒~数十秒程度で完了し、クライアントは引き続き同じエンドポイント経由でデータにアクセスできます(内部的にIPアドレスの引き継ぎ等が行われます)。さらに障害復旧後は元の構成にフェイルバックすることで冗長性を回復します。このような自動HA機能のおかげで、ストレージ側のトラブルによる業務停止リスクを大幅に低減できます。一方、開発・検証用途など高可用性がそれほど重要でない場合にはシングルAZ構成も選べ、コストを抑えつつONTAPを利用することも可能です(詳細は後述)。用途に応じて冗長構成を柔軟に選択できる点もFSx for ONTAPのメリットと言えるでしょう。
データ効率化(重複排除・圧縮・階層化)によるコスト削減:自動機能でストレージ最適化
ONTAPにはストレージ業界でもトップクラスのデータ効率化技術が搭載されており、FSx for ONTAPでもそれが活用されています。その代表が重複排除(Deduplication)と圧縮(Compression)、そして自動階層化(Data Tiering)です。重複排除・圧縮によって、保存データから重複データブロックや不要な空き領域を取り除き、実効的な使用容量を削減します。これらはONTAPのストレージ効率機能としてAWSコンソールやCLIからワンボタンで有効化でき、あとは自動的にバックグラウンドで処理されます。その結果、ユーザーは見かけ上100GBのデータを書き込んでも、重複除去後は例えば60GBの実消費で済む、といった恩恵が得られます。
また自動階層化(「容量プールストレージ」へのデータ tiering)もFSx for ONTAPの大きな特徴です。これはアクセス頻度が低下したコールドデータを自動的に低コストなストレージ層(容量プール、内部的にはオブジェクトストレージ)に移動する仕組みです。ユーザー側で特別な操作をしなくても、一定期間アクセスの無いブロックがスピンドルディスク相当の安価な領域に移され、活発なデータのみ高性能SSD領域に残ります。これにより性能を犠牲にせずストレージコストを大幅に削減可能です。ONTAPはこの階層化(FabricPool機能とも呼ばれます)でも定評があり、クラウドサービス化されたことで容量拡張も柔軟に(プール領域はペタバイト級まで伸長可能)行えます。総じて、FSx for ONTAPはデータ効率化の自動化によってコスト最適化を実現するスマートなストレージと言えます。
優れたパフォーマンスとスケーラビリティ:大規模ワークロードにも対応する柔軟性
エンタープライズ用途では性能も重要ですが、FSx for NetApp ONTAPはその点でも高い能力を持っています。各ファイルシステムは数GB/秒級のスループットや数十万IOPS規模の性能を発揮でき、大規模な分析処理や多数ユーザーの同時アクセスにも耐えられます。必要に応じてスループット容量(帯域幅相当)を段階的に設定できるため、初期は低コストな設定で開始し、負荷が増えれば動的に引き上げるといったスケーラブルな運用も可能です。また最新世代のFSx for ONTAPでは複数のHAペアを単一ファイルシステムに束ねることで、ペタバイト級の容量やさらに高いIO性能を実現するオプションも提供されています。
ONTAP固有のQoS(Quality of Service)制御も利用可能で、ボリューム単位でIOPSの上限を設定し特定アプリケーションが他を妨げないよう調整できます。これにより、混在ワークロード環境でも安定した性能を維持することができます。さらにキャッシュ機構やNVMe対応(後述)によってレイテンシの低減も図られており、オンプレミス同様のスピード感でデータにアクセスできます。スケールの観点でも、ONTAPはクラスター化技術により柔軟な拡張が可能であり、FSx版でもその恩恵を受けられます。容量追加やプロトコルの有効化もオンデマンドで行えるため、将来の需要変化にも迅速に対応できるのです。これら性能・拡張性の高さも、FSx for ONTAPが企業システムに安心して導入できる理由の一つです。
FSx for NetApp ONTAPの導入事例とユースケース:さまざまなシナリオでの活用例
FSx for NetApp ONTAPは多機能で柔軟なストレージサービスであるため、様々なユースケースで活用されています。ここでは代表的な導入シナリオをいくつか紹介します。オンプレミスのNetAppストレージをクラウドに移行するケースから、新規にクラウド上でエンタープライズアプリケーションの基盤として使う例、開発・テスト用途での一時利用、さらにはバックアップ先や災害対策ソリューションとして利用する例まで、企業ITにおける幅広い活用シーンがあります。
オンプレミスNetAppからの移行:SnapMirrorで既存データをクラウドに無停止移行
従来オンプレミスでNetApp ONTAPストレージを使っていた企業が、そのデータをクラウドに移行するケースです。FSx for ONTAPはNetAppのSnapMirrorレプリケーションに対応しているため、オンプレミスのONTAPシステムからクラウド上のFSx for ONTAPへデータを同期コピーすることが可能です。SnapMirrorを用いることで、オンプレ側の業務を継続しながらバックグラウンドでデータ転送が行われ、完了後に切り替えることで無停止での移行が実現できます。この方法は既存データ量が多い場合やダウンタイムを最小化したい場合に有効です。
移行後は、アプリケーションサーバー等をAWS上に構築し、FSx for ONTAPに接続することでクラウド上でサービスを再稼働できます。ONTAP同士の互換性が高いため、ファイルアクセスの方法や権限設定などは移行前後でほとんど変わりません。結果として、ユーザーはクラウド上でオンプレ時とほぼ同じ感覚でデータを扱え、しかもインフラ保守の負担が軽減されます。こうした移行事例は金融機関や製造業など、既存NetApp資産を活かしつつクラウドメリットを享受したい企業で多く見られます。
ファイル共有やERPなどエンタープライズアプリケーションのAWS移行:オンプレ同等のストレージ機能をクラウドで提供
企業内で広く使われるファイルサーバーや、ERP・CRMといったエンタープライズアプリケーション基盤としてFSx for ONTAPを採用するケースです。これらアプリケーションは大量のファイルデータやブロックストレージを必要とすることが多く、オンプレではNetAppストレージが使われてきた例も少なくありません。FSx for ONTAPを利用すれば、そうしたアプリケーションをAWSクラウドへリフト&シフトする際に、ストレージ機能面での不足を感じることがありません。NFSやSMBによる共有フォルダ機能、Snapshotによるデータ保護、マルチプロトコル対応による異種OS間アクセスなど、オンプレNetAppで実現していたことがそのままクラウドで再現できます。
例えば、社内のファイル共有サーバーをFSx for ONTAPに置き換えれば、Active Directory連携のアクセス制御や、数千人規模のユーザーホームディレクトリ管理もスムーズに行えます。またERPシステムで必要なブロックストレージ(データベース用LUN等)もiSCSIで提供可能です。これにより基幹系システムをクラウドへ移行しつつ、ストレージ性能や機能面の不安を払拭できます。さらにFSx for ONTAPの高可用性により、オンプレミス以上にDR・BCP対策が強化できる点もメリットです。このようにFSx for ONTAPは、既存の企業アプリケーション資産をクラウドへ移す際の強力な受け皿となっています。
開発・テスト環境での一時的な高性能ストレージ利用:必要な期間だけ利用しコスト効率向上
FSx for ONTAPは必要なときに必要なだけストレージ環境を用意できるため、開発やテストプロジェクトの期間限定利用にも適しています。例えば、新製品開発のために大規模なシミュレーションを行う際、一時的に高速な共有ストレージが必要になるケースがあります。オンプレミスでは一時のために高額なストレージ機器を購入せざるを得ませんが、クラウドのFSx for ONTAPなら数週間~数ヶ月といった期間だけファイルシステムを作成し、使い終わったら削除することでコストを最小化できます。
またテスト環境では、本番データのコピーを頻繁に取り扱います。ONTAPのスナップショットとクローン機能を使えば、本番環境のデータセットから即座に複製を作りテストに利用し、検証が終われば削除するといったワークフローが可能です。これによりテストデータ準備の手間や時間を大幅に短縮できます。FSx for ONTAPは高性能なので、本番同様の負荷をかけたテストでもボトルネックになりにくく、正確な結果を得やすいという利点もあります。必要な期間だけリソースを使い、不要になれば停止できるのはクラウドサービスの強みであり、FSx for ONTAPもそれを活かして開発スピード向上とコスト効率化に貢献しています。
バックアップ/災害対策用途での活用:他リージョンやオンプレミスへのデータ複製でBCP強化
FSx for NetApp ONTAPは、既存データのバックアップ先や災害対策(DR)環境としても活用されています。例えばオンプレミスの重要データを定期的にAWS上のFSx for ONTAPにレプリケーションしておき、万一オンプレ環境が被災・停止した場合にはクラウド上で代替稼働させる、というシナリオです。ONTAP同士のSnapMirrorレプリケーションにより差分転送で効率的にデータ同期が行えるため、回線帯域や時間を有効に使いながら常に最新データをクラウド側に用意できます。
またAWSリージョン間のレプリケーションも可能なので、FSx for ONTAPから別リージョンのFSx for ONTAPへデータコピーを保持し、地域災害に備えることもできます。クラウド上にバックアップデータがあることで、オンプレに障害が起きても迅速に業務再開でき、BCP(事業継続計画)上大きな安心材料となります。さらにFSx for ONTAP自体にも自動バックアップ機能があり、日次バックアップを長期間蓄積しておくことでランサムウェア対策やデータアーカイブにも役立ちます。このように、FSx for ONTAPは本番データの保護・複製先として信頼性の高いプラットフォームであり、企業のデータレジリエンシーを高めるソリューションとして導入されるケースも増えています。
FSx for NetApp ONTAPのアーキテクチャ概要:ONTAPストレージシステムの構成と仕組み
ここではFSx for NetApp ONTAPのシステム構成について概観します。ONTAP固有の概念であるストレージ仮想マシン(SVM)やボリュームといった論理構成要素、シングルAZ/マルチAZといったデプロイタイプの違い、そしてAWS環境におけるネットワーク接続の仕組みについて説明します。これらを理解することで、FSx for ONTAPがどのようにストレージサービスを内部実現しているか、また利用者がどのようにアクセスするかが明確になります。
ファイルシステムの構成要素:SVM(ストレージ仮想マシン)とボリュームによる論理区画
FSx for ONTAPのファイルシステム内部は、NetApp ONTAPの論理構成に従っています。大きく分けてSVM(Storage Virtual Machine)とボリューム(volume)という単位があります。SVMはONTAP上で動作する仮想的なストレージシステムで、オンプレミスONTAPでは「Vserver」と呼ばれていたものです。FSx for ONTAPでも1つのファイルシステム内に複数のSVMを作成できます。各SVMは独立したネームスペース(名前空間)とセキュリティドメインを持ち、マルチテナント環境を実現する鍵となります。
一方、ボリュームは各SVM内に作成されるデータのコンテナです。ファイルやディレクトリはすべて特定のボリューム上に保存されます。ONTAPではボリューム単位でスナップショットを取得したり、クローンを作成したり、QoSを設定したりできます。FSx for ONTAPでも同様に、ボリュームごとに様々な操作や設定が可能です。なお一つのSVM内のボリュームは単一の論理名前空間(Unixライクなファイルシステムパス空間)にマウントできます。NFSならエクスポートパス、SMBなら共有名として提供されます。このように、FSx for ONTAPではSVMとボリュームという階層構造で論理的にデータを区画し、管理やアクセス権の単位としています。
Single-AZ vs Multi-AZの展開オプション:冗長化構成の違いと用途別の選択肢
FSx for NetApp ONTAPはSingle-AZ(単一AZ内)構成とMulti-AZ(マルチAZ冗長)構成の2種類のデプロイメントタイプがあります。Single-AZ構成では1つのAZ内にONTAPのHAペア(アクティブ-スタンバイの2台)が配置されます。同一AZ内とはいえ独立したフォールトドメイン(電源やラックなどの障害区画)上に2台が置かれており、片方に障害が起きれば同一AZ内のもう片方にフェイルオーバーする仕組みです。データもAZ内でリアルタイム同期されているため、ディスク故障等でも即座にスタンバイ側からサービスを提供できます。ただしAZ全体がダウンするような大規模障害時にはサービス継続できない可能性があります。
一方、Multi-AZ構成ではONTAPのHAペアを2つの異なるAZにまたがって配置します。アクティブノードとスタンバイノードが別AZに所在し、データはAZ間で同期複製されます。これにより、仮に片方のAZが完全に機能停止しても、もう一方のAZ側からデータ提供を継続できるため、AZ障害を含めた高可用性が実現します。一般にMulti-AZ構成はミッションクリティカルな本番ワークロード向け、Single-AZ構成は開発・テストや二次データ格納向けなど、必要な可用性レベルとコストを考慮して使い分けられます。
なお、ファイルシステムのデプロイタイプは作成時に選択し後から変更できないため、要件に合わせて慎重に選ぶ必要があります。例えば、まずSingle-AZで始めて後にマルチAZへ変更したい場合は、新規にMulti-AZファイルシステムを作成しデータ移行(バックアップ復元やSnapMirror同期)が必要になります。逆に高可用性が不要なワークロードではSingle-AZ構成を選ぶことでコストを抑えた運用が可能です。AWSはサービスレベル合意(SLA)としてFSx for ONTAPの可用性を定めていますが、マルチAZのほうが高い可用性保証となっています。
ネットワーク接続とアクセスエンドポイント:VPC内での接続方法と各プロトコル用エンドポイント
FSx for NetApp ONTAPへのアクセスは、ユーザーが設定するVPC(仮想プライベートクラウド)内のネットワーク経由で行われます。ファイルシステム作成時に所属させるVPCとサブネットを指定すると、その中にFSx for ONTAPのエンドポイントが作成されます。ONTAPのSVMごとに、プロトコル別の論理インターフェースが割り当てられ、NFS用、SMB用、iSCSI用などのエンドポイント(IPアドレス)が有効になります。クライアントとなるEC2インスタンスやオンプレミス環境(VPN/Direct Connect経由)は、このエンドポイント宛てに通信することでストレージにアクセスします。
例えばNFSの場合、FSx for ONTAPのエンドポイントIPをマウントターゲットとして指定し、エクスポートパスを指定してマウントします。SMBの場合は、SVMをActive Directoryドメインに参加させることでそのドメイン内のサーバーとして認識され、\SVM名\共有名の形式でアクセスできます。iSCSIではイニシエータ(クライアント側)からターゲットIPとしてFSxの提供するIPを指定し、LUNをディスクとして接続します。さらに最新機能としてNVMe over TCPにも対応しており、NVMeプロトコル用のエンドポイントを介して超低レイテンシアクセスも可能です。
ネットワーク的にはFSx for ONTAPはVPC内のENI(Elastic Network Interface)として実装されており、エンドポイントのIPアドレスは選択したサブネットの範囲から自動割当されます。セキュリティグループも設定でき、許可するクライアントのIP範囲やポートを制御可能です。エンドユーザーから見ると、あたかもVPC内に自前でNASサーバーを立てたかのように同じVPCまたは接続されたネットワークから利用できます。オンプレミスからの利用時はDirect ConnectやVPNでVPCにネットワークを伸張させておけば、そちらからも社内ファイルサーバー感覚でアクセス可能です。要するに、FSx for ONTAPはAWSクラウド内にシームレスに統合されたストレージノードとして機能し、既存ネットワーク環境と容易に接続できるよう設計されています。
FSx for NetApp ONTAPの対応プロトコルと接続性:NFS、SMB、iSCSI、NVMeなど多様なアクセスに対応
FSx for NetApp ONTAPは、多様なプロトコルによるデータアクセスに対応する点が大きな強みです。Unix/Linux系システムで広く使われるNFS、Windows環境で標準のSMB、ブロックデバイスを提供するiSCSI、そして最新の高速アクセスプロトコルであるNVMe over TCPまで、主要なアクセス方式を網羅しています。以下では各プロトコルごとの利用方法や特徴について解説します。また、一つのデータを複数プロトコルで扱えるマルチプロトコル同時利用の柔軟性についても触れます。
NFS・SMBによるファイル共有アクセス:Linux/Windowsクライアントからシームレスに利用可能
FSx for ONTAPはファイル共有用のプロトコルとしてNFS(Network File System)とSMB(Server Message Block)の両方をサポートしています。NFSはLinuxやUNIX系OSで主に使われるネットワークファイルシステムで、FSx上のSVMでNFSサーバー機能を有効化すれば、EC2上のLinuxサーバーやオンプレミスのUNIXマシンからNFSクライアントとしてマウント可能です。通常のNFSサーバと同様、エクスポートパスとアクセス許可(ホストベース、またはKerberos認証)を設定できます。これにより、社内のLinuxサーバ群をAWSに移行した場合でも、従来通りNFS共有ストレージを利用できるわけです。
SMB(昔はCIFSとも)はWindows環境でファイル共有に用いられるプロトコルですが、FSx for ONTAPのSVMをActive Directory(AD)ドメインに参加させることで、Windowsサーバーやクライアントからドメイン参加ファイルサーバーとしてSMB共有を利用できます。NTFSアクセス権(ACL)もONTAP側で管理でき、ドメインユーザごとのフォルダアクセス制御も可能です。FSx for ONTAP上に作成したSMB共有は「\FSx-SVM名\SharedFolder」のようにパス指定してアクセスでき、オンプレ時と変わらない操作感でファイルにアクセスできます。
SMBはまた、AWSの他サービスとの連携でも使われています。例えばAmazon WorkSpaces(WindowsデスクトップのDaaS)環境のユーザーデータをFSx for ONTAPのSMB共有に置くことで、社内ファイルサーバーと同様の体験をクラウド上で提供できます。NFSとSMBいずれの場合も、FSx for ONTAPの高性能ストレージ基盤によりオンプレ同等かそれ以上のスループット/IOPSでファイルアクセスできるため、ユーザーはストレスなく利用できます。
iSCSIによるブロックストレージ提供:オンプレSAN同様のLUNをクラウド上で実現
FSx for ONTAPはファイル共有だけでなくiSCSIプロトコルによるブロックデバイスの提供も可能です。ONTAPの用語ではLUN(Logical Unit Number)と呼ばれる論理ボリュームを作成し、それをiSCSIターゲットとして公開することで、EC2インスタンスなどからブロックストレージとして利用できます。オンプレミスのSAN環境でサーバがストレージからディスクを割り当ててもらうのと同じ感覚で、AWS上でも専用ディスク領域を提供できるわけです。
具体的には、FSx for ONTAP上のSVMにiSCSIサービスを有効化し、イニシエーター(接続元クライアント)のIQNを登録、LUNを作成してターゲットにマッピングします。EC2側ではiSCSIイニシエーターを設定してFSxのSVMターゲットに接続すると、新たなブロックデバイスが認識されます。これにより、例えばデータベース用のボリュームをFSx for ONTAPから提供し、EC2上のDBサーバに接続するといった構成が可能です。ONTAPのiSCSI機能は成熟しており、マルチパスIOやターゲットポータルグループ構成など高度な設定もサポートしています。
オンプレの既存環境から見ると、FSx for ONTAPをクラウド上のストレージアレイとして位置付け、iSCSI越しにサーバを接続することもできるため、ハイブリッドクラウド構成での利用も考えられます。例えばオンプレのVMware仮想環境からFSx for ONTAPへiSCSI LUNをマウントし、クラウド上にデータを保管・拡張するといった活用です。いずれにせよ、iSCSI対応によってファイル単位だけでなくブロック単位での高速IOニーズにも応えられる点で、FSx for ONTAPは柔軟なストレージソリューションとなっています。
NVMe over TCP対応による高速アクセス:最新プロトコルで低レイテンシのデータ処理
NetApp ONTAPの最新バージョンでは、NVMe over TCPというプロトコルにも対応しており、FSx for NetApp ONTAPでもそれを利用できます。NVMe over TCPは、従来のiSCSIに代わる高速ブロックアクセス手段で、NVMeの高スループット・低レイテンシ性能をネットワーク越しに実現する技術です。ONTAP上でNVMe名前空間を設定し、TCPネットワーク経由でNVMeイニシエータから接続することで、ブロックストレージをより高速に扱えます。
現在のところNVMe over TCPを活用するには対応するOS側のイニシエータが必要ですが、Linuxカーネルの新しいバージョンなどではサポートが進んでいます。FSx for ONTAPにNVMeで接続した場合、iSCSIよりもプロトコルスタックが軽量で並列処理に優れるため、高IOPSが求められるワークロードで効果を発揮します。特にデータベースのトランザクション処理やリアルタイム分析基盤など、極力レイテンシを抑えたいシナリオで有用です。
ONTAP自体が持つ強力なキャッシュやNVMe対応SSDとの組み合わせで、NVMe over TCP経由のアクセスでも一貫した高性能が出るよう最適化されています。まだ採用事例は新しいですが、クラウド上で先進的なストレージ技術を試せる点もFSx for ONTAPの魅力です。将来的にNVMe over Fabric系のプロトコルが主流になってきた場合にも、FSx for ONTAPを利用していれば早期に恩恵を受けられるでしょう。
マルチプロトコル同時利用の柔軟性:同一データに複数プロトコルでアクセス可能
前述の通り、FSx for NetApp ONTAPでは一つのSVM内の同じボリュームデータに対してNFSやSMB、iSCSIなど複数のプロトコルで同時アクセスすることが可能です。このマルチプロトコル対応の柔軟性は、ハイブリッドなIT環境で特に真価を発揮します。例えば、ある設計図データをWindowsクライアントのエンジニアはSMB共有フォルダ経由で編集し、Linux上のCADツールはNFS経由でそのデータを読み込む、といった使い方が実現できます。データの一貫性はONTAP内部で管理され、ロック機構やアクセス権も適切に調整されるため、ユーザーは意識せずとも異なる環境間で安全にデータ共有できます。
また、一時的にブロックデバイスとして利用したデータを後にファイル共有として公開し直す、というような使い分けも容易です。ONTAPではボリュームをフレキシブルに再エクスポートできますので、初めはiSCSIでデータを書き込んだ領域を後からNFSマウント用にする、といったことも可能です(もちろんデータ形式の互換性はアプリ側で考慮が必要ですが)。このような柔軟性は、複雑なワークロードを扱う企業や、移行期において新旧システムが混在する環境で特に役立ちます。FSx for ONTAPはこうしたユースケースに耐えうるユニファイドストレージとして、システム全体のシンプル化と効率化に貢献します。
マルチAZ・高可用性構成:可用性99.99%を実現するFSx for NetApp ONTAPの冗長構成
企業の基幹システムでストレージに求められる要件として、高い可用性と耐障害性があります。FSx for NetApp ONTAPはそうした要求に応えるべく、AWSインフラとONTAPのHA機能を組み合わせた強力な冗長構成を提供しています。ここではマルチAZ構成の仕組みとフェイルオーバー動作、またシングルAZ構成との比較や使い分けについて説明します。
マルチAZデプロイメントの仕組み:2つのAZにまたがるストレージペアによる高可用構成
FSx for ONTAPのマルチAZ構成は、クラウドサービスで高可用性を実現する優れたアーキテクチャです。具体的には、ONTAPのHAペア(アクティブノードとスタンバイノード)を異なる2つのAZに配置します。例えば1つのAZに「ONTAPコントローラA(アクティブ)」があり、別のAZに「ONTAPコントローラB(スタンバイ)」があるイメージです。両者の間ではミリ秒単位で同期的なデータミラーリングが行われており、アクティブ側に書き込まれたデータは即座にスタンバイ側にも書き込まれます。
この構成により、仮にAZ全体に障害が発生してAがダウンした場合でも、Bが最新データを保持しているためサービス継続が可能です。通常時、クライアントからのアクセスは主にアクティブ側が処理しますが、AWSが提供する仮想ネットワーク機能によって、どちらのノードがアクティブになっても同じエンドポイントIPで到達できるようになっています。したがってフェイルオーバー後もクライアントの接続設定を変える必要はなく、裏側でIPルーティングやDNS登録が切り替わることで透明な冗長化が実現されます。
マルチAZ構成は内部的には2つのAZ間の高速な専用リンクを用いてデータ同期しており、書き込み性能にも配慮されています。AZ間通信のオーバーヘッドはありますが、ONTAPの効率的なレプリケーション方式により多くのワークロードで影響を感じません。結果として、FSx for ONTAPのマルチAZ構成はオンプレミスのストレージでは難しかったサイトレベルの冗長化をシンプルに実現し、重要データの可用性を最大限に高めているのです。
自動フェイルオーバーとフェイルバック:障害時にサービス中断を防ぐ切り替え機能
FSx for ONTAPでは、マルチAZ・Single-AZを問わずONTAPのHAペアによる自動フェイルオーバー機能が提供されています。例えばActive側でハードウェア障害やソフトウェア異常が検出されると、数秒~数十秒程度でStandby側がActiveに昇格しサービス継続を引き継ぎます。マルチAZ構成ではAZ障害時にも同様にスタンバイノードが自動昇格します。これにより、ユーザーから見るとストレージへの応答が一瞬途切れる程度でシステムダウンには至りません。
フェイルオーバー発生時、クライアント側では一時的にIO待ちが発生したり再接続処理が走る場合がありますが、タイムアウト設定内であれば自動的に再確立されます。例えばNFSクライアントはデフォルトでリトライしますし、SMBクライアントも短時間の中断なら継続します。ONTAPのHAでは「テイクオーバー(引き継ぎ)」と称しますが、AWSのFSxサービスによってそれがシームレスに行われるため、管理者が手動介入する必要はありません。
障害が解消した際にはフェイルバックも自動で行われます。元のノードが復旧すると、一度同期を取った上で元のActive/Standby配置に戻ります。これにより再度障害が起きた際も常に対になるノードが待機している状態が保たれます。なお、こうしたフェイルオーバー/バックのイベントはCloudWatchやONTAPのイベントログで検知可能なので、発生を把握して後で原因分析するといった運用もできます。いずれにせよFSx for ONTAPでは、この自動切り替え機能によりストレージ由来のサービス中断リスクを最小限に抑えており、まさにミッションクリティカル用途に耐える高可用ストレージをクラウド上で提供していると言えます。
シングルAZ構成が適するケース:開発環境などコスト優先シナリオでの利用
FSx for ONTAPのシングルAZ構成は、マルチAZほどの広域冗長が不要なケースで有用です。シングルAZでも先述の通りAZ内でHAペアによる冗長はされていますので、単一機器障害には対応できます。AZ自体の障害リスクは残りますが、その分コストが低く抑えられているため、例えば開発・テスト環境や、バックアップコピーの一時保管先などに適しています。また、本番系でも他の手段でDR対策が講じられている場合(例えば別リージョンに定期バックアップしている等)は、あえてFSx本体はシングルAZで構築しコストを節約する、といった選択も考えられます。
特にFSx for ONTAPはシングルAZ/マルチAZで内部機能差はなく、違いは可用性レベルと費用面にあるため、要件に応じて柔軟に使い分けるのがポイントです。シングルAZ構成はMulti-AZに比べおおむね利用料金が約半分程度になるため、コストセンシティブな用途では魅力的です。その代わりサービスレベルSLAが若干低め(99.9%台など)になることに留意が必要です。
また2022年のアップデート以降、FSx for ONTAPではシングルAZ構成にも第2世代(Enterprise)タイプが追加され、一つのAZ内で複数HAペアを持つ大規模構成も選択可能になりました。これにより、AZ内完結であっても相当な規模・性能のシステムを組めるようになっています。将来的にニーズが変わればスナップショットやSnapMirrorを使って別のFSx(例えば別AZや別リージョン)へデータを転送し、高可用な構成へ移行することも可能です。シングルAZとマルチAZを状況に応じて選択できる柔軟性は、クラウドサービスならではの利点と言えるでしょう。
ストレージ仮想マシン(SVM)とは何か:マルチテナント環境を実現する仮想ストレージ機能の役割と活用方法の解説
FSx for NetApp ONTAPの特徴的な機能の一つに、ストレージ仮想マシン(SVM)の存在があります。SVMは、一つのONTAPストレージ内に論理的に独立したストレージ領域と管理ドメインを複数作る仕組みで、マルチテナントを実現する基盤です。本節ではSVMの役割や基本概要、SVMごとの設定項目、そして具体的な活用例について解説します。
SVMの役割と概要:1つのファイルシステム内で複数の仮想ストレージを提供
SVM(Storage Virtual Machine)はONTAP上で動作する仮想的なストレージシステムです。従来NetAppの資料では「Vserver(ボリュームサーバ)」とも呼ばれていました。FSx for ONTAPにおいても、1つのファイルシステム(=ONTAPクラスタ相当)に対して複数のSVMを定義できます。各SVMはそれぞれ独立した名前空間(ファイルパス構造)とネットワーク設定、セキュリティドメイン(認証・認可)を持ち、あたかも別々のストレージ装置が存在するかのように振る舞います。
例えば、SVMごとに管理者アカウントを分けて権限を委譲することが可能です。あるSVMの管理者は自分のSVM内のボリュームや共有の設定はできますが、他のSVMには干渉できません。これにより、一つの物理(または仮想)ストレージ資源を社内の複数部署・プロジェクト間で安全に共有することができます。FSx for ONTAPの場合、デフォルトで最初から1つのSVMが作成されますが、必要に応じて追加でSVMを作り、使用目的ごとに分離して使うことができます。
SVMは各自固有のネットワークインターフェイスやプロトコル設定を持つため、例えば「SVM-AではNFSのみ提供しLinuxサーバ用に使う」「SVM-BではSMBを有効化してWindowsクライアント用共有を提供する」といった役割分担も可能です。さらにディザスタリカバリ用途でSVM全体を別システムにレプリケーションする、といった単位にもなり得ます。ONTAPの柔軟性を支える重要な概念がSVMであり、FSx for ONTAPでもその利点を活かして組織や用途に応じた論理区画を切れるようになっています。
SVMごとのネットワークと認証設定:Active Directoryドメイン参加など独立したアクセス制御
SVMはそれぞれ独立したネットワーク設定と認証方式を持てるため、異なる環境要件に応じたカスタマイズが可能です。ネットワークに関しては、各SVMごとにIPアドレスやDNS名を設定できます。FSx for ONTAPではSVM単位で一つ以上のIPを割り当て(各プロトコル毎にLIF=Logical Interfaceが作られる)、クライアントはそのIPを指定して接続します。他のSVMとはIPも別なので、ネットワーク的にも分離が保てます。
またSMBサービスを提供する場合、SVM単位でActive Directory(AD)ドメインへの参加設定が可能です。例えばSVM-Aは「corp.local」というドメインに参加して社内ADユーザー認証を用い、SVM-Bは「test.local」という別ドメインに参加させて検証環境用にする、といったこともできます。あるいはSVM-CはADに参加せずワークグループモードでスタンドアロンのSMB共有とする、など運用ポリシーに沿った構成が可能です。
NFSについても、Kerberos認証を使うかどうか、ラボ環境なら認証なしのオープンな設定にするか等、SVMごとに調整できます。さらにボリュームや共有のネーミングもSVMごとに独立しているため、同じ名前の共有を別SVMで用意しても競合しません(例:各部署ごとに「home」共有を定義する等)。このようにSVMごとにネットワーク・認証の設定を独立させられることで、一つのFSx for ONTAPインスタンスをまるで複数のストレージに見立てて運用できるわけです。マルチテナントでの利用や、テスト・本番環境の論理分離など、多彩な要求に応じた設定を行える柔軟性はSVMの大きな利点です。
SVMの活用例:部門ごとの分離や開発・本番環境の分割に応用
では実際にFSx for ONTAPにおけるSVMはどのように活用できるでしょうか。典型的な例の一つが部門別のストレージ分離です。大企業では複数の部門が各々専用の共有ストレージを必要とすることがあります。その際、FSx for ONTAP上で部門ごとにSVMを作成し、管理者権限も各部門のIT担当者に委譲することで、一元的な物理リソースを使いながら運用管理は部門単位に任せることができます。互いのSVMには干渉できないためセキュリティも担保されますし、コスト的にも単体の大容量ストレージを共有することで経済性が向上します。
別の活用例は開発環境と本番環境の分割です。一つのFSx for ONTAPシステム内に「Prod_SVM」「Dev_SVM」といった具合にSVMを分けておけば、本番用と開発用のデータが論理的に隔離され、かつ本番SVMから最新データをスナップショット転送して開発SVMにクローン展開するといった使い方も容易です。これにより、本番と同じデータを使ったテストが安全に行えます(SVM間でネットワークを切り離しておけば開発者が本番領域に誤ってアクセスする心配もありません)。
他にも、マルチテナント型のSaaSサービスを提供する企業が、顧客ごとにSVMを割り当てるケースも考えられます。こうすれば各顧客データが完全分離されるためセキュリティ面で安心です。このように、SVMはFSx for ONTAPを一台で何役にも使いこなすための鍵となる機能であり、運用設計次第で様々な応用が可能です。
FSx for NetApp ONTAPのデータ管理・運用機能:スナップショットやレプリケーションなど高度な管理機能
FSx for NetApp ONTAPはデータの保護や運用を支える高度な管理機能も豊富に備えています。ここでは、その中から主要なものを取り上げて説明します。瞬時にデータコピーを取得できるスナップショットとクローン、本番環境を守るバックアップとリストア、遠隔地へのデータ同期を可能にするレプリケーション(SnapMirror)、さらに自動階層化によるストレージ効率化など、ONTAPが持つデータ管理機能がクラウド上でも活用できます。
スナップショットとクローン:瞬時にボリュームのコピーを取得しテスト環境に活用
NetApp ONTAPの代名詞とも言える機能がスナップショット(Snapshot)です。FSx for ONTAPでも各ボリューム単位でスナップショットを取得でき、ほぼ即時にその時点のデータ状態を保存します。スナップショットは読み取り専用の過去データイメージとして保持され、ユーザーは万が一ファイルを誤削除・上書きした場合でもスナップショットから容易に元に戻す(リストアする)ことができます。これはいわばタイムマシンのような機能で、細かな誤操作からランサムウェア被害まで幅広くデータを保護します。
さらにONTAP独自機能としてFlexClone(フレックスクローン)と呼ばれるクローン機能があります。スナップショットで撮った過去時点のデータを元に、新たな書き込み可能なボリュームを瞬時に作成できる技術で、FSx for ONTAPでも利用可能です。クローン作成はスナップショットのブロック参照を共有するため、最初は容量を消費せず、必要に応じ変更部分だけ追加容量を使います。これにより、本番データの完全コピー環境を短時間・省容量で作れるため、テストや分析用途に大変便利です。
例えば本番ボリュームのスナップショットを取得し、それを元にクローンを作成してテストサーバにNFSマウントすれば、本番と同じデータで開発検証ができます。作業が終わればクローンを削除するだけで、本番データには一切影響ありません。FSx for ONTAPではこうしたスナップショット/クローン機能によりデータの複製・展開を自在に行え、バックアップ用途からDevOpsの高速化まで幅広く貢献します。
バックアップとリストア:自動バックアップとポイントインタイム復元でデータ保護
FSx for ONTAPにはマネージドサービスならではの自動バックアップ機能も備わっています。これはファイルシステム全体のスナップショットを毎日自動取得し、別ストレージ(AWSのバックアップストレージ、一般的にはS3に類する耐久性ストア)に保存しておくものです。ユーザーは保持期間を設定しておくだけで、日次バックアップが世代管理されていきます。バックアップは複数AZ間で冗長保管されるため、たとえファイルシステムが重大障害に見舞われてもバックアップデータから復旧可能です。
万一のデータ損失時には、これらバックアップからポイントインタイム復元ができます。具体的には指定日時の自動バックアップイメージを元に新しいFSx for ONTAPファイルシステムを復元作成し、必要なファイルをコピーしたり、システム全体をロールバックしたりできます。バックアップからの復旧には多少時間がかかりますが、データ耐久性99.999999999%(11ナイン)のAWSストレージに保管されているため、ほぼ確実にデータを取り戻せます。
また必要に応じてオンデマンドでスナップショットをバックアップ化することも可能です。たとえば重要リリース前に手動バックアップを取得しておき、問題発生時にすぐ戻せるようにする、といった運用ができます。これらバックアップ機能のおかげで、FSx for ONTAP利用者は高度なバックアップソフトを別途用意せずとも安心してデータを預けられます。日々のスナップショットとは別の破壊耐性を持つ保存先があることで、総合的なデータ保護レベルがさらに高まります。
レプリケーション機能(SnapMirror):他リージョンやオンプレへの同期で災害対策を実現
NetApp ONTAPにはSnapMirrorという強力なデータレプリケーション機能があり、FSx for ONTAPでもこれを活用できます。SnapMirrorを使うと、あるONTAPボリュームの内容を定期的に差分転送し、別のONTAPシステム上のボリュームに同期コピーを保持できます。FSx for ONTAP間はもちろん、オンプレミスのNetApp FAS/AFF装置や他リージョンのFSx for ONTAPともレプリケーションリンクを結べます。
この機能により、遠隔地へのデータ同期が比較的簡単に実現します。例えば東京リージョンのFSx for ONTAPから大阪リージョンのFSx for ONTAPへSnapMirror設定を行えば、定期的に差分データが大阪側に送られます。普段は待機状態ですが、東京側に災害が起きた際には大阪側を読み書き可能にプロモートしてサービスを引き継ぐ、といったDR構成が取れます(RPO/RTOは設定次第ですが数分~数時間程度に抑えることも可能です)。
オンプレミスのNetAppとの連携も同様で、本社データセンターにあるNetAppストレージからクラウド上のFSxへSnapMirrorでコピーを送り、万が一本社設備がダウンしたらクラウド側でサービス代行する、といったシナリオが可能です。SnapMirrorはブロックレベルの増分のみ転送する効率的な方式のため、回線帯域の節約にも優れています。FSx for ONTAPはこのSnapMirror対応によって、ハイブリッドクラウド/マルチリージョンでの包括的な災害対策ソリューションを構築できる点が大きな強みです。
自動階層化とストレージ効率化:低頻度データを自動ティアリングしコスト最適化
前述の特徴の章でも触れましたが、FSx for ONTAPには自動データ階層化(FabricPool)によるストレージ効率化機能があります。これも運用管理上非常に有用な機能です。具体的には、一定期間アクセスされていないブロックデータを高性能Tier(SSD)から低コストTier(容量プールストレージ)へ自動的に移動します。ユーザーはポリシーとして何日非アクセスなら階層化するかを設定しておくだけで、あとはONTAPがバックグラウンドで監視・移行を行います。
この機能により、使われていない古いデータがいつまでも高価なSSD領域を占有し続ける無駄を防げます。容量プール側はスループットやIOPS性能は劣りますが、めったに読み書きしないアーカイブデータであれば問題ありません。必要になれば自動的にプロモーション(再度SSD側に昇格)されるので、ユーザーは意識せず運用できます。結果として、システム全体のストレージコストを継続的に最適化でき、運用担当者が手動でデータ配置を見直す手間も省けます。
またONTAPが備える重複排除・圧縮と合わせて、こうした効率化機能は運用における容量管理の悩みを大きく軽減します。「いつの間にかストレージがいっぱいに…」という事態も起こりにくく、必要ならオンデマンドで容量追加もできるため、非常に柔軟です。FSx for ONTAPは高度な自動最適化機能で運用管理者を助けつつ、コストメリットも提供する洗練されたサービスと言えます。
FSx for NetApp ONTAPの料金体系とコスト最適化:容量・性能に応じた課金モデルと節約ポイント
FSx for NetApp ONTAPの料金は、利用リソースに応じた従量課金制になっています。オンプレミスのような初期ハードウェア購入費は不要ですが、その代わり毎月の利用量に比例した費用が発生します。本節では基本的な料金体系の内訳と、コストを最適化するためのポイントについて説明します。適切に設定・運用することで、必要十分な性能を確保しつつ費用を抑えることが可能です。
基本料金モデル:ストレージ容量、IOPS、スループットに応じた従量課金体系
FSx for ONTAPの主な課金項目は、大きく分けて以下の通りです:
- SSDストレージ容量 – プライマリのSSD領域に割り当てた容量に対する料金(GB/月)。プロビジョニングした容量全体に課金。
- プロビジョンドIOPS – 容量あたり3IOPS/GBを超えて追加で確保したIOPS分に対する料金(IOPS/月)。標準で容量に応じたIOPSが含まれ、それ以上を予約設定した場合のみ課金。
- スループット容量 – 選択したスループット性能(例えば128MB/s, 512MB/sなど)に応じた料金(MB/s換算・月)。ファイルシステム作成時に帯域クラスを選ぶ形。
- 容量プールストレージ消費量 – 自動階層化でプールに置かれたデータ容量に対する料金(GB/月)。プール領域は安価。
- バックアップストレージ消費量 – 自動・手動バックアップで保存されたデータ容量に対する料金(GB/月)。
基本的には「使用リソースに応じた従量課金」であり、使っていないものには費用はかかりません。ただしSSD容量などはプロビジョニング量ベースなので、例えば1TiBボリュームを作って10%しか使っていなくても1TiB分課金となる点に注意です(その代わりThin Provisioningを活用すれば実際に必要な物理容量だけ確保しコスト削減できます)。
またIOPSやスループットは必要に応じて上げられますが、その分料金も上がります。最適な値にチューニングすることでコストと性能のバランスを取ることが重要です。一方、容量プール側の利用は非常に低単価なので、アクセス頻度の低いデータを積極的にプールに逃がすほど経済的になります。
バックアップとデータ転送の費用:バックアップ領域やAZ間通信に関わる料金
FSx for ONTAPの料金で見落としがちなのが、バックアップとデータ転送に関する部分です。まずバックアップについては、前述のようにバックアップ先ストレージ利用量に課金があります。バックアップは重複排除・圧縮が効いた形で保存されるとはいえ、世代数が増えると容量も増加します。長期保管が不要なバックアップは適宜ライフサイクル設定で削除するなどし、無駄なコストを抑える工夫が必要です。
またデータ転送については、FSx for ONTAP自体には明示的なデータ転送料金は課されませんが、AZ間あるいはリージョン間通信に関してAWS共通のデータ転送料が発生する場合があります。例えばマルチAZ構成では、片方のAZからもう片方への同期通信が行われますが、これは内部的に同一リージョン内なので追加料金はありません。しかしバックアップデータの復元で別AZにデータを出す場合や、リージョン間SnapMirrorでデータを送る場合など、AWSのネットワーク転送料金がかかるケースが考えられます。
さらにクライアントからFSxへのアクセスでも、異なるAZやリージョンからアクセスすればデータ転送料金が発生する可能性があります(例:アプリサーバーとFSxが別AZの場合、クロスAZ通信の料金)。したがって、できるだけ同じAZ内で完結する配置にしたり、必要以上に遠隔地との大量同期をしない、といった設計・運用面の工夫でコストを下げることが可能です。
容量プールストレージの活用:自動階層化による低コストストレージへのデータ退避
コスト最適化の大きなポイントとなるのが、前述した容量プールストレージの活用です。FSx for ONTAPではアクセス頻度に応じてデータを容量プール(低コストのストレージ層)に移せますが、この容量プールの料金は通常のSSDストレージよりかなり割安に設定されています。したがって、この機能を有効活用すれば必要最低限のホットデータだけSSD料金を払い、大半のコールドデータは低廉なプール料金で済ませる、といった運用ができます。
例えば、全データが100TiBあるうち最近アクセスがあるのは20TiB程度だとします。その場合、20TiBをSSDに残し、80TiBはプール側に落としておけば、80TiB分については大幅に安いGB単価となります。ユーザーから見ると容量はトータル100TiB維持されており必要時には自動昇格するので、サービスに支障はありません。このように自動階層化を前提とした容量設計を行うことで、過剰なSSD割当を避けコスト効率を上げられます。
加えて、Thin Provisioning(シンプロビジョニング)を有効にしておくことで、実使用分以上にストレージを確保しないようにもできます。ONTAPのストレージ効率化機能も総動員して、必要容量を論理的に圧縮してから料金換算されるよう調整することがポイントです。もちろん急増するデータに備えてある程度余裕を持った容量設定は要りますが、FSx for ONTAPは容量追加も柔軟にできるため、余剰を抱えすぎず段階的に拡張する方が経済的でしょう。
重複排除・圧縮機能による削減効果:効率化機能で使用容量を縮小しコスト最適化
FSx for ONTAPで忘れてはならないのが、重複排除やデータ圧縮による容量削減効果です。これらONTAPの効率化機能により、見かけ上プロビジョニングした容量より実際の物理消費を抑えられれば、その分ムダな課金を防げることになります。FSxの料金はプロビジョン容量ベースですが、将来的に実利用が膨らんでも効率化で吸収できれば追加容量購入(月額費用増)を先延ばしできます。
例えば、仮想デスクトップ環境のユーザープロファイルが多数ある場合、重複部分が非常に多く発生しますが、ONTAPの重複排除を使えば共通部分を1コピーにまとめられます。圧縮もテキストデータやデータベースなどで効果が高く、50%以上の削減も珍しくありません。実際、NetAppはこれらを組み合わせた総合的なストレージ効率で定評があり、FSx for ONTAP上でもその恩恵をフルに受けられます。
さらにコストという観点では、マルチAZ構成かシングルAZ構成かの選択も影響します。マルチAZは冗長性が高い分、内部的にデータ2重化されるためコストはシングルAZの概ね2倍近くになります。したがって、予算制約が厳しい場合やバックアップコピー程度の用途であればシングルAZとし、その代わり重要データは他にバックアップするなどしてリスクヘッジするといった方法もあります。
このように、FSx for ONTAPのコストは設定と運用工夫次第で大きく左右されます。性能・可用性とコストのバランスを考え、効率化機能を駆使して必要十分なリソースだけ使うことで、クラウドストレージの強みを活かした経済的な運用が可能となります。
FSx for NetApp ONTAPの構築・利用の手順:基本設定からデータアクセスまでの流れ
最後に、FSx for NetApp ONTAPを実際に構築して利用を開始するまでの一般的な手順を説明します。AWSマネジメントコンソールでの設定を中心に、必要な前提条件の準備からファイルシステムの作成、ストレージ仮想マシン(SVM)やボリュームの設定、そしてクライアントからのアクセス方法まで、一連の流れを追ってみましょう。
前提条件の準備:接続先VPCやActive Directoryドメインなど必要環境の設定
まずFSx for ONTAPを利用するための前提条件として、ネットワークと認証の環境を整えておきます。FSxは特定のVPC内のサブネットに配置されるため、事前に適切なVPCとサブネット(空きIPが十分あること)を用意します。また、SMB機能を使う場合はMicrosoft Active Directory環境が必要です。既存のオンプレミスADをAWSに連結するか、AWS Managed Microsoft ADを構築するなどして、FSxを参加させるドメインを決めておきます。ADが不要ならこの準備は省略可能です。
セキュリティグループの用意も重要です。FSxにアタッチするセキュリティグループを作成し、NFSの場合はクライアントのTCP2049ポート、SMBなら445ポート、また管理API用にTCP/UDP 111ポートなど、使用プロトコルに応じポートを開放しておきます。さらにクライアントとなるEC2などのサーバー側も、同じVPC内に配置するか、別ネットワークの場合はピアリングやDirect Connect/VPNで接続しておく必要があります。
以上をまとめると、前提段階ではネットワーク接続と名前解決、必要なら認証基盤の準備がポイントです。適切なVPC設計とAD連携設定を済ませておけば、後のステップがスムーズになります。
ファイルシステムの作成:AWSコンソール上でFSx for ONTAPの基本設定を指定しデプロイ
準備が整ったら、AWSマネジメントコンソールからFSx for NetApp ONTAPのファイルシステムを作成します。コンソールの「FSx」サービス画面で「ファイルシステムの作成」をクリックし、タイプとしてAmazon FSx for NetApp ONTAPを選択します。するとウィザード形式で各種設定項目を入力していくことになります。
まずデプロイタイプとして「マルチAZ」または「シングルAZ」を選びます。次にストレージ容量(SSD容量)を指定します。必要容量+将来拡張見込みを考慮してTiB単位で入力します。続いてスループット容量(例: 512 MB/sなど)を選択し、必要なパフォーマンスレベルを設定します。IOPSは容量に応じ自動計算されますが、さらに必要なら追加IOPSを指定可能です。
ネットワーク設定では、FSxを配置するVPCとサブネット、および前段で作成したセキュリティグループを選択します。また、Active Directoryに参加させる場合はここでドメイン情報を入力し、サービスアカウントの認証情報を与えます。これにより、FSx作成時に自動でSVMがそのドメインに参加します。暗号化設定ではデフォルトでAWS管理のKMSキーが使われますが、必要に応じて独自のKMSキーを指定することもできます。
最後に「ストレージ効率を有効にする」オプションがあり、これはONTAPの重複排除・圧縮・コンパクション機能を有効化するかどうかです。通常は有効化しておくのが推奨です(デフォルト有効)。以上の設定を確認し、「作成」ボタンを押すとFSx for ONTAPファイルシステムの構築が始まります。数分から十数分程度で準備が完了し、利用可能な状態になります。
ストレージ仮想マシン(SVM)の作成:利用プロトコルに応じたネットワークエンドポイントを設定
FSxファイルシステムが作成されると、デフォルトで一つのSVM(デフォルトSVM)が構成されています。必要に応じてここに追加のSVMを作成します。例えば部署ごとに分けたい場合や、異なるActive Directoryドメイン用に分離したい場合です。SVM作成はAWSコンソール上から「ストレージ仮想マシンの作成」で行い、SVM名や、参加させるActive Directoryドメイン(またはCIFSワークグループ名)、有効にするプロトコル(NFS, SMB, iSCSI)などを設定します。
各プロトコルに対し、ネットワーク設定も必要です。すなわちSVMに割り当てるIPアドレスやネットマスク、ネットワークインターフェイス(サブネット)などを指定します。通常はFSx作成時に指定したサブネット内で自動割当てにすることが多いでしょう。SMBの場合は先ほど入力したADに参加するため、追加設定はほぼ不要ですが、ドメイン参加に成功しているかを確認します。NFSやiSCSIは特に外部サービス連携は無いので、そのままになります。
iSCSIを使う場合、SVM作成後にONTAPのCLIまたはAPIでLUNマップ設定等を行う必要があります(AWSコンソールUIでは現時点でiSCSI LUN作成操作がサポートされていない可能性があるため)。ただこの記事の範囲では詳細は割愛します。いずれにせよSVMが用意できれば、それぞれのSVMに対してクライアントが接続するための論理インターフェイス(LIF)が有効になります。
コンソール画面からSVM一覧を見れば、各SVMのNFS接続用エンドポイント(IPとエクスポートパス)、SMB用エンドポイント(UNCパス)、iSCSIターゲット名などが確認できます。これら情報を後のクライアント設定で使用します。SVMの役割としては、ストレージ利用者にとっての「窓口」となる仮想ストレージサーバーの用意が完了した段階です。
ボリューム作成とアクセス権設定:NFSエクスポートやSMB共有を作成し権限を構成
SVMを準備したら、その中にボリュームを作成して実際のデータ格納領域を確保します。ボリューム作成はAWSコンソールの「ボリューム」メニューから可能です。新規ボリューム作成時に、所属させるSVM、ボリューム名、サイズ、そして配置先アグリゲート(FSxではSSDアグリゲート固定)などを指定します。またエクスポートパス(Unixパス)や、ジャンクションパス(名前空間にマウントするパス)を決めます。通常は「/vol1」のようにルート下に配置します。
NFSの場合、このボリュームのエクスポートを有効化し、アクセス許可(ルール)を設定します。例えばCIDRベースで「10.0.0.0/16から読み書き可」等を指定可能です。SMBの場合は、ボリュームに対して共有名を付けてSMB共有として公開します。FSxコンソールから「SMB共有の作成」でボリュームを選び、共有名(例:data-share)とアクセス許可(読み取り専用/読み書き)を設定できます。
SMB共有の細かなアクセス権(ACL)は、Windowsのエクスプローラから共有フォルダのプロパティを開き「セキュリティ」タブでNTFS権限を設定する形で管理します(FSx上ではそのNTFS ACLがボリュームに保持されます)。Active Directoryドメイン参加済みであれば、ドメインユーザやグループに対してフォルダアクセス権を設定でき、企業のセキュリティポリシーに沿った利用者制限が可能です。
iSCSIの場合は、ONTAP CLIでボリュームをLUNとしてマスキングしターゲットに関連付けますが、ここでは割愛します。ボリュームおよび共有の設定が終われば、ストレージ側の準備は完了です。あとはクライアント(サーバー側)から実際にこのボリュームにアクセスして使う段階となります。
クライアントからのアクセス:EC2などからマウントしてファイルシステムを利用開始
最後にクライアント側の設定です。まずNFSの場合、EC2 Linuxサーバーからの接続であれば、マウントコマンドを使用してFSx for ONTAPのNFSエクスポートをマウントします。例として、FSxコンソールに表示されているエンドポイントIP(またはDNS名)とエクスポートパスを用いて:
sudo mount -t nfs -o vers=4.1 fsx-endpoint.amazonaws.com:/vol1 /mnt/fsxshareのように実行すれば、/mnt/fsxshare 配下にFSx上のデータが見えるようになります(適宜fstabに登録すれば永続化も可)。
SMBの場合、Windowsサーバーからであればエクスプローラで\FSxSVM\共有名を開くか、「ネットワークドライブの割り当て」でドライブレターを指定してマウントします。初回は資格情報(ADドメインのユーザ名・パスワード)を求められるので入力すれば、そのユーザがアクセス許可を持つフォルダに接続できます。LinuxからSMBを使う場合は、cifs-utilsを使って同様にマウント可能です。
iSCSIの場合、例えばWindowsなら「iSCSIイニシエーター」設定からターゲットとしてFSxのSVMターゲットIQNを指定し、接続→ディスクの初期化→ボリューム作成といった流れで利用開始します。Linuxならopen-iscsiでターゲットログインしデバイスマッピングしてからファイルシステムを作成します。
以上の手順を経て、クライアントからFSx for NetApp ONTAP上のデータにアクセスできれば導入は完了です。あとは必要に応じてスナップショットポリシーを設定したり、CloudWatchで性能メトリクスを監視したり、バックアップ保持期間を調整したりと運用フェーズに移ります。こうした高度な運用もAWSマネージドサービス上で実施できるため、手探りでONTAPを構築するより格段に効率良く安心して利用を開始できるでしょう。















