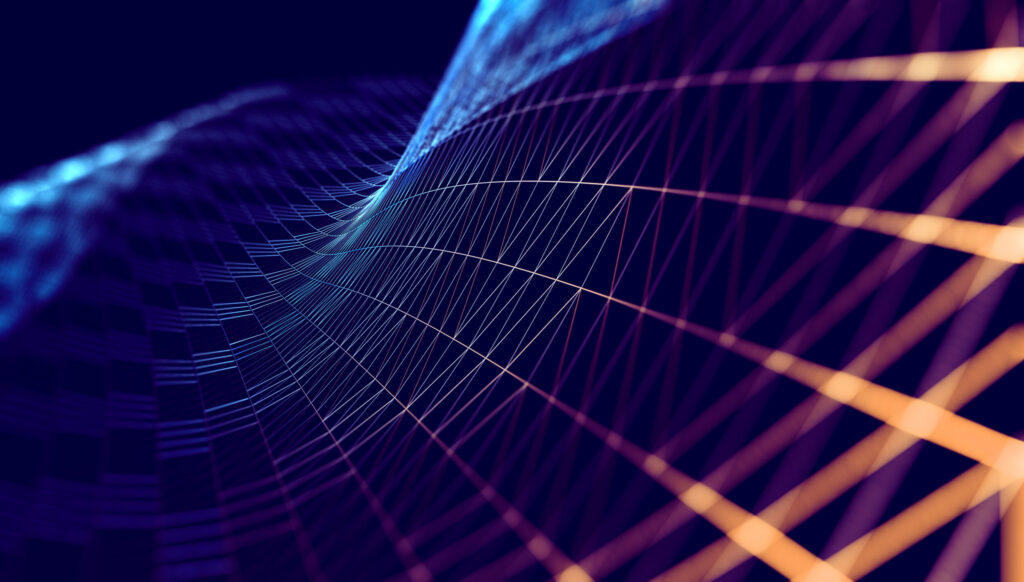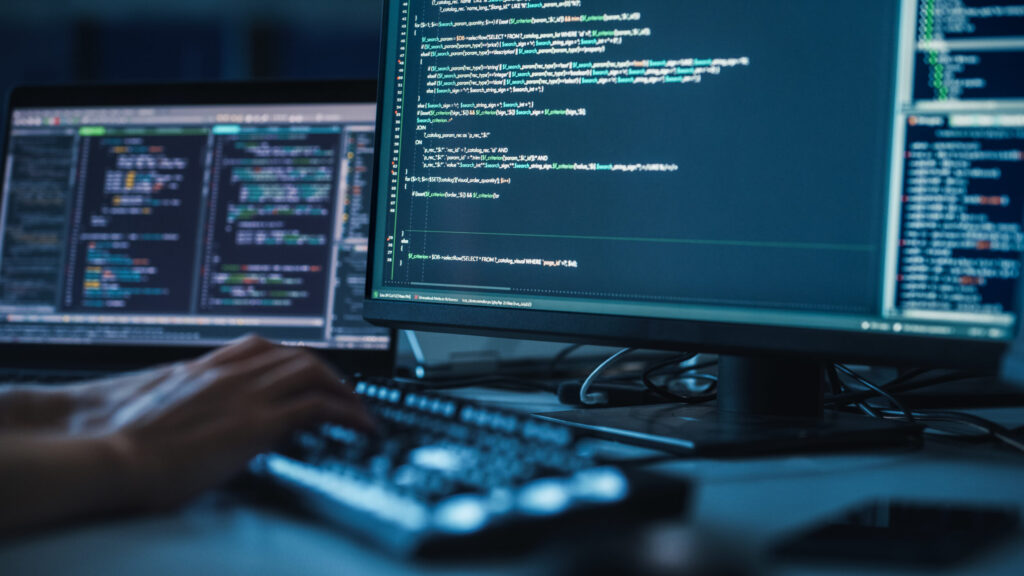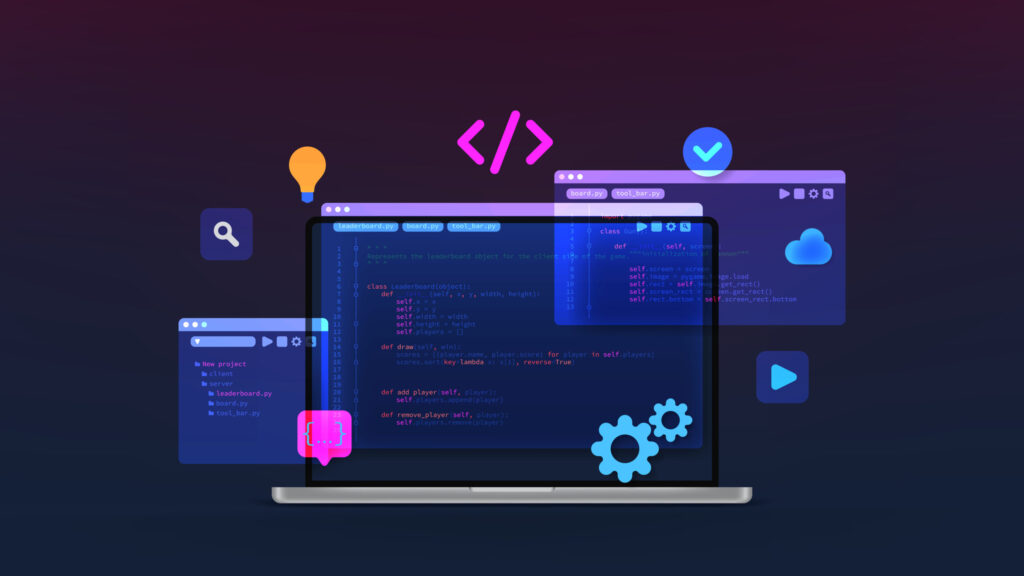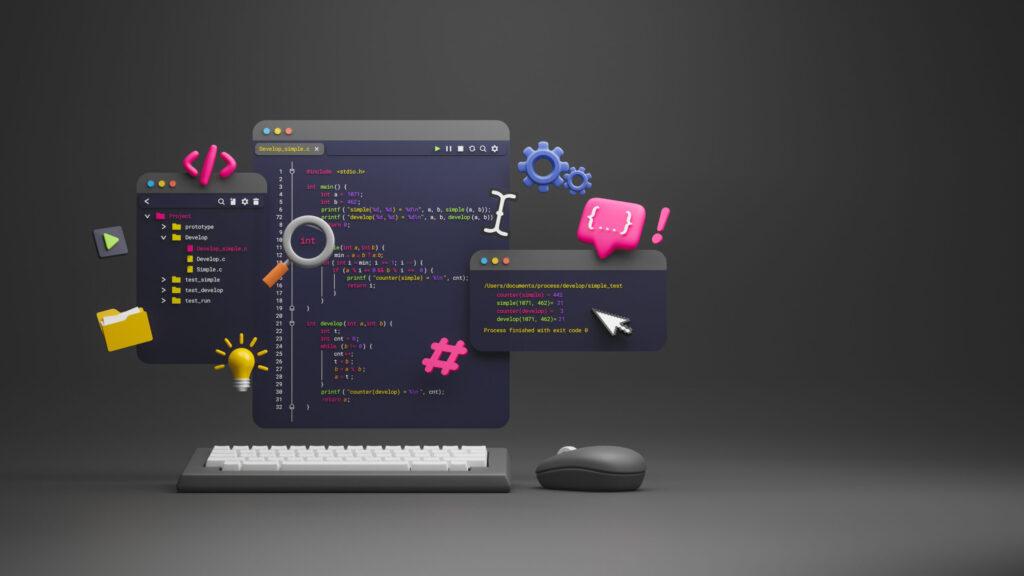Datadog CodeSecurityが提供する主な機能と技術的特徴
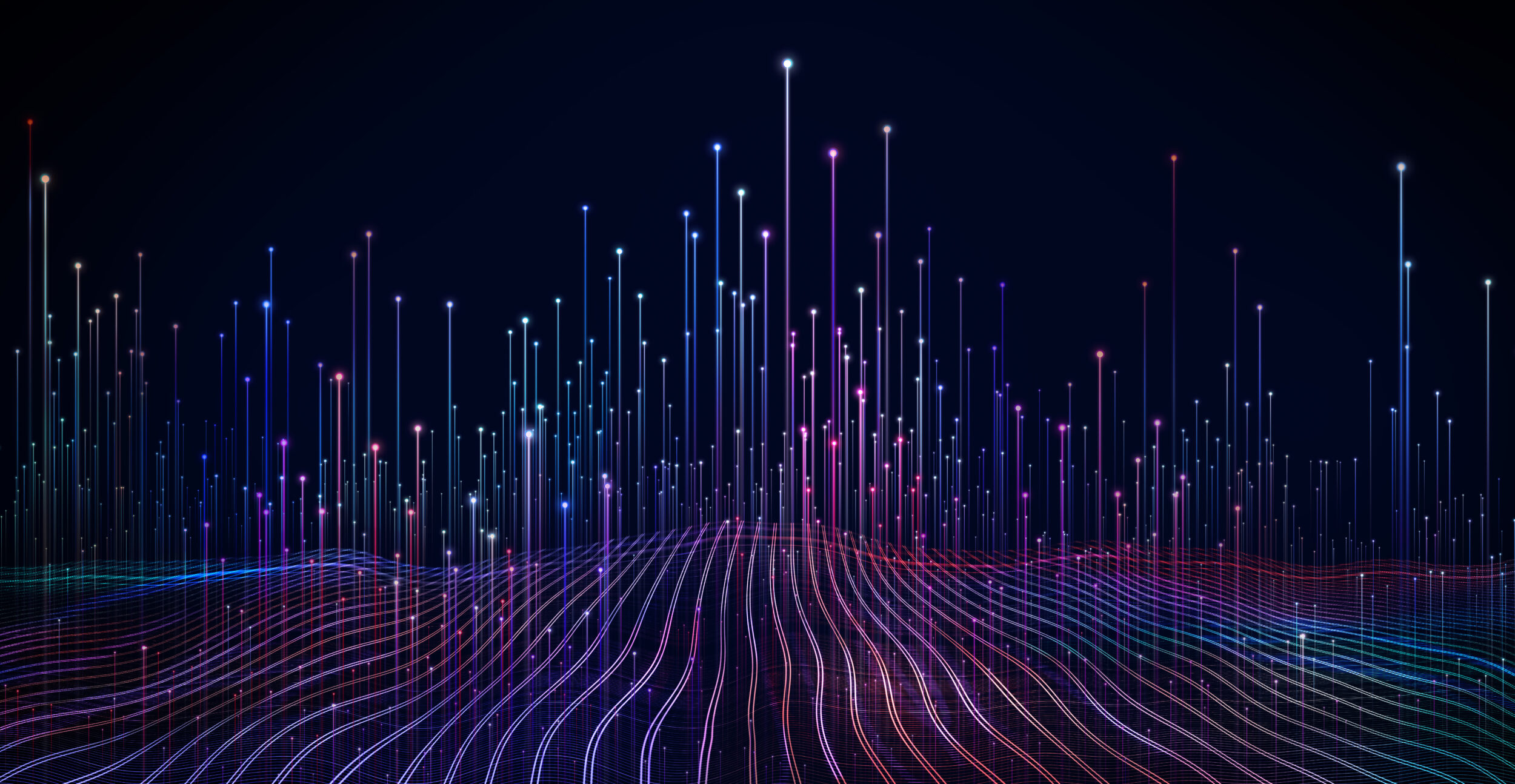
目次
- 1 Datadog CodeSecurityとは何か?最新のセキュリティ監視の革新
- 2 Datadog CodeSecurityが提供する主な機能と技術的特徴
- 3 コード脆弱性をリアルタイムで検出・管理する仕組みとは
- 4 静的コード解析(SAST)の役割とCodeSecurityでの活用方法
- 5 インストール不要のエージェントレススキャンによる利便性と効果
- 6 本番環境での脅威検出に対応するIAST機能の重要性と活用例
- 7 WAFなど他のセキュリティツールと比較したDatadogの優位性
- 8 開発環境やCIパイプラインと連携することで得られるセキュリティ効果
- 9 脅威をリアルタイムで検出し迅速に対応するための仕組みと機能
Datadog CodeSecurityとは何か?最新のセキュリティ監視の革新
Datadog CodeSecurityが誕生した背景とセキュリティ市場の変化
現代のアプリケーション開発において、セキュリティは開発初期から組み込むべき必須要件となっています。従来のセキュリティツールは主に運用フェーズで使用されていましたが、コードレベルでの脆弱性がビジネスリスクに直結する現在では、より早期に脅威を検出し対処する必要があります。Datadog CodeSecurityはこのニーズに応えるべく、クラウドネイティブ環境に特化した形で誕生しました。特にCI/CDパイプラインへの統合性とリアルタイム監視能力が注目されており、DevSecOpsを推進する企業にとって不可欠なソリューションとなっています。
アプリケーションセキュリティの包括的な可視化を実現する
Datadog CodeSecurityは、アプリケーションコードに潜む脆弱性を開発段階で検出し、運用環境まで一貫して可視化する機能を備えています。静的コード解析(SAST)やインタラクティブアプリケーションセキュリティテスト(IAST)を活用し、ソースコードや実行環境の挙動を多角的に監視することが可能です。これにより、開発者とセキュリティチームは同一プラットフォーム上で連携でき、セキュリティリスクの早期特定と修正が実現します。従来のツールのように複数のシステムを横断する必要がなく、セキュリティ運用の効率化にも貢献します。
クラウドネイティブ環境に特化したセキュリティ設計の強み
近年のソフトウェアはマイクロサービスやKubernetes、サーバーレスといったクラウドネイティブ技術を採用しており、従来のオンプレミス型セキュリティでは対応が困難になっています。Datadog CodeSecurityはこうしたクラウドネイティブ環境を前提に設計されており、各種クラウドプロバイダーとのシームレスな連携やエージェントレススキャンなど、柔軟性の高い機能を提供しています。また、Datadog本体のモニタリング機能とも統合されているため、アプリケーションパフォーマンスとセキュリティを同時に監視できる点も大きな利点です。
セキュリティ運用チームと開発者の連携強化を支援する仕組み
従来は開発チームとセキュリティチームの連携が乏しく、脆弱性対応が後手に回ることも少なくありませんでした。Datadog CodeSecurityでは、GitHubやGitLabといった開発ツールと統合されており、脆弱性の発見が即座に開発者へ通知されます。これにより、修正対応までの時間を短縮でき、セキュリティと開発スピードの両立が実現されます。また、発見された問題には推奨修正案が添えられるため、セキュリティ専門知識がない開発者でも容易に対応できる仕組みが整っています。
既存のDatadogユーザーにとっての導入ハードルの低さ
すでにDatadogを利用しているユーザーにとって、CodeSecurityの導入は非常にスムーズです。追加のソフトウェアや複雑な設定は不要で、既存のDatadogアカウントに機能を追加するだけで利用を開始できます。特にDatadogの統合ダッシュボードやアラート機能との連携が強力で、セキュリティインシデントとパフォーマンスの関係を可視化することが可能になります。これにより、トラブル発生時の根本原因の特定が迅速に行えるほか、既存のモニタリングフローにセキュリティを自然に組み込むことができます。
Datadog CodeSecurityが提供する主な機能と技術的特徴
脆弱性スキャン・依存関係分析など多彩なセキュリティ機能
Datadog CodeSecurityは、コードレベルのセキュリティスキャンから依存関係の脆弱性チェックまで、幅広いセキュリティ機能を備えています。特に、オープンソースライブラリやサードパーティパッケージに含まれる既知の脆弱性(CVE)を自動で検出し、リスクレベルに応じた対処方法を提示する仕組みは、開発者にとって非常に有益です。また、これらの情報はすべてDatadogのダッシュボードで一元管理され、リアルタイムで更新されます。これにより、プロジェクト単位でのセキュリティ状況の把握が容易になり、予防的な措置を講じることが可能です。
静的解析・インタラクティブ解析を統合した脅威検出の仕組み
Datadog CodeSecurityの大きな強みの一つは、SAST(静的コード解析)とIAST(インタラクティブアプリケーションセキュリティテスト)を組み合わせた脅威検出能力です。静的解析では、コードに潜むロジックミスや安全でない書き方を検出し、開発初期段階でのセキュリティ強化に貢献します。一方、IASTでは実行時のアプリケーション挙動を監視し、動的に発生する脆弱性にも対応可能です。これらの手法を同時に活用することで、理論上のリスクと実際の挙動に基づくリスクの両面をカバーし、セキュリティの網羅性が格段に向上します。
エージェントレススキャンでのセキュリティテスト自動化機能
多くのセキュリティツールは、対象環境へのエージェントインストールを必要としますが、Datadog CodeSecurityはその煩雑さを排除し、エージェントレスでスキャンを実行できます。これにより、導入・運用の手間が大幅に削減され、既存インフラへの影響も最小限に抑えることが可能です。GitHubやBitbucketなどのリポジトリを指定するだけで、リモートからコードをスキャンし、脆弱性を自動で検出・レポート化します。これにより、CI/CDの一環としてセキュリティチェックを簡単に組み込むことができ、開発プロセスにおけるセキュリティ意識の底上げが実現します。
リアルタイムでのセキュリティアラートと可視化ダッシュボード
Datadog CodeSecurityは、脆弱性の検出と同時にアラートを発信し、開発者やセキュリティ担当者に即時対応を促します。これらのアラートは、Slack、Teams、PagerDutyなどの通知ツールとも連携可能で、チームのワークフローに合わせた迅速な対応を支援します。また、専用のダッシュボードでは、検出された脆弱性の件数、重大度、対応状況などがグラフィカルに表示され、セキュリティの全体像を一目で把握できます。プロジェクト別・チーム別にカスタマイズすることも可能で、エンジニアリングマネージャーにとっても非常に有用な管理ツールとなります。
マルチクラウド対応とCI/CDツールとの幅広い統合機能
Datadog CodeSecurityは、AWS、Azure、GCPといった主要なクラウドサービスとのネイティブ統合を実現しています。これにより、クラウド上でホストされているアプリケーションのセキュリティ状態をリアルタイムでモニタリングすることが可能です。さらに、GitHub Actions、GitLab CI、CircleCIなどのCI/CDパイプラインツールとも密接に連携でき、コードのプッシュやマージのタイミングで自動的にセキュリティチェックを挟むことができます。この柔軟性により、開発から運用まで一貫したセキュリティ監視を実現し、DevSecOpsの実践をより現実的なものとします。
コード脆弱性をリアルタイムで検出・管理する仕組みとは
コードレビュー段階での自動脆弱性検出と警告機能
Datadog CodeSecurityは、コードレビューの段階から自動的に脆弱性を検出する機能を備えています。開発者がプルリクエストを作成すると、CodeSecurityがコードを解析し、セキュリティ上の問題点をコメントとして提示します。これにより、開発者はレビュー中にリスクを認識し、修正対応が容易になります。検出された脆弱性は深刻度に応じて分類され、重要な問題には明確な警告が表示されるため、優先順位付けがしやすいのも特徴です。また、検出プロセスはCI/CDパイプラインと連携しており、継続的なセキュリティチェックが開発フローに自然と組み込まれます。
脆弱性の深刻度に応じた優先順位付けと対応ワークフロー
コード中に発見された脆弱性はすべてが同じ重要性を持つわけではありません。Datadog CodeSecurityはCVSSスコアや攻撃ベクトル、使用箇所などの要因をもとに、自動的に優先順位を付けて表示します。これにより、開発チームはリスクの高い問題から順に対応することができ、効率的なセキュリティ対策が可能になります。また、各脆弱性には修正推奨が付随しており、修正方法や参考リンクなども提示されるため、対応工数の削減にも貢献します。さらに、トリアージ機能を活用することで、組織としての方針に基づいた管理が実現されます。
チーム別・プロジェクト別に管理できるセキュリティレポート
Datadog CodeSecurityでは、セキュリティレポートをチーム単位・プロジェクト単位で出力することができ、組織全体のセキュリティ状況を詳細に把握できます。レポートには検出された脆弱性の数やその内訳、対応状況などが明確に示され、マネジメント層への報告にも活用可能です。また、レポートはPDFやCSV形式でエクスポートできるため、他ツールとの連携も容易です。定期的な自動レポート機能を活用すれば、時間をかけずに進捗の可視化や外部監査対応にも利用できる点が評価されています。
検出された脆弱性の詳細情報と推奨される修正案の提示
検出された各脆弱性については、単なる警告にとどまらず、その背景や影響範囲、推奨される修正案まで詳細な情報が提示されます。たとえば、クロスサイトスクリプティング(XSS)やSQLインジェクションといった典型的な脆弱性には、どのような攻撃が可能か、どういったコードパターンが危険かが具体的に解説されます。さらに、OWASP Top 10などの標準に準拠した分類も行われるため、開発者がセキュリティの理解を深める教育的な役割も果たしています。こうした情報は、Web UI上だけでなく、IDE内やPull Requestにも表示されるため、開発効率を損なうことなく活用できます。
トリアージや例外管理を支える柔軟なポリシー設定機能
すべての脆弱性に即座に対応するのは現実的ではありません。Datadog CodeSecurityは、トリアージ機能や例外管理機能を通じて、組織のポリシーに合わせた柔軟な運用を可能にします。たとえば、軽微な脆弱性については一時的に保留にし、リリース後にまとめて対応する、といった対応方針も設定可能です。また、再発防止のためにポリシーをカスタマイズし、特定の種類の脆弱性が検出された際に自動でアラートを出す、修正が完了するまでデプロイをブロックするといった制御も行えます。これにより、セキュリティとビジネス要件のバランスを取りながら、現実的な対策を講じることができます。
静的コード解析(SAST)の役割とCodeSecurityでの活用方法
SASTとは何か?動的解析との違いと組み合わせによる利点
SAST(静的アプリケーションセキュリティテスト)は、ソースコードやバイナリコードを実行せずに解析し、セキュリティ上の問題を検出する手法です。これにより、開発初期の段階から脆弱性の予防が可能となり、修正コストを大幅に削減できます。一方で、DAST(動的解析)はアプリケーションを実行した状態で外部から脆弱性を検出するため、実行時にしか見えない問題を特定できます。Datadog CodeSecurityではSASTとIAST(実行時解析)の両方を組み合わせることで、コードの静的な構造と実行時の挙動の双方から脅威を検出します。これにより、検出漏れを防ぎ、より包括的なセキュリティ対策を実現します。
開発初期段階で脆弱性を検出するためのSAST導入の価値
SASTの大きな強みは、開発の初期段階、すなわち設計・実装フェーズでセキュリティリスクを把握できる点にあります。一般的に、開発が進むほどに修正コストは指数関数的に増加しますが、SASTによって早期に問題を発見すれば、手戻りを最小限に抑えることが可能です。Datadog CodeSecurityは、コードの保存時やプルリクエスト作成時にSASTを自動実行し、開発者に即座にフィードバックを提供します。これにより、開発者はセキュリティを意識しながら日常の業務を進めることができ、結果としてプロジェクト全体のセキュリティ品質が向上します。
CodeSecurityでのSAST実行プロセスと対応プログラミング言語
Datadog CodeSecurityでは、SASTはCI/CDパイプラインやリポジトリ連携によって自動的にトリガーされます。設定はシンプルで、GitHubやGitLabといったコードホスティングサービスとの接続を行えばすぐに利用可能です。SASTはPython、JavaScript、TypeScript、Java、Goなど、モダンな開発でよく使用される言語に対応しており、継続的なアップデートで対応範囲も広がり続けています。各言語ごとに最適化されたルールセットが用意されており、一般的なコーディングミスから深刻なセキュリティホールまで幅広く検出することができます。
検出結果の可視化とデベロッパー向けフィードバックの仕組み
SASTによって検出された脆弱性は、Datadogの統合ダッシュボード上でわかりやすく可視化されます。各検出項目には、脆弱性の内容、影響範囲、推奨される修正方法が記載され、開発者が即座に対応できるよう工夫されています。また、GitHubなどのリポジトリと連携している場合は、プルリクエストにコメント形式で自動フィードバックを表示させることも可能です。これにより、開発者は自分のコードに対するセキュリティ上の指摘を、その場で確認・修正できるため、セキュアな開発文化が自然と根付いていきます。
SASTとCI/CDの統合によるセキュリティ自動チェックの実現
SASTをCI/CDパイプラインに統合することで、コードのビルドやデプロイ前に自動的にセキュリティチェックを行うことが可能になります。Datadog CodeSecurityでは、GitHub ActionsやGitLab CIといった主なCIツールに対応しており、わずかな設定で導入できます。これにより、開発者はセキュリティチェックを意識することなく、安全なコードだけが本番環境へとデプロイされる仕組みを構築できます。特定の重大な脆弱性が検出された際には、ビルドプロセスを自動的に中断する設定も可能で、ビジネスリスクの回避に寄与します。こうした仕組みは、セキュリティと開発スピードの両立を目指す現代の開発環境において、非常に価値の高いものといえるでしょう。
インストール不要のエージェントレススキャンによる利便性と効果
エージェントレススキャンの技術概要と導入における利点
エージェントレススキャンとは、対象システムに専用ソフトウェア(エージェント)をインストールせずにリモートからセキュリティ検査を実行できる技術です。Datadog CodeSecurityではこの手法を採用することで、既存環境への影響を最小限に抑えながら、コードと構成の安全性を精査することが可能です。エージェントを導入しないため、システム構成の変更やパフォーマンス低下といった懸念がなく、セキュリティ導入の障壁が大幅に低減します。開発者やセキュリティチームはGitHubやGitLabなどのソースコード管理ツールと連携するだけで、即座に脆弱性スキャンを開始でき、スピーディなセキュリティ対応が実現します。
ユーザー環境に負荷をかけずに実行できるセキュリティ分析
従来のエージェント型セキュリティスキャンでは、対象システムのリソースを消費し、場合によってはアプリケーションの動作に影響を与えるケースもありました。Datadog CodeSecurityのエージェントレススキャンは、クラウド上のリポジトリに保存されたコードを対象とし、外部環境でスキャンを実行するため、ユーザー環境に一切の負荷をかけません。また、スキャン対象となるコードの範囲や対象ブランチの設定も柔軟にカスタマイズできるため、必要な範囲だけを効率的に検査できます。これにより、セキュリティと可用性を両立させた運用が可能になります。
設定・導入の簡易さと迅速なスキャン結果取得の特徴
Datadog CodeSecurityは、初期設定が極めてシンプルである点も大きな魅力です。GitHubやGitLabとの連携は数クリックで完了し、APIトークンやOAuth認証を通じてリポジトリへのアクセスを許可するだけで、セキュリティスキャンが即座に有効になります。エージェントのインストールや複雑な構成作業は一切不要で、開発スピードを損なうことなくセキュリティ強化を進められます。また、スキャン結果は数分以内にダッシュボードへ反映され、問題の深刻度別に一覧表示されるため、担当者は迅速にリスクを把握し、優先度の高い対応から着手できます。
クラウドインフラ環境との自然な統合と柔軟な対応力
Datadog CodeSecurityのエージェントレススキャンは、クラウド環境との高い親和性を誇ります。AWS、Azure、Google Cloudといった主要なクラウドプロバイダーのソースコードリポジトリとも容易に統合でき、クラウドインフラ上で開発されるマイクロサービスやAPI、Lambda関数などのコードも包括的にスキャン対象とすることができます。また、IaC(Infrastructure as Code)に対応した設定ファイルのセキュリティチェックにも対応しており、ネットワーク構成やアクセス制御設定の誤りも検出可能です。これにより、クラウドネイティブな開発環境においても、脆弱性の見落としを最小限に抑えることができます。
他のスキャン手法との併用によるセキュリティ精度の向上
エージェントレススキャンは導入が容易で利便性が高い一方、全ての脆弱性を検出できるわけではありません。そのため、Datadog CodeSecurityではSASTやIASTなど他のスキャン手法と併用することで、より包括的なセキュリティチェックを実現しています。たとえば、エージェントレススキャンで事前に検出された構成ミスをSASTで補完し、さらに実行時の異常挙動をIASTでモニタリングすることで、理論上の脅威から現実的な攻撃まで幅広くカバーすることが可能です。複数の手法を統合的に活用することで、セキュリティ対策の「死角」をなくし、組織全体のリスク管理体制を強化します。
本番環境での脅威検出に対応するIAST機能の重要性と活用例
IASTとは何か?DASTやSASTとの違いを解説
IAST(インタラクティブアプリケーションセキュリティテスト)は、アプリケーションが実行されている環境下でリアルタイムにコードの挙動を分析し、脆弱性を検出するセキュリティ手法です。SASTがソースコード静的分析、DASTが外部からの動的テストであるのに対し、IASTは内部で発生する動作とデータフローを可視化し、実際に動作中のアプリケーションから正確なセキュリティ情報を取得します。Datadog CodeSecurityのIASTは、これらの違いを活かして本番環境やステージング環境に近い状態での検出を行い、検出精度の向上と誤検知の低減を実現します。
実行時の挙動に基づいて脆弱性を検出するIASTの仕組み
IASTは、アプリケーションのリクエストやデータの流れ、APIの応答など実行時の動作をリアルタイムでモニタリングし、コードがどのように動作しているかを内部から解析します。たとえば、ユーザー入力がSQLクエリに不正に挿入されている場合、それをリアルタイムで検知して通知を発します。Datadog CodeSecurityでは、軽量なセンサーをアプリケーションに組み込むことで、実行時のセキュリティイベントを収集・分析します。この方式により、テスト環境や本番に近い条件下でのみ発生する問題を特定することが可能となり、SASTやDASTでは検出しにくい複雑な脆弱性にも対応できます。
本番に近い環境での精密なセキュリティ評価の利点
IASTは、開発環境やステージング環境など、本番に近い状況での動作検証に特化しているため、実際のユーザー操作を模倣したセキュリティチェックが可能です。これにより、実稼働時にしか表面化しない問題、たとえば特定のユーザーデータの組み合わせや設定依存の脆弱性などを的確に捉えることができます。Datadog CodeSecurityのIASTは、Webリクエストやバックエンド処理のトレース機能と組み合わせることで、どのパスでどのような入力がどの処理に影響したかを視覚的に表示します。これにより、開発者は問題の根本原因を迅速に把握し、適切な修正を行えるようになります。
IASTにより見逃しがちな脅威を正確に特定する方法
一般的なセキュリティスキャンでは見逃されやすい論理的なバグや、複雑な入力条件下でのみ発生する脆弱性も、IASTでは実行時の挙動に基づいて検出できます。たとえば、条件付きで生成されるテンプレートエンジンの脆弱性や、環境変数に依存する設定ミスなどが該当します。Datadog CodeSecurityは、こうした難易度の高い脆弱性に対しても、実際のデータの流れと処理のトレースをもとにアラートを出すため、誤検出が少なく信頼性の高い脅威検出が可能です。さらに、発見された問題には技術的背景や修正指針も添えられており、セキュリティ専門家でなくとも適切な対応を実行できます。
Datadog CodeSecurityでのIAST活用事例と導入効果
Datadog CodeSecurityを導入してIASTを活用した企業では、実行時にしか表面化しなかった深刻な脆弱性を早期に検出し、重大なインシデントを未然に防いだ事例が複数報告されています。たとえば、SaaS型アプリケーションを提供するある企業では、顧客の設定内容により動作が変化する処理ロジック内で、条件付きSQLインジェクションが存在していたことがIASTによって判明しました。このように、Datadog CodeSecurityのIASTは、実践的でリアルタイムな検出を可能にすることで、従来のセキュリティテストを補完し、より高度なアプリケーション保護を実現しています。
WAFなど他のセキュリティツールと比較したDatadogの優位性
WAF・SAST・IASTそれぞれの役割と機能を比較
セキュリティ対策には様々なツールが存在し、それぞれに異なる強みがあります。WAF(Web Application Firewall)はネットワーク層での攻撃を防ぐためのフィルタリング機能を提供し、トラフィックベースで不審な挙動を検出・遮断します。一方、SASTは開発段階でのコード検査、IASTは実行中アプリの内部挙動を解析する手法です。Datadog CodeSecurityはこれらのうち、SASTとIASTに対応しており、WAFでは見逃しやすいコード内の潜在的脆弱性を事前に検出できます。また、Datadog本体のAPM機能と連動することで、WAFのような外部検知では対応できないアプリケーション内部のセキュリティ可視化が可能です。
Datadog CodeSecurityはどこで差別化されているのか?
Datadog CodeSecurityが他のセキュリティツールと最も差別化される点は、「監視とセキュリティの統合」にあります。多くのWAFやSASTツールは単体で動作し、情報の断片化が起きがちです。これに対してDatadogは、CodeSecurity、APM(アプリケーション監視)、ログ管理、インフラ監視を統合して提供しており、開発から運用、セキュリティに至るまで全体を一つの画面で監視可能です。これにより、アラートの一元管理やトラブルシュートの迅速化が図れるだけでなく、セキュリティリスクの根本原因をパフォーマンス視点と合わせて分析できるのが強みです。
アプリケーションセキュリティにおける包括的なカバレッジ
Datadog CodeSecurityは、コード、構成、依存関係、実行中の挙動といった複数レイヤーにわたるセキュリティ検査を一括で提供します。SASTを使った静的解析では脆弱な記述を発見し、IASTでは実際のリクエスト処理の中で問題を追跡。加えて、依存ライブラリのCVE情報を自動で照合することで、サプライチェーンリスクも軽減します。このように、複数のセキュリティツールが必要とされる機能を一つの製品で完結できる点は、特に開発体制の効率化や運用負荷の軽減に大きく貢献します。WAFでは補いきれないアプリ内ロジックの安全性も担保できる点で、Datadog CodeSecurityは優位です。
セキュリティ運用全体をDatadogで一元管理するメリット
セキュリティ製品が複数存在すると、データ連携やアラート管理が煩雑になり、対応漏れや重複作業が発生しがちです。Datadog CodeSecurityは、既存のモニタリング機能とシームレスに統合されており、アプリケーションのパフォーマンス監視、インフラ監視、ログ分析と一体となって運用できます。これにより、セキュリティアラートもDatadogのインシデント管理機能を通じて整理され、DevOpsチームやSREチームとの連携もスムーズになります。結果として、インシデント対応のスピードと精度が向上し、セキュリティ体制の強化につながります。
他ツールと併用する場合の補完関係と構成パターン
Datadog CodeSecurityは単体でも高機能ですが、既存のWAFやSIEM、EDRなどと組み合わせて利用することで、より高度なセキュリティアーキテクチャを構築できます。たとえば、WAFでネットワーク層の不正アクセスをブロックし、CodeSecurityでアプリケーション層の脆弱性を早期検出、SIEMでログの相関分析を行うというように、各ツールの役割を明確に分担できます。Datadogは各種セキュリティソリューションとのAPI連携も充実しており、サードパーティとの連携も容易です。こうした柔軟性があるため、既存環境を無理なく拡張しながら、全体として堅牢なセキュリティ体制を築くことができます。
開発環境やCIパイプラインと連携することで得られるセキュリティ効果
CI/CDとの統合でセキュリティチェックを自動化する仕組み
Datadog CodeSecurityは、GitHub Actions、GitLab CI、CircleCIなど主要なCI/CDツールとシームレスに統合できます。この統合により、コードがプッシュまたはマージされるタイミングで自動的にセキュリティスキャンを実行し、開発の流れを止めることなく脆弱性の検出と対応が可能となります。特にコードレビュー時に問題が明示されるため、開発者は日常的にセキュリティを意識しながらコーディングするようになります。ビルドフェーズでの自動チェックにより、本番環境へのリスク持ち込みを未然に防ぐことができ、DevSecOpsの実現を強力にサポートします。
GitHubやGitLabなど主要ソース管理ツールとの接続方法
Datadog CodeSecurityは、GitHub、GitLab、BitbucketなどのリポジトリサービスとAPI経由で連携し、スキャン対象のリポジトリを簡単に選択できます。OAuth認証により接続が確立されると、リポジトリ内のコード変更に対して自動的にスキャンが実行されるようになります。プルリクエスト単位で脆弱性が指摘されるため、問題のあるコードがどのように導入されようとしているのかを明確に把握できます。設定はノーコードまたは低コードで完了し、セキュリティ導入の障壁を大きく下げてくれる仕組みです。導入後はスキャン結果をリポジトリ画面上で即座に確認できるため、開発者の作業効率を落とすことなく活用可能です。
セキュリティと開発効率を両立させるDevSecOpsの実現
従来、セキュリティは開発の最終段階でのみ実施されることが多く、対応が後手に回ることが課題でした。Datadog CodeSecurityは開発初期からセキュリティを組み込むことで、DevSecOpsの実践を促進します。開発プロセスに自然とセキュリティチェックが組み込まれるため、セキュリティを「後から足す」のではなく「最初から一部とする」考え方が実現されます。これにより、脆弱性の早期発見と迅速な修正が可能となり、全体の開発サイクルも効率化されます。セキュリティにかかる認知的・時間的コストが軽減されるため、開発チーム全体のパフォーマンス向上にもつながります。
プルリクエスト時の脆弱性検知とデベロッパーへの通知
Datadog CodeSecurityは、プルリクエストのタイミングでコードの静的解析を実行し、問題がある場合はその場で開発者に通知します。この仕組みにより、コードがマージされる前にリスクを排除できるため、本番環境に不完全なコードが入り込むのを防ぐことができます。アラートはGitHubのコメント欄やDatadogの通知機能を通じて送信され、指摘箇所の行番号とともに修正方法も提示されます。これにより、開発者が手元で即座に確認・修正できる環境が整い、セキュリティ対応のスピードが格段に向上します。セキュリティチームに依存せず、各開発者が自律的に対応できる点が大きなメリットです。
テストフェーズでのセキュリティ監視と継続的な改善体制
CI/CDパイプライン内での自動スキャンに加え、テストフェーズでもDatadog CodeSecurityの機能を活用することで、品質と安全性の両立が可能となります。ユニットテストや統合テストと並行してセキュリティスキャンを実施することで、開発者は機能と安全性の両方を同時に確認できます。また、検出された脆弱性は履歴として記録され、継続的な改善のためのナレッジベースとして活用できます。さらに、各リリースごとのセキュリティトレンドを可視化することで、開発チームの成熟度やリスク傾向を定量的に把握することも可能です。これにより、PDCAサイクルに基づいたセキュリティ強化が現実的に実施できるようになります。
脅威をリアルタイムで検出し迅速に対応するための仕組みと機能
リアルタイムで脅威を通知するアラートシステムの詳細
Datadog CodeSecurityは、脆弱性やセキュリティインシデントを検出すると、即座にアラートを発信するリアルタイム通知システムを備えています。検出された脅威は重大度に応じて分類され、担当者に自動で通知されるため、手動による監視やチェックの手間が大幅に軽減されます。アラートは、SlackやMicrosoft Teams、PagerDuty、メールなどの外部ツールと連携可能で、既存のインシデント対応フローに自然と組み込むことができます。これにより、対応のスピードが飛躍的に向上し、セキュリティインシデントの被害を最小限に抑えることが可能になります。
インシデント対応を加速する自動化ワークフローの構築
検出された脅威に対して迅速に対応するには、単にアラートを出すだけでは不十分です。Datadog CodeSecurityでは、インシデント対応のプロセスを自動化するワークフローを構築できます。たとえば、特定の脆弱性が検出された際に自動でチケットを発行したり、Jiraと連携して修正タスクを割り当てたりすることが可能です。また、修正が完了したことを検知して再スキャンを実行する自動ルールも設定でき、対応から検証までのプロセスがスムーズになります。このような自動化により、人的ミスや対応遅延を防ぎ、セキュリティ運用の効率が大幅に向上します。
検出から修復までの流れを支援するインサイトとダッシュボード
Datadog CodeSecurityには、検出から修復までの一連のプロセスを支援する直感的なインサイト機能とダッシュボードが用意されています。各脆弱性については、発見日時、影響範囲、推奨対応、対応者などの情報が時系列で表示され、進捗管理が容易になります。さらに、ダッシュボードではプロジェクトごとの脆弱性件数や対応状況、解決までに要した時間などもグラフ表示され、全体の健全性を俯瞰できます。この可視化によって、開発チームはどこにボトルネックがあるのかを把握し、より効率的なセキュリティ体制を構築することが可能になります。
アナリティクス機能による脅威傾向の分析と改善施策の立案
Datadog CodeSecurityは、単なる脆弱性検出ツールにとどまらず、検出結果をもとにした脅威分析も可能です。たとえば、ある期間に特定のプロジェクトで発生した脆弱性の種類や頻度、修正までに要した時間などを自動的に集計し、リスク傾向を可視化します。これにより、特定のチームやモジュールで繰り返し発生している問題を特定し、根本原因に対処するための改善施策を立案することができます。分析結果は、エンジニアの教育計画やコードレビューの強化などにも活用でき、組織全体のセキュリティ意識を高める基盤として機能します。
セキュリティ対応の迅速化を実現するAIベースの推奨機能
Datadog CodeSecurityでは、AIを活用した脆弱性対応支援機能も提供されています。たとえば、検出された脆弱性に対して過去の修正履歴やベストプラクティスをもとに、具体的な修正方法を自動で提案する機能があります。これにより、開発者は自ら調査する時間を削減でき、より迅速に対応可能になります。また、AIはプロジェクトの履歴や組織の対応傾向を学習し、最適な対応フローや優先順位付けの指針を提示するように進化していきます。こうしたインテリジェンス機能により、属人的だった対応作業が標準化され、組織としての対応力が強化されます。